2012-02-13
引越し魔のルーツ。
去年5月末、東京から大阪へ戻り、先月末、また大阪から東京に戻ってきた。ただでさえ体力も時間もお金も消耗激しい引越しだが、これで通算19回目ともなると、口ではイヤだとほざいてみても、もはや好きでやってると思われても仕方がない。
しかしながら、ふと思う。引越しみたいなガテンな現実は、幾たび繰り返したとしても、それが色香や情緒の端緒につながることはまずないと。転職、転業、結婚、離婚、出産も然り、憲法で権利と自由が保障されている分野の労苦とチャレンジは、人並み外れた回数こなせばこなすほど、憂い、惑い、躊躇い、思慮深さという情緒や知性が態をひそめ、代わりにヘンな胡散臭さ、残念な軽さ、浅さ、甘さ、鈍さが妙に際立つ向きがある。これが最後と繰り返すあやまちが奔放な魅力や妖艶な色気につながる唯一の所業があるとすれば、そう、それが「恋」というものなのか・・・ などと、ドアも窓も開けっ放しの寒風吹きすさぶ部屋で、凍える寒さに震えながら、今一番どうでもいい「恋」という文字を浮かべてみたのは他でもない。何かの本で、世界的クライマーの「凍死寸前には、最もろくでもないことを考えるものさ」という言葉に、ちょっと習ってみたかっただけだ。なるほど、たしかに、あまりのどうでもよさにアホらしくなって気は紛れた。が、寒いもんは、寒かった。
思えば、生まれてこの方42年。およそ差し迫った事情だけでひたすら転々と動き回ってきたせいか、“落ち着く”ということに免疫がない。しばらく何ごともない平穏な生活が続くと、妙にそわそわ落ち着かなくなってくる。それもこれも、これでしばらく落ち着けるかなと思うやいなや、必ずや何かが起こり、引っ越さねばならない事態に陥ってきた経験が割合豊富だからだ。そのため「落ち着いたら、何かが起こる」という脅迫感から、日々「うっかり落ち着いたらあかん」と自分に言い聞かせ、それがまた落ち着けない気運を呼び込むのか、結局、また動かざる得なくなる。ひと言でいうと、小心なのだ。
わたしがもっともハイペースに動いていたのは、7歳から20歳までの13年間で、その間の引越回数は11回。その時、その時の親の事情、お母ちゃんの判断、決断、思惑、感情、ひらめき、思いつき、気分にひきずられるように、東淀川区と淀川区の2つの区内を年に1度のペースで動き回っていた計算になる。そんな過去を振り返ると、今回のようにパートナーの転勤という世間通りのいい理由で引っ越せるというのは、自慢に聞こえるんじゃないかと躊躇われるほどだ。
その当時、わたしが小学生の頃の引越しといえば、引越会社など頼まず、母子3人せっせと家内作業で済ませるのが常だった。それは何も昭和50年当時に引越サービスがなかったわけでも、自分の家だけが特別そうだったわけでもない。引越屋のトラックがでかでかと停まっているのは、ええ氏の金持ちか、ええ会社に勤めてはる人の家か、景気のええ商店・自営の家くらいで、まわりの親戚、友だちの家など大抵の引越しは自分たちでやるのがあたりまえだったし、やればできることに何万も払うような余裕などほとんどの家になかったように思う。
自分たちで移動・搬入出することを前提とすれば、引っ越す家は近所に限る。だからわたしの家も、引っ越す家は毎回元の家から歩いて5〜10分程度の至近距離で、それゆえ新しい家にせっせと荷物を運び入れるアリの巣作りのような引っ越しを難なく繰り返せたのである。さらには、同区以外に越してしまうと転校を余儀なくされるので、親としては何とか近場で済まそうと思いやってくれたというのもある。にしても、1〜6丁目まである町内、住んだことがないのは2丁目だけという細かい動きにいったいどれほどの意味があったのか、他に方法はなかったのかと、お母ちゃんのせせこましくエネルギッシュな生き方には今もって疑問が残る。とはいえ、毎回引っ越しの度、ダンボールに荷物を詰め込みながら思い至らされるのは、こんな面倒な作業を1年おきに、しかも子ども2人、ポメラニアン1匹、アップライトピアノ1台抱え、何くそ、何くそ繰り返していた母親のクソ根性のものすごさ。娘としては到底叶わないと敬服するも、同性としては「わたしは違う」とライバル心を燃やす。が、気づけば母親と同じ轍を踏んでいるのだ。
そんな母と弟の3人、あの家この家、転々と暮らしていた昔。夕ご飯を食べ終えるとお母ちゃんがどこからか拝借してきたリヤカーに荷物を積み、夜な夜な新しい家に荷物を運び入れていく。今の家から徐々に物がなくなって、次の家に自分の家ができあがっていく。現在のわたしにすれば、そんなちまちまと面倒で手間のかかる引越しなど絶対に御免だが、小学生のわたしは「これまでの家」と「これからの家」を行ったり来たりする過程に、よりよい明日へ向かっている実感を得ていたのかどうか、ともかく新しい家に越せば、今より良くなる希望と期待に胸弾ませ、無性にうれしかった記憶がある。そんな子ども時代の思い出の中でも、格別の盛り上がりを見せたのは、母親が一時同棲した相手と別れたときの引っ越しである。アイツがいなくなってお母ちゃんと弟の3人だけで生活が始まると思うと、たとえ移り住むのが悪臭漂う川沿いの木造長屋の文化住宅でも、わたしには美しい湖畔に立つ夢の城に見えた。わたしと弟は今もそれを「バラ色の引っ越し」と呼び、年に一度正月に会うたび、後にも先にもあんなに自分の未来が輝いてみたことはなかったと情けなく振り返るのがクセである。
向田邦子や小津安二郎の昭和の家族の物語には、必ず長く住み続けた「家」が登場する。悲喜こもごもの家族の思いや人生に寄り添うように、たゆたうように静かに流れる時間そのものが家なのだ。その都度その都度、転々と暮らしてきた自分は、そこに脈々と流れてきた膨大な家族の歴史を感じさせる大河ドラマのような包容力のある「家」に無性に憧れを抱いてしまうが、それはきっと自分にないから良く見える、ないものねだりでしかない。
家の歴史、家族のルーツでいえば、それこそわたしにも「パパが居った家」「パパとお母ちゃんが別れた家」「アイツが居た呪いの家」「3人だけで楽しかった家」、「バブ(養父の愛称)が来た家」「バブのおかげでバブリーだった頃の家」「バブが狂った家」・・・等々、人間のややこしい喜怒哀楽と込み入った事情が織りなすドラマがなかったわけではない。ただ、いかんせんスケール感がない。そのかわり、しみじみ考えなくても、何が間違いか、誰が悪いか、なんでそうなるのか、ものすごくわかりやすい。見どころは、「全部です」といいたいくらいに。
かくして、いつ見てもドタバタとせわしないわたしの引越しアクションドラマは、母親編から娘編へ、大阪から東京へ舞台を変え、これからも続いていくことだろう。嗚呼、続いていくのか・・・。

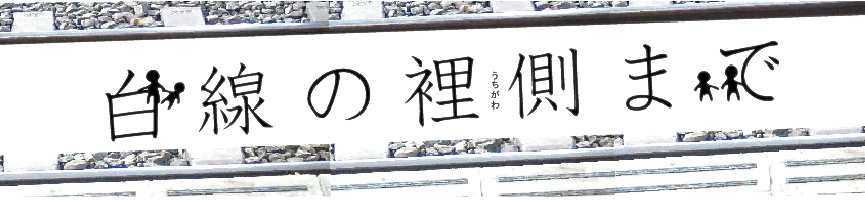

3件のコメント
向田邦子も転勤族の家族だったのでカブるところがライターとしてはあるような、ないような…。
「バブが狂った家」というのがとても気になります。
ご意見、ありがとうございます。そうあったら嬉しいものは、ないもんですね(苦笑)そしてバブ、バブかぁ・・・。あの東電幹部の奇怪な顔ぶれ、物言いを見るたび「バブ的な偏狂」を感じます。
なぜか泣き笑いしました。ぜひ出版しませう。
コメントする ※すべて必須項目です。投稿されたコメントは運営者の承認後に公開されます。