2012-04-12
映画「KOTOKO」ー恐るべし母の愛
東京の桜も満開の見頃を迎え、うららかな春の光と風に包まれた先週の土曜日。花も嵐も関係なく、今年始まって以来、連続出勤記録更新中で今日も元気に休日出勤のおーちゅんに「Coccoの映画で、自分を痛めてくる」と言い残し、「痛そうやな、気をつけて」と見送られ、塚本晋也監督作、Cocco初主演「KOTOKO」を観に行った。上映初日だけに満員かと危ぶまれたが、残り3席の幸運に恵まれ、最後列末席の遠目から塚本晋也監督の舞台あいさつにも預かれた。
映画の舞台あいさつでは携帯撮影禁止が通例だが、「どんどん撮ってください。そして、感想やコメントを書きこんで、できるだけ多くの人に広めてください」と、もったいつけずフルオープンな塚本監督。ベネチア国際映画祭グランプリ受賞を始め、ヨーロッパの映画賞を総なめに絶賛の評価を得ている気鋭の映画監督であるにもかかわらず、その謙虚で誠実で寛容な人柄にまずもって心打たれた。
本作は、Coccoの歌、Coccoの存在そのものに強く心揺さぶられ、「最も尊敬するシンガーソングライター」として敬愛してやまない塚本監督が、Coccoとの対話を繰り返し、Coccoの脳内と監督自身の内面を重ね合わせながら手探りで作りあげた母と子の愛の物語であり、全女性たちへ捧げる映像賛歌である。クランクインと同時に大震災があり、撮影を延期することも考えたという塚本監督だが、その心を動かしたのは、震災後、子どもたちを守るため必死で闘うエキセントリックな母親たちの姿だったという。
パンフレットには、7年間の介護の末、昨年7月、母親を看取ったという監督の言葉が綴られている。そんな監督自身の亡き母への思いと、Coccoの母としての覚悟と決意が結実した本作には、生々しく激しく痛ましい母の愛、母の嘆き、母の叫びが炸裂し、血まみれのあたたかさに溢れている。
それは、ありきたりな母性神話やおしゃれで素敵でハッピーな母親幻想をこっぱ微塵に打ち砕く、本能剥き出しの“母なるもの”の凄まじさだ。
何というか「この子の七つのお祝いに」の岸田今日子とか、見るからに狂った母親ホラー&ミステリー作品でない限り、どうも「母物」となると、たくましく美しくあたたかくすべてを包むのが母の愛みたいな過度に美化された立派な母親像に興ざめすることが少なくないのだが、この作品にはそういう虚像が一切ない。それは、Coccoが演じ表現したKOTOKOという母親が、過剰に溢れやすく、自ら壊れがちな女性心理そのものだったからだ。
泣きやまぬわが子を片腕に抱き、よしよし、よしよし、火にかけた中華鍋をやかましく返すKOTOKO。赤子は一層火が付いたように泣き叫ぶ。よしよし、よしよし、炒めた野菜を皿にのせる。もうちょっと、もうちょっと・・・なのに、泣いて暴れる赤子の足が皿を蹴り、皿は割れ、料理はこぼれ、琴子は壊れる。うわぁーっと鍋を壁にぶつけ、泣き叫ぶ赤子を抱きしめたままキッチンの床にへたれこみ泣き叫ぶ。大事なことはわたしが一番わかっている。だけど無理なときがある。無理な自分もいる。大事、大事、大事と自らを焚きつけ、無理、無理、無理と燃え盛り、けもののように咆吼するKOTOKO。孤独と不安の極致に追い詰められるたときの女の自爆と暴発を見せられたようで、わかるだけに身に凍みて痛い。
一瞬たりとも手が離せない、離れられない、逃れられないかけがえのない思いに、自分が自分で耐えきれなくなる。それもまた世の母親が葛藤する現実だ。「ねんねんころりよおころりよ 寝る子の可愛さ 起きて泣く子の憎らしさ」と、昔から母親たちが子守歌に歌ってきたように、愛おしさも憎々しさも、「あなたがいたから」も「あんたがおらんかったら」も、母親としてあるべき感情もありえない感情もごちゃ混ぜに愛情いっぱい迫ってくる。それが恐るべき母の愛というものだと、自分の母を思い返すとそれでいいんじゃないかとわたしは思う。
わが子を守りきれない困難に崩れそうな母親、誰にも頼れない孤立と孤独の中で、振り絞った弓のような緊迫感でギリギリ自分を保ち続ける母親、世の母親たちが抱える不安、苦悶、現実を一心に背負い、KOTOKOは愛し、嘆き、狂い、歌う。
ラストシーン。すっかり大きくなった小学生の息子が病院に面会にやって来る。もはや言葉もなく微笑みもなく、わが息子に何も与えて上げられないKOTOKOに、また来るから、バイバイと去っていく息子。一度去ったと見せかけて、木の陰からひょっと手だけ出して、バイバイ。その仕草は、赤ちゃんだった頃、KOTOKOが息子にいつもしていたバイバイ。息子が何もわからない小さなとき、KOTOKOが必死に手をかけ与えた愛情は、遠く離れていても、褪せることなく失われず、その子の中で大きくなって生き続けていた。母は壊れても、母の愛は何にも耐えてあり続ける。それは母にとっても子にとっても、絶対に失われない希望に思えた。
狂ったように尾羽を打ち鳴らし、必死にひな鳥を守る母鳥がいなければ、ひなたちは一瞬にして餌食となる。人間もそうだ。自分が何もできないとき、何も覚えていないときに自分のためにすべてを捧げ、闘い、祈り続けた母、母なるものがいなければ人は誰も生きられない。けれど、いつか子どもは母の腕を離れ、「もう、ひとりで飛べるから。大丈夫だから」ありがとうバイバイと手を振って、自分の空に飛び立っていく。そしていつか、背負った子に背負われるときが来る。それもまた、母が味わう悲しみなのか喜びなのか、寂しさなのか救いなのか。
KOTOKOは、わが子を守る母親の究極の愛の形であり、世の母親がみなKOTOKOのように凄まじく激しくむき出しの愛で突っ走っているわけではないだろう。愛し方も闘い方も守り方も、それぞれの気力、体力、感情の波の高さ、血の気の多さなど、個々のレベルに応じて様々にあるわけで、母親たちが皆、苛烈に過酷を極めるコマンドーだったら、それはそれで夫・父親としてはとんだ災難、受難である。わたし自身は、むき出しのKOTOKOの痛みに、おまえは自分が守りたいものを守り抜く覚悟があるのかと、きつく問われたようで、確かに少々ぐったりしている。
そうだ、とにかく、KOTOKOのごとき剝きだしの母性にせよ、おしゃれでハッピーなママにせよ、素敵に頑張る働きママにせよ、あるべき理想の母親像に母親たちが苦しみがちな世の中なので、人の親ではない第三者の立場としては、こう言いたい。母親は、おかあさん、ママ、おふくろ、おかんとしてそこに居るだけで、誰が何と言おうと子どもにとってはこの世で絶対最強の母親なんじゃないかと。
なぜなら、わが子を脅かすものに狂ったようにに立ち向かう強靭で獰猛で滅茶苦茶な母。わが子を守るためなら人殺しでも何でもやりかねない母なるものに、途轍もない希望と最強の力をもらい、わたしは今、生きている。だから、KOTOKOの苦しさに、どうしても泣けた。母親とは何かと言われたら、それは人類共通、永遠不滅の泣きどころだ。それが、愛ってことか・・・。

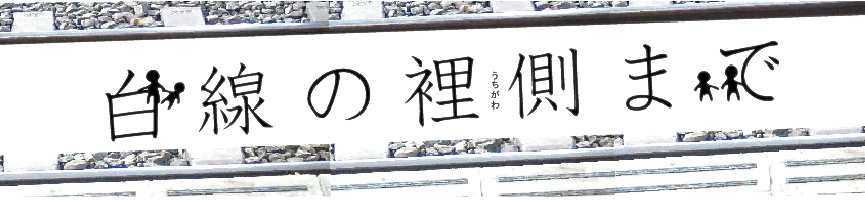

2件のコメント
まだ、自転車こいで、健康ランドにパートに行く
昭和16年、種子島生まれの 母…
自分も 40才を超え、子供も自立し始めた 今…
やっと、オカンの『偉大さ』と『愛』を痛感してます。
読みながら、ちょっと 涙がこぼれました(^^)
いつも、オモロい話 感謝してます(^^)
秀虎さんのおかん話、むっちゃ好きです。
わたしの亡き母も、昭和18年生まれ、隠岐の島出身、死ぬまで住み込みで働きながら、しっかり恋してました(苦笑) お互い似たような泣きどころを持ってるわけですね。いつも読んでいただき、こちらこそありがとうです。
現在、コメントフォームは閉鎖中です。