2019-02-22
平成の暮れ、昭和が灯るよ、寅次郎。そして…
昨年の夏に発表された天皇陛下の生前退位。ああ、いよいよ、平成も終わるのか。そう思うと、子どもの頃、最も古い元号だった明治のひとと同じ位置へ繰り下がっていく時の流れがしのばれる平成が淵のほとり。
わたしの明治生まれの母方の祖母、カ子コと書いて「カネコ」と読む、ひと呼んでカネばあちゃんも、よく言っていた。明治・大正・昭和と、三世も生きられるなど望むべくもない幸せで、もはや今この昭和にある命など、いつ迎えが来てもかたじけなきおまけだと。それが明治という時代なのか、とにかく何かにつけてカネばあちゃんのセリフには、かくなる上はの信念、覚悟が凄かった。
今でも、そんなこと孫の前でよく言えたものだと苦笑いに思い出すことがある。
カネおばあちゃんの傍らでチラシの裏にお絵かきしているわたしを見て、茶飲み話に立ち寄った近所のおばちゃんの「女のお孫さんは大人しくて、かわいいでしょ」。
何気ない愛想文句のひとつにも容赦なく、真剣そのもの振りかぶった紋切り口調の隠岐弁で「ええぃ!そげなことないですだ(そんなことはありません)。孫は孫でみな同じ、されど、家の大事は男の子。女の孫より、男の孫がかわいいですだ!」
まさか、そうやったんや、カネばあちゃん…。「女の孫は大事ではない」というカネばあちゃんのとりつく島のない宣言に、耳を疑った幼いわたしだったが、女の孫であるわたしの存在を否定して傷つけても、人の手前とごまかすことも適当に流すことも許さず、おのれの信念を貫き通すカネばあちゃんの一本気な武骨さの方が、自分の一抹の悲しさなどより圧倒的にケタ違いに深く力強い衝撃だった。
その当時、カネばあちゃんは70歳。宝来苑という下宿アパートの管理人として住み込みで暮らしており、わたしと弟は、学校が休みに入ると、女手ひとつ子どものことなど構っておれないおかあちゃんの代わりに、カネばあちゃんの世話に預かり6畳一間の管理人室で寝泊まりしていた。カネばあちゃんとの生活といえば、毎朝、目覚ましがわりに聞こえてくるのは、戦死したお祖父ちゃんの仏壇に唱える「南無阿弥陀仏」。日曜の早朝は、高島屋「皇室アルバム」を正座して観た後に聞かされる君が代の歴史。アパートの掃除となれば、手ぬぐいを頬被りにたすき掛け、モンペ姿でほうきを握る、まさに戦時中の婦人の装い。ときに管理人室に現れるセールスマンや空き室確認の不動産屋の来客が「男だ!」と見るや、管理人室の小窓をわずか一寸しか開けず、長刀持って身構えるがごとく「あなた様は何用か!」と振りかぶる時代錯誤なレセプション。銭湯に行っても、たとえそれが女しかいない女湯であっても、のほほんと真っ裸でくつろぐなど、女人たるもの言語道断。片手でしわしわの乳を、今さらいったい誰が見るかという女の操を押して忍ぶように湯に浸かる巌窟な羞恥心と貞操観念。そのすべてが昭和ではない、明治のひと、昔のひと。
そんなカネばあちゃんもおかあちゃんも、生まれたときからそこにいた人々が逝き、時は流れて、わたしひとり歳だけとって、めぐりめぐる今年の四月。春のさくらも散り果てる頃には、わたしもカネばあちゃんのように三世前の「昔のひと」になると思うと、なんだかな。いつしか来た道、いつか行く道、わたしは、どこまでいつまで自分で行けるのやら…
二度とは来ない時代の思い出いっぱいに暮れてゆく平成の茜空を見上げると、どこをどうやってかここまで歩いて来たはずの昭和を振り返らずにいられない、と、振り返ったところで、どこにもない帰り道。
いよいよ昭和の岸辺ははるか遠く、もはやどんな好天に恵まれても見えるわけない島の影という心許なさ寂しさに、今一度かぶりつきたい昭和まみれの草団子。どいつもこいつも昭和なやつしか出てこない不朽の昭和とくれば、これしかない、「寅さん!」。
ということで、平成の終わりにまだ言うかの昭和ブルースを唸りたいわたしである。
わたしが子どもだった昭和50年代は、正月映画といえば、「寅さん」と「トラック野郎」の二本立て。それは、大衆庶民の新年一発目の景気づけであった。子ども時分は、菅原文太演じる度胸千両の一番星、運転しながら牛乳をチューブで吸い込む愛川欽也のカモメのジョナサン、お呼び出ないおとぼけ警官・由利徹、そして、なぜか最終的には身ぐるみ脱がされ「いや〜ン」と路上にボインと置き去られるあき竹城というくっきりわかりやすいキャラクターに幼い好奇心は簡単にかき立てられ、当然「一番星」がお気に入り。
けれども人生、その歳に至らねば、そこまで行ってみなければわからない行き止まり、落ちて来ない洗面器があるもので、大人になって流れ流れにもまれもまれた年の波に打ち寄せられる30歳も40歳も過ぎてくると、途端に沁みて懐かしくなる「寅さん」のあったかさ。どんなに自分がパッとしない鳴かず飛ばずに役に立たずなものに思えるときも、寅さんの話を聞くと、なんだか悩んでいること自体がバカらしく、だんだん捨てたもんでもないように思えてくるアホらしい気持ちよさ。それを今風に言うと愛なのかラブなのかアムールなのか、日本人ならそこは人情というべきだと、いくら外国に住もうが外国人と暮らしていようが、そこだけは譲れない。
昭和と平成。いったい何が違うのか。何が変わったのか。何が失われたのか。そんな難しい議論は、朝まで生テレビの政治家、学者、論客たちにまかせるとして。わたしが、この平成30年が幕を閉じようというこの期に及んで、昭和にはゴロゴロいて、平成にはめったと見なくなったものはと思い起こすのは、それは、見るからに自分の過去、因縁、性、業を燃やしてもくもくと生きている内燃エンジン・ディーゼル車みたいなひと、正しかろうが間違ってようが迷惑だろうが捕まろうが、燃え尽き果てる我が人生に悔いなしの怒濤の走りを見せる人間、だろうか。
もし、昭和の人間 100人がツイッターやブログをやれば、100人ともが大炎上間違いなしに違いなく。話せば話すほど話にならない凝り固まった精神論、経験則だけで物事を決めつけるひと、過激以外の考え方、生き方があることを知らない極端なひと、中国を「シナ」、障害者を「かたわ」、犬猫ペットを「畜生」と言ってはばからないわたしの祖母みたいなひと、うっかり人前に出せない厄介な当代きっての曲者が、テレビにも身内近所にも世の中にもウヨウヨあたりまえにいた時代。それが昭和。
銀幕のスターを紐解くまでもなく、わたしの記憶のスターであるおじいちゃん、おばあちゃん、おかあちゃんの人間性を振り返っても、言うことはひどいがやることは本気千両、いいも悪いもありったけの生々しさを発散して生きている人間が主流だった。それは「寅さん」に出てくる登場人物、葛飾柴又帝釈天の御前さまから、おいちゃん、おばちゃん、タコ社長、頭の足りない源ちゃんに至るまで、言うことなすこと思うこと考えることすべてがおまえ以外の何者でもないおまえがおまえ、てめえ、よくもそこまで! という人間どもが猛威を振るっていた時代。なぜなら、今のわたしたちが、言うことなすこと、どぎつい、えげつない、ありえない、生けるハラスメントみたいなやつに出くわしたら、きっと必ず、その人のことをこう表すだろう。
「もう、なんか、すべてが昭和やねん…」と。
そして、そんな昭和の濃密なひとのえぐみやアクを、江戸っ子ならではのカラリと後腐れない口上で笑わしてくれる、フーテンの寅次郎。けれど、そんなあったかい人情以上に、五十を前にした自分があらためて見返して初めて気づいたぬくもりがある。それは、寅さんの人柄、言葉というより、そんな寅を寅のまま、どうしようもなく赦してくれるひとがいるからこそ、ひとは自由に旅ができる、わたしがわたしで生きられるありがたさ。
風の向くまま気の向くまま、テキ屋稼業の根無し草、生まれて初めて見たものを親と慕う動物並みに出会った女性に恋をする素晴らしくシンプルな純粋さ。そんな寅さんは、日本人が憧れる「自由」の象徴のように思ってきたが、少なからず外国暮らしを味わった今だから気づかされる、戻れる祖国、戻れる故郷、待ってるひとがそこにいてこそある、わたしの自由。
あてもない旅にふと迷い疲れたら、「おうっ!」と何食わぬ顔で帰れる、連絡も予約も契約もなくいきなり現れても寝る布団が敷いてある「とらや」の尊さ、ありがたさ。寅さんに言わせれば、田舎もんの教養のねぇ年寄りのおいちゃんおばちゃん、たったひとり血を分けた妹・さくらと取り柄と言えば真面目なだけでひとつも面白味のねぇ亭主のヒロシ、それでも気持ちだけはあったけぇもんが、そこには必ず「おかえり」と待っている。だからこそ、寅さんは、思いっきり裸の心で旅を続けられるのではないだろうか。
旅の途中で懐寂しく恋破れ、どうしたもんかと立ち止まりたいそんなとき、「とらや」のない寅さんは、果たして寅さんでありえたか、あり続けられただろうか。帰る場所も戻る家も金もなく歩き続けるフーテンの旅。となると、「フーテンの寅」ではなく蒸発の寅? いや、難民の寅? そう来られたら、どこに笑える余地があるかということに、無性に揺すぶられ、さすられたわたしであった。
どいつもこいつも言うこと成すことすべてが昭和としか言いようのない寅さんシリーズだが、寅さん、おいちゃん、おばちゃん、タコ社長は昭和でしか通用しない人物で、平成もそのまま何の障害も炎上もなく渡っていける、どんな元号、時代に変わろうと、柔軟にその時代を生きられるのは、自分のことより人の気持ちを大切にいたわる筋金入りの女神精神を持つさくら、そして、つねにニュートラルな視点から本質をわかりやすく解説しようとする池上彰のような亭主のヒロシ。わたしひとりの肌感触で決めつけさせてもらえるなら、昭和の主流は、寅さん、おいちゃん、おばちゃん、タコ社長。そして、平成の主流は、さくらとヒロシ。誰もが自分らしく心地よく暮らせる社会へ進まんという進化の法則に添えば、それはもう多種多様なさくらとヒロシが主役を張るしかない。その方がひととひととの衝突も軋轢もしがらみもなくいられるという流れには、わたしも、大いに賛成だ。
何しろ、繰り返すが、わたしが子どもの昭和40、50年代は、今では考えられないような差別や偏見、人生うまくいかない原因のすべては、おのれを見つめ直すより、先祖のたたりだ因縁だと大騒ぎに墓やツボを買いに走るいい歳をした大人たちが五万といた。自分の夢や希望を語ったその場で「身の程を知れ!」と斬り捨てられ、可能性や個性、ポジティブ思考、平成の今なら尊重されて然りの「個」が、全部まとめて「世の中、そんな甘ないぞ!」でぶった斬られる時代でもあった。そう、それは今思えばひどい言葉も扱いもあたりまえにあった。けれども、そのひどさと同じ熱量、感情馬力で、ひとの心を揺さぶる人間がいたことを、わたしは忘れたくないのである。
寅さんの数多あるエピソードの中で、言ってみれば、これが昭和のひとで、これが平成のひとか、と、その感触の違い、味の違いを噛みしめた場面がある。
京都を旅する寅さんが、ひょんなことで人間国宝の陶芸家・加納作次郎と出会い、そこから加納作次郎の秘書兼まかない婦をしているいしだあゆみ扮するマドンナ「かがり」に恋をする回。
作次郎がどれほど有名な陶芸家であるかなど知ったこっちゃない、ご大層に湯飲み茶碗を作っている道楽じいさんとしか見えていない寅さんは、おのれの料簡、おのれの次元、おのれの経験則だけで思ったことを思ったように口にする。
作次郎の元で12年修行中の弟子(柄本明)に親切心を振りかぶって講釈を垂れる寅さん。
「じゃあ、おまえさんは12年も修行してんのかぃ? そいつは見込みねぇんじゃないか? にんげん、他にいくらでも生きる道はあんだから、よぉ」
そんなこと、ひょっと現れた他人に言われたら誰でも怒るに決まっているだろう失礼なことを言っておきながら、言われた弟子がむっと気を害して顔をしかめると、「こっちは心配して言ってやったんだから、怒んなよ」となだめかかる。そういう「おまえが言うな」のふてぶてしさと可笑さがとぐろ巻いてそこにいても赦される、なぜなら、それが寅さんだから。
そこから、この人間国宝・作次郎。「ええもん作りたい、ひとに褒められよう、そんなこと思ったら、ろくなもんはできん。作るんやない、掘り出すんや!」と、おのれの内なるろくろと窯で、あるがままの土からあるがままの美を焼き上げる陶芸の真髄を語るそばから、「えらいっ、その向上心!うちのあの年寄りの団子職人に聞かせてやりてえよ」と、次元を越えた単純な返しを入れる寅次郎。
いかなる高みにある人物の真言も、すかさずおのれの漁場に引き寄せる自由自在な寅次郎の地引き網。自分の尺でしか物事をとらえない寅さんの素直で強い「個」。
世の中というものは、どんなに時代が変わっても、そこはお構いなしに何を言っても赦される人と人の間があってこそ成り立つものではないかと、ひとのしくじり、勘違い、言葉尻をとらえては正義の炎を振りかざし火あぶりにされてしまう昨今をかんがみるわたしである。
そして、そこに漂う平成の素敵な薫りが、今回のマドンナ・かがり、である。作次郎の弟子の一人、今や陶芸界でめきめき名を上げのし上がる神原とかがりは、ひそかに恋仲にあった。ところが神原は、かがりとのことはなきも同然に、出世と名誉のためあっさり良家の娘と結婚することを師匠の作次郎に御丁寧に報告に来る。
かがりと弟子・神原の関係を陰ながら見守っていた師匠・作次郎は、無論、この一番弟子の薄情さに承伏しがたい憤りと情けなさを打ち鳴らし、「好きにせえ」と絶縁を言い放つ勢いで自室にこもる。
そんな師匠を慮って「ご心配をおかけして、すみませんでした」と謝罪に現れるかがり。そのときの作次郎の叱責、怒りの文言セリフが、これまさに昭和の骨頂なのだ。
「なんで私に謝らんならんねん!これ、あんたのことと違うんか。あんたが幸せになれるかなれんかという問題ちゃうんか。あんたほんまに神原を好きなんか?」
声もなく、「はい…」とうなだれる、かがり。
「それやったら、なんであんた、あの男の首玉にしがみついてでも一緒にならへんかったんや! 他人に気ぃばっかり遣って生きとるあんたを見てるとな、時々、もう、腹立って、腹立ってしゃあない時あるねん。人間というもんはな、ここぞと言う時には全身のエネルギー込めてぶつからへんかったら、あかへんねん。それがでけへんようなら、とてもやないけど、あんた、幸せにはならへんわ!」
当事者のかがり以上に嘆き、憤り、燃えさかり、どうにもこうにも辛抱たまらぬ最後の締めに、「あんた、幸せにはならへんわ」。神原が与えた裏切りの傷よりもなお深く刺さる呪いの文句を全身全霊込めて叩きつける作次郎。
ただ、しかし、作次郎の切り捨て御免の怒りの作法は、わたしの昭和当時は家庭でも学校でも職場でも友人同士でもご近所同士でも、日常茶飯そこらじゅう、ざらにあった流儀である。おそらく、作次郎みたいな明治大正、そして昭和の人間がこの世から去ってからの平成30年、それは、いつしか今度はかがりのように、人に気ぃばっかり遣ってしまう人間が気を遣い合う思いやりの時代となり、あげくに「自分をさらけ出すって?」「ありのまま生きるって?」みたいな吐息のようなつぶやきをみんなでシェアして考えようという、言っちゃ悪いが正直「知らんがな」のイチモツを表立っては誰も言えない時代になったような気がしないでもない。
誰も真っ向真剣には斬り掛かってこない、平成が辻。それはそれで傷つき倒れる心配はないのかもしれないが、ひと誰しもが心に隠し持っている牙や刃を誰にも何にも向けることなく、向けられることなく、人は人として生きられるものなのか。
あれは確か、わたしが高校生の頃。あるとき2階の部屋にいた私の耳に、階下の玄関でガラガラガッシャーン何かが崩れる物音が響くと同時に、「えらいこっちゃー!」というおかあちゃんの叫びがけたたましく聞こえた。けれども、そのときのわたしは、転げるように階段を駆け下りることもなく、「何があったんかな?」と案じつつも、部屋から動かずそのまま雑誌の続きを読んでいた。すると、「おまえというやつは!」と跳び蹴られる勢いで般若の形相で飛び込んできたおかあちゃん。
地上げか借金の取り立てか「なめてんのか、われ〜」の剣幕でまくしたてられた、そのとき、何がどうだったか。それは、わたしにすれば、そもそも、下駄箱の上に何でもかんでも物を積み過ぎていた自分のクセがたたってのことではないかと言いたいような過剰な積載量ゆえに、下駄箱の脚が折れ、積んでた物が総崩れ、その足元に丸まっていた愛犬ルルちゃんが危機一髪という、ガラガラガッシャーンだったらしい。
そんなルルちゃんが生きるか死ぬかの一大事に、おまえはなぜ、「あれ?」と思っている余裕があるのか、何様じゃ! というのが、おかあちゃんの炎の芯だったのだ。そのときのおかあちゃんの、まさしく人間が持つエネルギーの凄味に、わたしは、それこそ、かがりじゃないが、声もなく「うん」とうなだれるだけだった。
「あんた、よう、覚えときや。なんぼ思った、思ったゆうて、なんも動かず、なんもせんかったら、あんたの思いみたいなもん、全部ウソや! 人間、一番大事なんは、初動や。思わんでも動く、それが人間や!」
そこだけは、覚えとけと、手元にあった昭和ガールズのおしゃま雑誌「オリーブ」をこんなもんと叩きつけられ、完膚なきまでの罵倒と逆鱗の焼きを入れられたあの時から三十余年。「人間、初動」。それはわたしの座右の銘というか、忘れたらしばかれる恐怖のモットーとなっている。
街角インタビューでも芸能人のコメントでも、街を歩けば耳につく昭和には聞こえなかった平成の声と音。
「と、思ってぇ、で、そう思ってぇ」。
個々思うことの差違、多様な生き方、考え方のバリエーションを認め合おうという寛容な空気。そこは、どう考えても、平成時代の進歩である。けれど、そんな進歩の過程にあるわたしたちがもう一歩踏み込まなくてはならないのは、「それぞれの思いを思いやる」というやさしい言葉の裏側で、だから「わたしの思いも思いやってもらいたい」と思っている自分がいやしまいかというなかなか哲学的な思索の域である。
人の気持ちに立って考えるには、その前に、痛い、悲しい、苦しい、いややというわたしの気持ちを有り余るほど感じられる自分でなければならないのではないか。自分の熱さ、醜さ、弱さ、ずるさ、アホくささを出さないまま、以心伝心思いやれるほど、わたしたちの相互理解力は明治大正昭和の昔より高次元に発達したのだろうか。
なんというか、やっぱり自分は、「誰も傷つけない、だから、誰にも傷つけられたくない」思いやり契約より、おれもおまえを傷つける、おまえもおれを傷つける、だから、お互い「悪く思うな」という生身の証文を叩きつけ合うほうが、好きなのだ。わたしもそこは触れないから、あなたもそこは触れないで。そんな遠慮も時には大事だが、ここぞとなれば「わたしも踏む、あんたも踏む」そこに炸裂する目くそ鼻くその小競り合いに命を懸ける、懸けられる人間でありたい。濃厚な昭和のエキスを吸いながら育てられ大人になった昭和の子として。
寅さんの昭和になみなみとこぼれ滴る人情。それは、たまらなくあったかいものではある反面、いつ何時、その者が持つ醜い感情むき出しに襲いかかられる危険、面倒も熱々にある。
自分にとっての昭和は、そんな厄介で面倒な人間の記憶でしかなく、それはおそらく、いよいよ遠くなってこそ心に浮かぶ故郷、離れて見れば懐かしい、が、いざ戻って2、3日もすれば「やっぱり、ないわ」のズレが甚だしい実家とか両親とか、そのような幻想なのかもしれないが。それでも、今となっては、それがたとえ幻想であっても、戻れるものなら戻りたいと思える昔、時代、記憶というのは、それを持ってどこに行こうか、次の時代に向かう力をくれる。寅さんにとっての「とらや」とさくら、のように。
これも、あるとき、明治生まれのカネばあちゃんに、何気なく訊いたことがある。
「カネばあちゃんなぁ、もし、好きな時代に戻れるとしたらいつの時代に戻りたい?」
「そいだなぁ」と、心の過去帳をめくるように思案して、出てきた時代は、「大正だ」。
その理由は、明治にも昭和にもあった戦争が、唯一なかった時代だから。それを出されたらぐうの音も出ない戦争。そうか、大正かと、なんとなくわかった素振りで、おばあちゃんの大正話に、それでそれで? と聞き入るわたし。
大正ー それは、モボ・モガに代表されるように西洋のモダンな文化ロマンがわんさか日本に押し寄せてきた時代。そんな見るもの聞くものすべてが見たことも聞いたことも未知の仰天と驚きに満ちていた時代を得として語るカネばあちゃんが、最もたまげたベスト・オブ・西洋。
それは、ジャムパン。
それがカネばあちゃんの口から発せられた瞬間、わたしが味わった「ジャムパ ん?」
けれど、そんなカネばあちゃんのジャムパンと同じように、人には人の時代があり、わたしにはわたしの昭和があるということを、今回は、ちょっとどっさり語ってみたかった。
ちなみに、今現在、こんなわたしの昭和の与太噺を夜な夜な聞かされる役のアメリカンなフランス人。
わかっているのかわからんのか、yeah, I know, I see わかった風に「それは世界中誰もが感じる、過ぎ去った時代というやつさ」と、「for example」と出してきた例に、いつになく同感できた、国境なき世代感。
「僕らが子どもの頃の80年代、マクドナルドには、ドナルドがいただろ? けれど、どうだ、恐がる子どもがいる、よく見ると不気味だ、LOHAS 的なおしゃれなイメージにそぐわない時代遅れだと、いつしかドナルドは消え去った。いや、消し去られた。いまや、初めからそんなものは「なかったもの」になっている。しかし、ドナルドは確かにいた。そこを、僕たちは忘れてはいけないんだ。マクドナルドは、マックだけじゃない、ドナルドがいたからこそ、マクドナルドだったというあの時代を…」
「それや、あんた! わたしが言いたい昭和の人間、寅さんがいた時代のなんたるかを英語で言うたら、ドナルドや!」
言葉と文化の壁を越え、分かち合うグローバルな昭和感。
「寅さん」なき平成、それは、ドナルドなきマック。
次に来る時代の名はわからないが、それでもわたしは、死ぬまで大好物とむしゃぶりついて、かぶりつくだろう。
寅さんとドナルドがいたあの頃の味に。

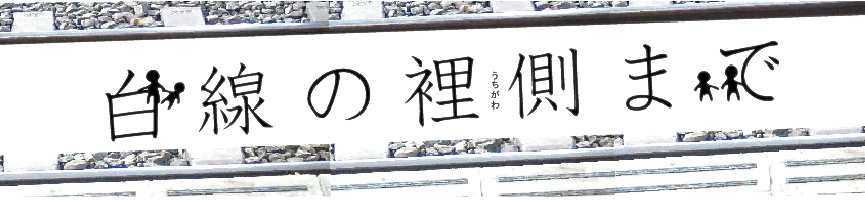

コメントはまだありません
まだコメントはありません。よろしければひとことどうぞ!
コメントする ※すべて必須項目です。投稿されたコメントは運営者の承認後に公開されます。