2011-10-2
日本昔話とイタリアに見る
ささやかな幸運
孫のいる方ならわかるのかもしれないが、どうも世の親というのはわが子以上に孫というものに格別の愛情と感慨を抱くものらしい。
「 なんでこんなに可愛いのかよ〜孫と言う名の宝もの〜」と、今から14年ほど前、大泉逸郎の「孫」という演歌が流行ったこともあったっけ。
ちょうどその頃、仕事も私生活も何もかも上手く行かず、下手にやさぐれていた27歳のわたしは「こんな爺バカの骨頂みたいな歌が流行るなんて、世も末やわ」と、えらそうに世紀末の世を儚んだものである。
しかし、親子では見られない爺婆特有の熱狂的な「可愛がり」というのはいったい何なのだろう。と、よくよく考えてみると、西洋の昔話にはあまり見受けられない傾向として、日本の昔話は爺婆に孫のような子ができるという設定に集約されている。「あるところにおじいさんとおばあさんが〜」と、物語の大役を果たすのは決まって爺婆である。しかも、そのおじいさんとおばあさんがひょんなことで子を授かり、その子が立派に成長し、鬼退治や化け物退治などの世直し事業で大成し、故郷に錦を飾るというのが大筋のパターンである。ということは、孫可愛がりというのは日本人の抜きがたい性質なのか。ただ童話や寓話には、その国、その土地の人生観が凝縮されている。おそらく日本の昔話に貫かれた人生観、幸福観というのは、それはやはり「子は宝」に尽きるのではなかろうか。「子は宝」という言葉には、自分の息子、娘、血肉を分けたわが子に対する愛情というものよりもっと広く、大らかで、はちきれんばかりに豊潤で、びっくりするほど奔放で無頓着な感性や感情がほとばしっているように感じる。なぜなら、昔話の爺婆が一貫して「かわいい、かわいい」と啼いてほたえて育てる子は、どこの誰が産んだのやら、そんなことはどうでもいいほど、ほんに可愛い「どこぞの子」である。得体の知れない桃の中や、よくもまあこんな竹の中からぽんと割って出てきたような子であっても、それがたとえ親指ほど小さな一寸足らずの子であっても、「子は宝」と大事に大事に育てることが、昔々の日本人が思う「幸せ」であり、子のいる空間、子のいる風景、野辺や田んぼのあぜ道を子が駆け回る一瞬の光景こそが、貧しくともささやかな希望や喜びだったのだろう。
自分の子どもには十分愛情をかけて可愛がってやらなかった、やれなかった人でも、おじいさん、おばあさんになった途端、子煩悩にめざめるというのは、ちょっとした先祖返りなのか。孫の誕生と同時に何かのスイッチが入ってそういう昔話の頃のDNAが蘇ってしまうからなのかもしれない。
そういえば日本の昔話はおじいさん&おばあさんの夫婦が主体なのに対して、「ピノキオ」しかり、「フランダースの犬」「アルプスの少女ハイジ」など、西洋の話にはやもめ暮らしのおじいさんがよく登場するが、あれは何か含みがあるのだろうか。しかも、そのおじいさんというのは、大抵無骨で無口で偏屈で気難しく扱いづらい職人タイプで、鬱蒼とたくわえた白髪まじりのヒゲに深く刻まれたシワ、森の奥の泉のような光と翳りを帯びたその貌には、十代の頃からずっと働いて働いて腕一本で生きてきたであろう汗と脂が染みついた威厳と悲哀が滲む。そう、見るからに「人間とは・・・」の重圧と圧迫にねじ伏せられる孤高の老人というやつだ。けれど、そんな巌窟じじいの長い苦節の歳月に錆び固まって開かなくなった心の扉を開くのは、ピノキオでありハイジでありネロという、やはり「子」なのである。それもまたわが子ではなく、降って湧いたように目の前に現れた孫なのだ。
ということは、この爺婆と孫という一世代またいだ「間」、そこにたゆたう「時」というのが人の心をときほぐす何かをもたらすのだろう。何というか、今まさに山頂へ登らんとする者と下りてくる者が笑顔で行き交う瞬間のような得も言えぬ安らぎ、あるいは「ゆく年・くる年」を送り迎える大晦日のような理屈抜きの楽しさをもたらす存在が孫という名の宝物なのかもしれない。
で、話は日本昔話から一気にイタリアへ。最近、毎週録画して観ている「イタリアの小さな村(BS日テレ)」。先週は、イタリア北部、3000m級の山々が連なる裾野の村・エトゥルーブルで、B&B(ベッド&ブレックファーストの略、宿泊ベッドと朝食を提供する宿泊施設)を経営するムッツィオさん(59歳)の生活を追っていた。
ムッツィオさんは40年間家具職人として働きづめに働き、退職を機に妻と2人、まだまだ働けると宿泊業を始めた。そんな今の楽しみは、4歳の孫娘と遊ぶこと。ムッツィオさんは決して裕福ではない。高度経済成長時代の父親たちと同じく家庭など顧みず働き通し、毎日遠く離れた町の工房から自宅に辿り着くのは深夜過ぎ。息子と遊んだことも、一緒にどこかに出かけたことも、話を聞いてやったことなど一度もない。「息子には父親らしいことを何一つしてやれなかった」。それがムッツィオさんのこれまでの人生である。その一人息子のミッシェルさんは隣町で消防局員として勤務している。余談だが、このミッシェルさんがこれまた驚くほど端正な美男子で、ほのかにウェーブがかったロンゲが素晴らしく絶品の伊達男なのだ。で、その妻は保育士で、若い夫婦共働きで2人の子を育てている。ミッシェルさんが夜勤の日、孫の世話をしに息子の家を訪れるムッツィオさん。出勤前の息子とふたりテーブルで向き合い、ただ静かにエスプレッソを飲むひととき。たまにムッツィオさんが口を開けば、やはりどうしても家具職人時代の話になる。
「こないだおれの作った家具がバージニアに行ったよ」
「おれの作った家具は世界中あちこちに飛んでいったのさ」
と、自分が手がけた仕事、自分の業界の置かれた状況や時代の変遷をぽつぽつと、だが機嫌よく語るムッツィオさん。仕事のこと以外、口火を切って話せる話題が見つからない親父と、「へえ、そうなんだ」と微笑む息子の間に流れるぎこちなくおぼつかない空気が何ともじれったくイライラするのだが、それがまたいいのである。腹立つけど。そう、働いて働いて女房子どもを養うだけで精いっぱいだった男の誠というのはこういうことだ。と、心では重々わかっているのだが、その要領を得ない不器用さにはギャッと噛みつきたくなってしまう。その辺の女の凶暴な気性は万国共通なのか、ムッツィオさんに対する女房の口ぶり・態度はかなり頭ごなしに偉そうなものだった。
番組の終盤、保育園に孫を迎えに行き、自宅の庭で遊ばせるムッツィオさん。満面の笑みで小さな孫娘を抱き抱え、じいちゃんの思いをこう語る。
「息子や孫たちが、ささやかな幸運に恵まれることを願います。普通のくらしができればと望みます。そんなに良くならなくても、それで十分です」
自分が歩いてきた人生を振り返り、これから息子や孫たちが歩いて行くであろう人生を遠く見つめるようなこのまなざしは、父、息子、孫、3代の時を経て初めてたどり着けるものなのかもしれない。
そう、だから大泉逸郎の歌みたいに「可愛い、可愛い」言うてるだけじゃあかんのよ! と、ことさらムッツィオさんの言葉が胸の奥にじんわりしみ渡る。「ささやかな幸運か・・・」と何度もその言葉を繰り返すうち、かの一休和尚が「この世で一番めでたいことを描け」と殿様に銘じられ描いたという屏風絵の文句が思い浮かんだ。
「じじ死ね、ばば死ね、子死ね、孫死ね」
殿様は「なんと不吉な、このクソ坊主!」という勢いで、烈火のごとくお怒りになったという。が、生きて死ぬ一生に、ささやかな幸運に恵まれるというのは、そういうことなのだ。きっと、たぶん(いっきゅう〜)。

「何もしてやれなかった」というムッツィオさん(言うまでもなく写真左)だが、息子のミッシェルさん宅の家具はすべてムッツィオさんが作ってやったという。

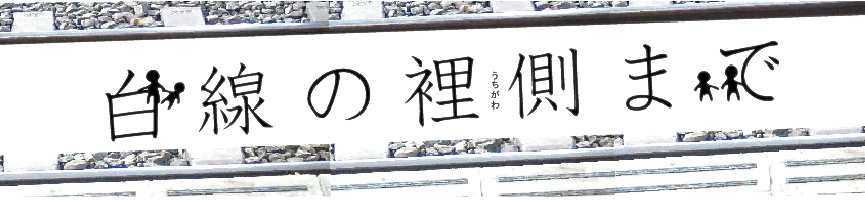

コメントはまだありません
まだコメントはありません。よろしければひとことどうぞ!
コメントする ※すべて必須項目です。投稿されたコメントは運営者の承認後に公開されます。