2010-11-30
知性とは?ルンペンおじさん考
スーパーのレジ前に並ぶ料理雑誌や女性誌の中に、気持ちはわかるが何となく気色悪いタイトルを発見した。「東大に行くこどもの作り方」。いったいどんな「やり方」かと興奮しながらページをめくると、何てことはない。東大生の親になるためのマニュアル本。いえば「自慢のわが子レシピ」か。
学歴がすべてではないが、確かに、それはあるに越したことはない。いくら頭が良くても、頭がいいだけの人はいっぱいいるし、大学など出ていなくても「学」を感じさせる人もいる。学者の知識と職人の知恵に優劣などつけようがない。むしろ、人間的魅力でいえば、職人に軍配を上げてしまう。およそ学歴というものは家柄みたいなもので、ないよりあった方が箔がつく。それだけのことだと思う。でも、それだけのことが大きいのが世の中の常でもある。
「東大出」とか「ハーバード卒」などと言われると、それだけで自分とは違うかしこい生き物に見えてしまうことも否めない。「高学歴」の響きには、一瞬にして人の心を轟かせる威力があり、目を眩ませるまばゆさがある。
でも、そのまばゆい光が、自分にとって本当にありがたく映るのは、「知識の量」や「専門性の高さ」などではなく、やはりその人が自ら蓄えた知性によって紡ぎ出した言葉、世界を見せられたときでしかない。
そんな見方があったのか、そんな考え方があったのか、そんな言い方もできるのかと、目の前のことしか見えないわたしに「見るべき」筋道を見せてくれるのが本当に知性のある人だと思う。
学歴の光と知性の光は照らすものが違う。学歴はその人の光だ。けれど本当に知性ある人は、その光でもって、人の人生を照らしてくれるのだ。
はっきり言って、およそ学問や教養というものは、学者や研究者やその道の専門家でない限り、一般の実生活にはほとんど役に立たない。けれど、実生活に役立つようなものではない、現実の人生に何の利益ももたらさない、なんら得することのないものに心血注いで打ち込めるのが知性の為せる技ではないか。現実のようにうろたえ、現実のようにしか考えられず、現実なるようにしかならない人生を生きている自分は、現実の中に自分の真実を見ることのできる「知性ある人」に、得も言われぬ羨望と尊敬を抱いてしまうのである。「学歴なんかなくても、勉強なんぞできなくても、生きるのには困らない」という庶民の決まり文句にも、「そんなもの」への永遠の憧れがあるような気がする。
映画「男はつらいよ」の中で、学のない者の心情をしみじみ語る寅さんのセリフがあるが、それが何とも味わい深く、ホロリとさせられる。
「人間長い間生きていりゃ、色々面倒な目にあうだろう。そんとき、俺みたいに勉強していない人間はいい加減にサイコロを振って気分で決めたりするしかないんだ。それが、勉強したヤツはな、自分の頭でキチンと筋道を立ててどうすればいいか、考えられるんだ。そのために大学に入るんじゃないか・・・」
なきゃないで困らないが、あるに越したことはない。うちの親もよくそんなことを言っていた。
「金のあるやつは金を使え、学のあるやつは頭を使え、金も学もないやつは体を使え」「頭を使える人間は偉い。でも、体を使って生きる人間は尊い」。それは、あるもんで何とか生きるしかない庶民の意地から出た言葉なのだろう。
そういえば、わたしが高一くらいの頃だったか、家の前の新幹線の高架下に3〜4人のホームレス(その頃はルンペンと呼んでいた)が住みついていたことがあった。そのルンペンたちの中に1人、まったくもって場違いな知性を漂わせた「おっさん」とは呼べないおじさんがいた。ワンカップの酒を手に将棋や談笑に明け暮れるおっさんの中で、革表紙の分厚い本を読みふけるおじさんは、まさに何の役にも立たない「知性」の現れのようだった。身なりや風貌にそぐわぬ知的な匂いを醸すおじさんの存在は、近所でもちょっとした噂になり、実は京大出身の教授か何かだったが、事故か事件か不幸な事情で家族を失い、絶望の末に世捨て人になったみたいなうそくさい物語が口々に囁かれていた。
他のおっさんたちが空き缶拾いかダンボール集めで日銭を稼ぎに出ている間も、そのおじさんだけは高架下の柱にもたれて座り、じっと本を読んでいる。となると今度は「実は資産家らしい」みたいなことをおばちゃん同士がぺちゃくちゃしゃべって回る。下世話な庶民の町づくりのスローガンは、何につけても「ほっといたれよ」なのである。
昔からインテリに弱い母親のお節介で、何度かそのおじさんのところに麦茶とおにぎりを持って行ったりした。おじさんはいつも丁寧に頭を下げ、ありがたく受け取って、数日後にはちゃんと麦茶の容器が玄関前に置かれていた。けれど、そんな平和な日々もつかの間、ある日訪れた警察によって、ルンペンおじさんたちは強制退去させられてしまったのだ。が、そのルンペンたちを追い出すときの警察官の物言いが、他の「おっさん」とその「おじさん」に対するときでは明らかに違うのである。他のおっさんには、「おまえら〜」「〜あかんやろ」と小突くような口ぶりなのに、そのおじさんに対しては「お宅はいつからここに?」とか「〜してもうてええやろか?」と、ちょっとした敬語。その様子を間近に見守っていた母親とわたしは「えらい不公平やなぁ」と、笑ってはいけない可笑しさをかみ殺しつつ、笑ってしまった。
人生に学のあるなしは関係ないとはいえ、それがあるように見えるか見えないかで人の見る眼は変わる。憎たらしいがしょうがない世間というものを見た気がした、16歳の夏のこと。
わたしが今でも忘れられないのは、そのおじさんが立ち去るとき、わたしたちに向かって深々とお辞儀をした姿。思わずわたしたち母娘も頭を下げ、警察に連れられて行く後ろ姿をじっと見送った。
その後、家に戻った母親はお約束のように「ルンペンいうても、京大出てはる人は違う。引き際も立派や」と、やたらうるさかった。
それにしても、あのおじさんの「違い」は何だったのだろう。京大出身なんてただの作り話のウソだろうが、確かにあのおじさんには、他のルンペンたちにはない勉学の素地が感じられた。
「何も迷惑かけてへんやろ!」と警察に食ってかかって言い争う「おっさん」たちと平然と静かにそこに立っているおじさんは、置かれた立場やつきつけられた現実は同じであっても、どこか立っている場所が違うような隔たりが見えた。おっさんたちはいわば現実そのもので、そのおじさんはやけに現実から遠いところをさまよっている、現実との間の取り方の違いなのか。でも、差し迫った現実や追い詰められた状況でも、現実と自分の間に「間」を置けるというのは、それだけ自分を俯瞰し客観視できる知的な営みをそのおじさんは持っていたのかもしれない。
なぜ勉強しなければならないのか、「学」はないよりあった方がいいのかというと、現実を前にしたときに自分を失わないためではないか。
どんな立場や境遇に置かれても、その現実から離れて考えることのできる場所と時間と言葉を自らの中に持っていることが、よく出来た人、出来のいい人だと、わたしは思う。
人生の苦難や責苦の中で何を思えるか、何を見るか、何を発見できるか。
どれだけ現実に負けずに生きられるか、どうしようもない運命や人生の価値をどれだけ自分で転換できるか。人の知性の最大にして最強のひらめきは、学歴や偏差値などでは決してはかれない。
東大に行ったからといって、それが得られるとは限らない。
そこが世の中、上手くしたところである。

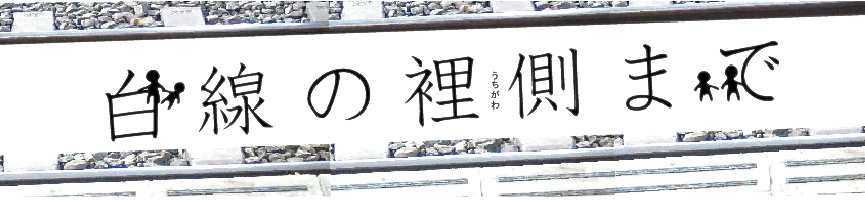

コメントはまだありません
まだコメントはありません。よろしければひとことどうぞ!
コメントする ※すべて必須項目です。投稿されたコメントは運営者の承認後に公開されます。