|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魚見幸代(以下、魚見) | 10年前に出版された『オニババ化する女たち~女性の身体性を取り戻す』は、出版当時、タイトルの過激さもあって、かなりセンセーショナルにメディアなどで取り上げられていました。アマゾンのレビューも賛否両論すごく多くて、10年経った今でも書き込みがあります。この本を出されたとき、これほどの激論が交わされると想定していましたか? |
|---|---|
| 三砂ちづるさん(以下、三砂) | 書く人間は、自分を守っていかないといけないところもあるので…、ネット批判は精神衛生上、良くないので見ないようにしています。 ただ、この本を出したときは、個人的にも、大きなところからも、小さなところからも、批判がいっぱい来ました。私としては、正直ビックリしたところがありました。 |
| 魚見 | ネットで書かれている声はかなり激しくて、どうしてそこまで…と、読んでいるこちらがドキドキしてしまうほどです。 |
| 三砂 | 私は80年代後半から2000年までのちょうどバブルの頃、ブラジルに10 年、イギリスに5年ほどいて、母子保健に関する研究をしていて日本にいませんでした。ブラジルでは妊娠中絶の大きな調査をしていて、いわゆるフェミニストと呼ばれる人たちとも仕事をしていましたし、自分がやっていることが「アンチフェミニズム」なことだとは全然思っていなくて。 特にラテン社会では多様なフェミニズムがありますし、子どもを産むとか、母親であるとか、そういうことは揺るぎのないことで疑問は呈されないで、そのうえで女性としてどういう風に生きて行くのか、そういう議論でした。 |
| 魚見 | 私は本を読んで、「アンチフェミニズム」とかそういうことよりも、こんな大切なこと、誰も教えてくれなかったな…ということでした。もっと早く読めばよかったと。 |
| 三砂 | そうでしたか…。 ただ一方で、1994年にカイロで開かれた国際人口開発会議で、「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」というのが提唱されました。それはひとりひとりの女性は、自分が産む、産まないを決めることができる権利があるということ。つまり、女性が妊娠中絶をする権利があるという言い方でもあります。 これが非常に政治的な問題だということはわかってはいるんです。妊娠出産が素晴らしいということだけでなく、中絶の苦しみを考えなければいけないという議論があることもわかっています。また、産めない人がいるのに、産むことを前に出すと問題があるということもわかっていました。 だからといって、出産が素晴らしい経験であることや女性が妊娠出産を大切にすべきであることが、リプロダクティブ・ヘルス/ライツで言われていること、その背後にあるフェミニズムに相反するものだとは、全く思っていなかった。 むしろ、日本のフェミニズムの幅をもっと広げていくものになればいいなと「女性の身体性を取り戻す」という本を書いたんです。 |
 |
|
| 魚見 | 副題がタイトルでしたか? |
| 三砂 | 最初はそうですね。でも光文社の編集の方がこれでは売れないんじゃないかと。 |
| 魚見 | そういう感じはしていました。 |
| 三砂 | 「ざらんざらん、べろんべろんと小憎さんの尻をなめた」…というオニババの昔話のことは元々原稿にあったので、編集の方が朝風呂で現タイトルを思いついたんです。私も最初はちょっと…と思いましたが、このタイトルで納得して、原稿も書き直したんですよ。 |
| 魚見 | 降りてきたんですね、オニババが(笑)。 |
| 三砂 | でも、いざ本を出そうとしたところで編集さんは出版社の上層の方に呼ばれたらしい。こんなタイトルの本を出したら、著者はすごいバッシングをうけるのに、それに耐えられるのかと。まあ大丈夫じゃないですかと言うことになったんですけど、豈(あに)図らんや。それがタイトルだけではなくて、内容を読んだらもっとフェミニストコードにひっかかることがあったということで、すごく批判されることになりました。 |
| 魚見 | 私は三砂さんが提唱されていることは、本来の女性のあり方を称えるもので、ある意味、本質的なフェミニズムの考えなのではないかとも思ったんですけど、正直、フェミニズムとはどういうものか、よくわかっていません。 |
| 三砂 | 世界にいろいろあるフェミニズムからみると、日本のフェミニズムはマルクス主義や社会学を中心とした、かなり特定の分野のフェミニズムだろうということもぼんやり分かっていたんですが、15年日本にいない間に変わっているんじゃないかと思って。 |
| 魚見 | 期待もあったんですね。 |
| 三砂 | でも、そんなに変わっていなくて。特定のフェミニズムコードに全部ひっかかったことを書いていて、批判されたんだと思います。読んでいないのに雰囲気で批判する人もいました。 これと同じ時期に酒井順子さんの『負け犬の遠吠え』が出たんですけど、そちらはフェミニズムの本で、私の本はアンチフェミニズムの本であると英語の論文まで書かれたことがあるくらい。 |
| 魚見 | すみません…。私はその、雰囲気で流されていたほうです。両方とも読んでもいないのに、自分のことを書かれていると思って。自分が選んで、自分がやりたいと思って生きてきた人生が、「オニババ」や「負け犬」といったカテゴリーの中に入れられてしまうのが嫌でした。「負け犬」のモデルはイケイケ女性で、まったく当てはまってなかったですが…。 だから、読んで批判する人は逆に勇気があるなとも思ったんです。自分の考えがあるんだろうと。私は自分の中に、考えがなかった。 |
| 三砂 | 読んで批判をしたかった人も読まないで批判をしたかった人も、ある意味、自分にあまり確信はなかったんだと思うんです。絶対、こういうことは批判しないといけないんだっていう、世の中の風潮になっているから批判しているだけ。私としては、自分がやっていることを正しいと思っていないからこそ、反応したんだろうなと思っているんですね。 |
| 魚見 | そうですね。そのときはよくわからかったけど、振り返ると自分に自信がなくなってしまうんじゃないかと不安だったんだと思います。 |
| 三砂 | 妊娠出産や母乳保育をして、自分の体で「これだ」という経験をつかんだ人たちは、そんなに人を批判しなきゃいけないとも思わないので、批判する必要もないところがあります。これを言われたら、ポリティカリー・コレクトではないから、反応しておかないといけない。そうしないと自分が信じていることが危うくなってしまう、不安だから反応しているんだろうなと理解してきました。 |
 |
|
| 魚見 | 風潮だけのフェミニズムは、私たちを幸せにしているんでしょうか? |
| 三砂 | もちろん、フェミニズムや女性解放運動がわたしたちにもたらしてくれたものはたくさんあります。でも、男性が手にしてきたものをもっと女性が手にしたい、という経済の「パイ」の問題ともいえる。 |
| 魚見 | セクハラ批判とかだけでなく、アベノミクスが女性の労働力に期待して、ウーマノミクス(ウーマンとエコノミクスを合わせた造語)だとかいって、企業も女性の管理職の登用を増やしていくとか、育休を3年にするとか、なんだか応援している風な感じですけど、それは応援ではなくて、そうしないとあなたの人生は充実しませんよと、という勝手な刷り込みのような気がして。それで、大事なものを失ってしまうのではないかと…。 |
| 三砂 | フェミニズムはひとつのイデオロギーですからね。政治とか経済とか、世の中の大きな構造はもちろん、時代によって変わるわけですけれども、人間が人間である限り、揺るがすことができない部分というのがあると思うんですよ。 |
| 魚見 | はい。 |
| 三砂 | 「生の原基」という言葉があります。聞き慣れない言葉だと思いますが、『逝きし世の面影』をお書きになった、渡辺京二さんの言葉です。私はずいぶん何度も引用させてもらっている。
「あらゆる文明は生の原基の上に、制度化し人工化した二次的構築物をたちあげる。しかし、二十世紀から二十一世紀にかけてほど、この二次的構築物が人工性・企画性・幻想性を強化して、生の原基に敵対するようになったことはない。一切の問題がそこから生じている」(『心に残る藤原書店の本』(藤原書店2010)より引用) つまり、人類がこれまでつくってきた全ての文明は、生の原基(生のもとの形)を強化するような二次的構築物をつくってきたけれど、20世紀後半からいまの文明はその二次的構築物が生の原基と敵対するようになった、という。 |
| 魚見 | ものすごい腑に落ちた感があります。 |
| 三砂 | 母性というのは「生の原基」に属するものだと思うので、世の中がいくら変わろうが、人間が生物としてある限り、揺るがすことができないもの、ということを私は興味の対象としています。次世代を残さないと人類は終わってしまうわけですから、実はそこに非常に大きな喜びがビルドインされているのではないか。「生の原基」をしっかりつかむような生活をしていると、生きていくということ自体が肯定できるようなものであろうと、私は思っているんです。 |
 |
|
| 018 疫学者・作家 三砂ちづるさん Interview | |
|---|---|
| 第1回 フェミニズムは女を幸せにしているか。 | 2014年8月25日更新 |
| 第2回 少子化対策に、なぜ保育所なのか。 | 2014年9月5日更新 |
| 第3回 出産は喜びに満ちた”セクシャル“な経験。 | 2014年9月25日更新 |
| 第4回 生の原基を伝承する「場」とは? | 2014年10月5日更新 |
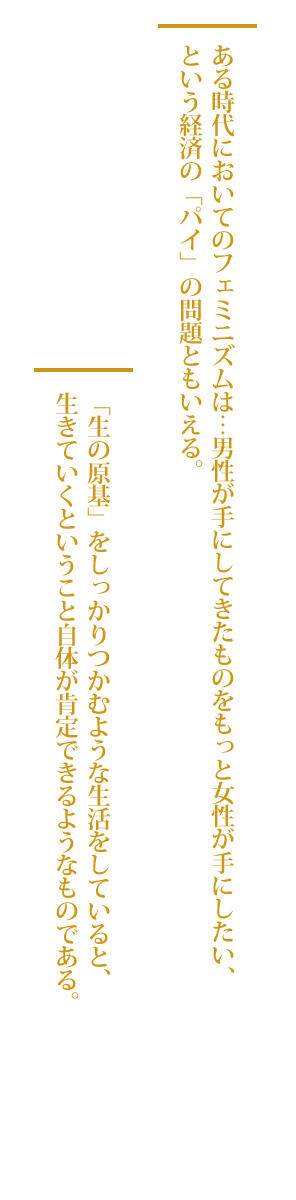
1958年山口県生まれ。兵庫県西宮市で育つ。京都薬科大学卒業。ロンドン大学PhD(疫学)。ロンドン大学衛生熱帯医学院(London School of Hygiene and Tropical Medicine) リサーチ・フェロー、JICA(国際協力事業団ー当時)の疫学専門家として約15年間、疫学研究を続けながら国際協力活動に携わる。2004年4月、津田塾大学国際関係学科に教授として就任。 「生の原基」としての女性のありよう、妊娠、出産、こども、について公衆衛生研究、国際保健協力、教育、小説、エッセイ、NGO活動などを通じて関わる。研究を通じて「変革の契機となる出産」、「月経血コントロール」、「おむつなし育児」などさまざまな体の知恵の復権も提唱する。
![]()

- 020
五味太郎さん×
イシコさん - 2016020

- 019
作家
平野啓一郎さん - 2015019

- 018
疫学者・作家
三砂ちづるさん - 2014018

- 017
写真家
鬼海弘雄さん - 2014017

- 016
劇作家
平田オリザさん - 2013016

- 015
フリーライター
井上理津子さん - 2013015

- 014
政治活動家
鈴木邦男さん - 2013014

- 013
歌手
八代亜紀さん - 2012013

- 012
社会学博士
大澤真幸さん - 2012012

- 011
カルーセル麻紀さん - 2012011

- 010
政治学者
原武史さん - 2011010

- 009
社会学者
宮台真司さん - 2011009

- 008
ノンフィクション作家
佐野眞一さん - 2011008

- 007
精神科医
春日武彦さん - 2011007

- 006
AV監督
村西とおるさん - 2011006

- 005
芸人/漫才協会名誉会長
内海桂子さん - 2011005

- 004
株式会社リナックスカフェ 代表取締役
平川克美さん - 2010004

- 003
映画監督
塩屋俊さん - 2010003

- 002
セラピューティック・トレーナー
白石宏さん - 2010002

- 001
生活哲学家
辰巳渚さん - 2010001
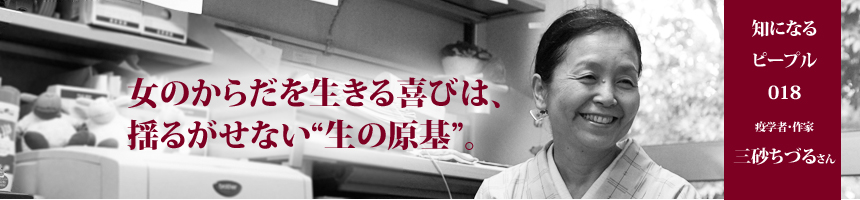
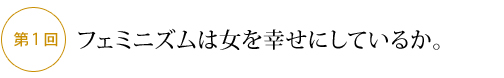
1件のコメント
「そうしないとあなたの人生は充実しませんよ、という勝手な刷り込み」という感覚、すごくよく分かります!
コメントする ※すべて必須項目です。投稿されたコメントは運営者の承認後に公開されます。