|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集部多川(以下・編た) |
小さい頃からずっとテレビで観ていたので、ほんとにお会いできて光栄です。 |
|---|---|
| 内海 |
内海桂子・好江の漫才をよく見てたっていうお客さまは60〜70歳ぐらいだから、あなたたちは知らないんじゃない? |
| 編た |
いえいえ、わたしは漫才番組に恵まれた大阪で育ったので、桂子・好江のお名前はよく存じ上げております。ずっとお二人は姉妹だと思っていました。海原お浜・小浜やかしまし娘など、当時、女性漫才というと姉妹が多かったので。 |
| 内海 |
そう、好江さんとはよく姉妹に間違われたけど、まったくの他人です。 |
| 編た |
内海師匠が芸事を習い始めたのは小学の頃ですか? |
| 内海 |
10歳のときに奉公に出されたの。おふくろが床屋の職人と一緒に暮らしたいからって、その家の保証金20円を借りるために「お前、奉公に行っとくれ」って頼まれたから「いいよ」ってね。20円といっても今じゃピンとこないだろうけど、お風呂が10銭、電車が7銭、家賃が8円。だから20円といえば、当時は大変な額よ。 |
| 編集部魚見(以下・編う) |
「銭」となると、ものすごく時代のギャップを感じます(苦笑)。その奉公先というのは、どういうところだったんですか? |
| 内海 |
日本中にその名が知られるほど有名なお蕎麦屋さんで、わたしの役目はそこの坊ちゃんの子守り。坊ちゃんが7歳でわたしが10歳だから、3歳しか変わらないんだけどね。坊ちゃんが学校へ行くときに草履袋を持って一緒に付いていって、勉強をしている間は、二宮金次郎の石像のところに腰掛けて、教室から聞こえる先生の教えを砂に書いて勉強してたわよ。 |
| 編た |
そういう自分の親に対して不満とかはなかったのですか? |
| 内海 |
それが当たり前だと思っていたからね。親に奉公に出されるのは自分だけじゃなく、丁稚に出される子も芸者に出される子もいました。たとえば芸者になろうと思えば、6つか7つから踊りや三味線の芸事を仕込まなきゃならないのよ。今は学校行ってからなる人もいるけど、とても12歳でお座敷に出て、13歳で半玉(芸者見習いのこと)に上がれないはずですよ。いえば、芸の世界は小さい時から習わないと一人前にはなれないわけ。 |
 |
|
| 編た |
親や家のために子どもが働くことが、それこそ人権問題でも何でもなく、社会全体の常識として当たり前だった時代なんですね。 |
| 内海 |
そうよ。だって私設だけど職業紹介所もあったくらいだから。桂庵(けいあん)っていう。親に手を引かれて出向いて行って、おふくろと帳場の人が何やら話し合って、そのまま連れて行かれたのがお蕎麦屋さんってわけよ。 |
| 編た |
自分の幸せとか、自分はどうなりたいとか、そういうことは考えなかったんですか? |
| 内海 |
自分の幸せなんか、考えたことなかったわね。今の人たちはまず自分でしょ。違うんですよ。まず国のために働くの。で、親のため。自分のことは最後。 |
| 成田(内海師匠のご亭主) |
でも、そんな中一度だけ自殺しようと思い詰めたことがあるんですよね。 |
| 内海 |
おふくろが父(桂子師匠の実父)と離婚したとき、わたしを連れて実家に戻ったのよ。その実家の祖父には後妻がいて、言えば母とわたしは赤の他人ね。で、そのおばあさんに辛く当たられて、ご飯のときも、うちのおふくろとわたしの分だけ、箱膳もお箸もないのよ。連れ子や店の人にはあるのにさ。とにかく一事が万事、扱いが酷くて、子ども心にものすごくさみしくなってとぼとぼ歩いて近くに流れる隅田川を眺めてたら、死んじゃおうかなと。でも飛び込んだらかあちゃんがかわいそうだと、それで死ななかった。 |
| 編た |
その思い詰め方って、人生を儚んで・・・みたいな寂しさと孤独ですよね。10歳で、そういう寂寞とした思いを噛みしめさせられるとは・・・。 |
| 内海 |
昔の10歳といえばね、親の事情も世間のこともちゃんとわかって自分で気持ちの片を付けられる、しっかりしたもんよ。しかも蕎麦屋で働いて毎日色んなお客さまの話を聞かせてもらってるから、いい社会勉強をしているわけ。その蕎麦屋にはお座敷があってね、お客さまが上がり込むとわたしはさっとゲタを揃えるの。すると「この子ずいぶん、気が利くね」っていって、ときには小遣いがもらえたんです。そういうことって、教えられたわけじゃなく、小さい頃から働いてると、誰に言われなくても勘が働く、気が利くようになるもんよ。自然とお客さまの大切さがわかる。お金の値打ち、ありがたみが身を持ってわかる、子どもでもね。 |
| 編た |
お金がもらえるからありがたい、というより、お客さまに喜んでもらうことで成り立っている商売、生活、自分というものを、子どもの頃に漠然と感じて育ったことがすごく大事なような気がします。 |
| 内海 |
お金がもらえるからというと、根性が汚いといえば汚いけど、なにも盗むわけじゃないからね(笑)。だってお客さまが喜んでくれて、わたしも嬉しいというのは、そこにあるのはお金ばかしじゃないってことですよ。とはいっても、基本的に自分の親が苦労してるのはお金のためなんですがね。 |
| 編た |
たとえば男の芸人さんは、遊びが芸みたいなところがあるけど、女の芸人さんはそんなことないんですか? |
| 成田 |
一流の芸人は自分でお金は使わない。ぜんぶまわりの人が賄ってくれるのが一流の証、といいますよね。 |
| 内海 |
昔、私を贔屓にしてくださった旦那衆はみんな鷹揚な遊び人で、芸のためにと歌舞伎に舞台にお座敷に、色んな所に連れていってくれました。芸者買いや女郎買いにも連れて行ってもらった。女が女のところにいっても、何も面白いことないけどね。でも、そうやって世間ってもんを知ることが芸の肥やしになったわけで、大枚切って勉強させてくださったわけね。たとえば、噺家さんをお座敷に連れて行っても、酒の席で落語なんか聞かないわよ。そこで即興で百面相をやったりして、隠し芸が生まれるの。 |
 |
|
| 編た |
芸人を育てるパトロンがいた時代なんですね。 |
| 内海 |
昔の芸人はほとんどが貧乏人だったから、そういう贔屓筋に可愛がってもらわなきゃ成り立たない世界だったわよ。 |
| 編た |
昔の漫才師の話とか、考えられないようなビンボー話がありますよね。 |
| 内海 |
そうよ。柴崎町や松葉町とか、芸人のたまり場だったのよ。たとえば大阪から東京に芸人が稼ぎに来るじゃない? そしたら同じ小屋に出てる東京の芸人が「うちにおいでよ」って、3畳1間しかなくても泊めてあげるの。そしてついつい、そこにいついちゃうのね(笑)。逆に東京の芸人が大阪に行くと、大阪の人が面倒見てくれる。だから芸人の家といえば、それこそ楽屋と同じで、芸人が何人もゴロゴロいるのが当たり前だったわね。 |
| 005 漫才協会名誉会長 内海桂子さん Interview | |
|---|---|
| 第1回 自分の幸せなんか考えたこともない。 | 2011年1月16日 更新 |
| 第2回 離れたら終わり、漫才コンビの絆。 | 2011年1月22日 更新 |
| 第3回 恋も仕事も人生も、女は甲斐性! | 2011年1月29日 更新 |
| 第4回 人の役に立ってこそ、生き甲斐がある。 | 2011年2月5日 更新 |
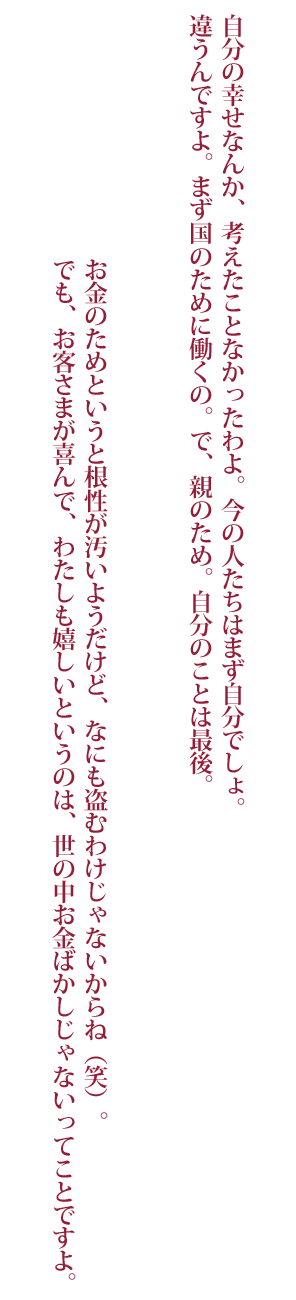
1922年生まれ。東京都出身。1938年高砂屋とし松とコンビで浅草橋館に漫才初出演。1950年内海好江とコンビ「内海桂子・好江」結成。58年「NHK漫才コンクール」優勝。その後、82年に漫才としては初の栄誉である「芸術選奨 文部大臣賞」を受賞するなど、数々の賞を受ける。1998年に漫才協団会長に就任。2005年社団法人漫才協会会長に就任、その後名誉会長に。漫才活動のほか、映画、ドラマ、バラエティ番組などに出演。また絵画個展等を開催するなど、幅広く第一線にて活躍中。
![]()

- 020
五味太郎さん×
イシコさん - 2016020

- 019
作家
平野啓一郎さん - 2015019

- 018
疫学者・作家
三砂ちづるさん - 2014018

- 017
写真家
鬼海弘雄さん - 2014017

- 016
劇作家
平田オリザさん - 2013016

- 015
フリーライター
井上理津子さん - 2013015

- 014
政治活動家
鈴木邦男さん - 2013014

- 013
歌手
八代亜紀さん - 2012013

- 012
社会学博士
大澤真幸さん - 2012012

- 011
カルーセル麻紀さん - 2012011

- 010
政治学者
原武史さん - 2011010

- 009
社会学者
宮台真司さん - 2011009

- 008
ノンフィクション作家
佐野眞一さん - 2011008

- 007
精神科医
春日武彦さん - 2011007

- 006
AV監督
村西とおるさん - 2011006

- 005
芸人/漫才協会名誉会長
内海桂子さん - 2011005

- 004
株式会社リナックスカフェ 代表取締役
平川克美さん - 2010004

- 003
映画監督
塩屋俊さん - 2010003

- 002
セラピューティック・トレーナー
白石宏さん - 2010002

- 001
生活哲学家
辰巳渚さん - 2010001

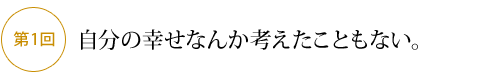
コメントはまだありません
まだコメントはありません。よろしければひとことどうぞ!
コメントする ※すべて必須項目です。投稿されたコメントは運営者の承認後に公開されます。