|
編集部
魚見
(以下 編う) |
家事というのは、各家庭で教わるという、私の中ではプライベートなイメージがあるんですけど、それを塾とかセミナーで習うというのに、少し違和感があるんです。それは時代の変化とか関係があるのですか?
|
|
| 辰巳 |
家事というと、炊事、洗濯、掃除と反射的にだれでも思い浮かべますね。それで間違ってはいないのですが、私はもう少し大きな意味を込めて、家事=家の事、暮らすこと、をもう1回考えようという意味で家事といっているんです。
炊事、洗濯、掃除は従来、家庭で親から教えてきたのではないの?というのは、ある意味、その通り。でも、もうちょっと広い意味でとらえれば、例えば家の手入れのことは親から子どもにだけ教えていたのかというとそうではなく、職人さんが来て、家をみてもらって、直してもらったり。
買い物ひとつでもそう。八百屋に行って、野菜を触っていたら、「売り物にさわるんじゃねえよ」って怒られたりして、買い物のマナーを身につけていた。
それはどんなことにも言えて、暮らしのルールやマナーというのは「親から子へ」を基本に隣近所、その土地、その地域、社会全体で共有してたもの。もうひとつ付け加えると、炊事・掃除・洗濯などの家事の仕方は、ずっと親から子に教えていたかというと、必ずしもそうではなかった。それは何かというと、行儀見習いです。女中奉公も本当にお金がなくて、下働きにでる家庭もあったけれども、仕込みの面で出される面もあった。落語家とか、丁稚奉公もそうですね。そこで最初になにをするかといったら、炊事、洗濯、掃除。
炊事、洗濯、掃除でさえも、社会全体で受け継いでいた。それを家庭に閉じ込めて、親だけの責任にしたのは戦後であろうと私は思います。
それが、戦後3世代目になって破綻し始めていて、生活能力のない子どもができたり、家庭をもっても家事の仕方がわからないとか、理想とする生活と自分の生活とがうまくつなげられない不安を抱える人がとても増えている。だから、そういう「暮らしを共有する機会や場」を家庭の中だけに押しこめるのではなく、もう一度社会の中へ引き出そうとしているのが、私の仕事です。
|
|
編集部
多川
(編た) |
辰巳さんの塾に来られる方は、ほとんど主婦の方ですか?
|
|
| 辰巳 |
家事という言葉で反応するのは、主婦と母親ですね。
|
|
| 編た |
そういう方達は、自分の家事のやり方を改めて学びたいという気持ちがあるのですか。
|
|
| 辰巳 |
そうですね。
苦手だとか、自信がないとか、子どもにも、自分がやっていることが正しいかわからないから、「お手伝いさせましょう」といっても何を伝えればいいかわからないと…。
でもみんな、意識があって来る方だから、実際には人並み以上にやっているのね。
|
|
| 編う |
人並み以上にやってるからこそ、「このままでいいいのか」「このままじゃいけない」みたいな問題意識が生まれてくるということですか?
|
|
|
|
|
| 辰巳 |
そうですね。
私はフリーで働き始めたバブルの頃からずっと「幸せってなんだろう」って思い続けてきたんですね。これだけ豊かな生活をつくりあげながらも、みんな幸せだと思えない、なにかが欠けていると思い続けている。
そしてようやく、自分たちに欠けているものが何なのかということに、頭だけではなく、もっとカラダの感覚で気がつく人が出てきた。
頭のいい人たちは、それこそ心の豊かさであるとか、日々の生活であるとかは言うんですよ。昭和の初期から、賢い人たちは、労働者運動と合わさって、「生活こそが文化である」とかね。でも今は、とくにそういう立派な思想からではなく、もっと具体的な生活を営んでいる、単純に自分の幸せを考えている人たちが「おうちごはんよね」とか、言っているわけですよね。
でも、そういうこと(家事)をやろうとすると、実際にはうまくいかない。おしゃれなものはいっぱいあるけど、それは自分の手でやったら、何か違うとようやくみなさん思いはじめた。
|
|
| 編た |
私の中では、暮らしの基本や原理原則みたいなものは生まれ育った家庭にあって、それを時代や自分の価値観に合わせアレンジしながら作っていくのが「その人なりの暮らし方」だと思うんです。ただ、その原理原則をまったく持っていないと、アレンジしようがなく。世間一般に「イケてる」とされる主流のスタイルでないと安心できない!みたいな…。
たとえば子育てひとつでも、自分はこれでいいという「ベース」がないと、男の子ママ・女の子ママとか、わけのわからない架空の価値観に振り回されたりして。
|
|
| 辰巳 |
おっしゃるとおり。
ベースがないというのは、正しい言い方で、私はよく、「私たちにはなにもないよね」と言うんです。中が空っぽな感じ。よって立つべきものが何もない感じ。
私は個人的には、自分の世代(40前半)からだと思っていて。それは親が、焼け跡世代なんですよね。少なくとも、確固としたものを受け継いだ親であれば、子どもに何かしらは伝えられる。意識的でなくても、社会のしくみとしても。
母から娘へ、親から子へ、大人が子どもへ伝えるべきことを伝える。そういうあたりまえの「受け渡し」作業が、戦後育ちの母親世代でぱたっと止まってしまったと思うんです。母たちは、自分が受け継いだベースがあるから、まだかろうじてやっていけた。社会もまだ、前の余力も持っている。でも、肝心の「受け渡し」が成されなかった私たち世代には、もう何もないっていう感じですかね。私より後に続く世代が、どれだけ…。
|
|
| 編た |
私もそう思います。
|
|
| 辰巳 |
いま、おいくつ?
|
|
| 編た |
40歳です。
サザエさんとか、寺内貫太郎一家とか、向田邦子さん、その辺の世界観を肌で知っているのが、私たち40歳ぐらいまで。もう30歳ぐらいだと、イメージはわかるけど…という感じだと思います。
別に親が子どもを育てるとかではなくて、近所の年長の子に遊んでもらったり、夕暮れ時にどこからともなくごはんの匂いがしてきて、おばちゃんが「もう帰りなさいよ」と声をかけてくれたり。かつてあったはずの「人と人との関わり方」を伝えていく役割がある年代なんだと、日々、感じさせられます。
|
|
| 辰巳 |
ね、役割でしょ。だから、家庭でやってればいいじゃない?っていうのではなくて、そういう意味での家事塾なんです。
それが将来、社会のしくみになるのが、たぶん一番いいことだと思うんですけどね。少なくとも私自身もそれで(きちんと家事を教えられることがなく)、すごく苦しい思いをしてきたし、世の中を見ていても、恐らくそこに、いまの苦しさってあるなあと。
私が私であることの実感が持てないとか、自分はこれでいいと思えないとか。たぶん、ベースにあるものの脆弱さにあるなあと思うと、世代の使命感みたいなのものを感じますね。
|
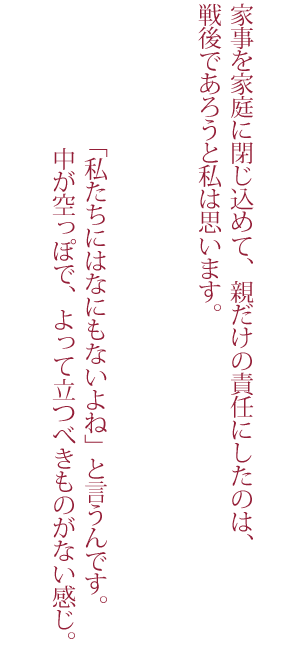

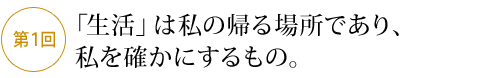





















コメントはまだありません
まだコメントはありません。よろしければひとことどうぞ!
現在、コメントフォームは閉鎖中です。