|
編集部
魚見
(以下、編う) |
いつぐらいから問題意識が出てきたんですか?
|
|
| 辰巳 |
そもそもでいうと、大学を卒業して、マーケティング雑誌に配属されたのが大きなきっかけ。マーケティングというのは、商品によって、人はどんな幸せが叶えられるのかというのを模索するような仕事で、いまが消費社会である以上、生活の中のあらゆるものが「買うこと」で手に入るんですね。
出産や子育てでさえも必ず買い物がついてくる。常に幸せって何だろうというのを、仕事として考えながら、私自身のこととして問い続けました。
マーケティングをしていた頃の一番の実感は、「私たちには暮らしはないのだ」ということだったんです。そのときには、そういう感想で終わっていたんですけど、じゃ、どうしたらいいんだろう、何が欠けているんだろうって見えてきたのは、わりに最近になってからです。
|
|
編集部
多川
(以下、編た) |
さっき、母親の世代の話がありましたが…。
私は母子家庭だったんですけど、母親はずっと「結婚なんかしなくてもいい」、「子どもなんか生まなくていい」と言っていたのに、死ぬ間際になってから「結婚してくれんと死んでも死にきれん」とか、「こんな孤独な思いはおかあちゃんだけで十分や」と、誰でもいいから結婚だけはしてくれと懇願してくるわけです。私からすれば、「なぜ今ごろ?」と。「女たるもの結婚すべき」とか、たとえそこに反発を覚えたとしても、何かこう親が頑として子に植え付けるものってあっていいと思うんですよ。
|
|
| 辰巳 |
なければ、それに反発する事さえできないからね。
団塊世代は幸せですよね。
|
|
| 編た |
私の母親は女手ひとつで私たち2人の子どもを育ててくれたんですけど、そのがむしゃらな苦労を見て、絶対に一生続けられる仕事を持とうと思ったんです。何があっても食べていける職業に就こうと。
|
|
| 辰巳 |
いまは編集?
|
|
| 編た |
コピーライターです。
|
|
| 辰巳 |
看護士とかじゃないのね(笑)。
|
|
| 編た |
そこは、詰めが甘いんですけど(苦笑)。
辰巳さんは、母親の世代から学んだことと、こうはならないぞと思ったことはありますか?
|
|
| 辰巳 |
母子の問題は,うちは葛藤が激しい家なので、個人的な領域と、世代とか客観的な分析の領域とありますね。
母は焼け跡世代で、高度成長期に子ども2人を産み、夫はサラリーマンで、専業主婦で、子どものために命を捧げて、今もですけど、それがどれだけ私には重荷だったか。
母が苦労をしていない、というわけではないんですけど、母の関心がすべて自分に向いていることがどれほど息苦しかったか…。言ってしまうと「真綿で首を絞められているような日々」。今でも真綿が首にまとわりついているんですけどね。
たとえば、今のお受験ブームなどにしても「親の作品化」してるとか、「親の自己実現のための手段にしている」など問題視されますが、それがどれだけ子どもにとって少しずつ少しずつ息をとめていくようなことかと。私もこれまでの人生、母から逃れるために格闘してきたような気がしますね。
|
|
|
|
|
| 編た |
早い時期から独立されたんですか。
|
|
| 辰巳 |
27歳。私は小学のときに父が亡くなったので、姉と私と母の女3人暮らしで、なかなか飛び出したりしにくい環境だったんです。母はお嬢様なので、娘が反抗するとパニックになって、なにを起こすかわからないので、家を出るまで27年かかった。
でも今、私、離婚してひとりなんですね。子どもも2人いる。働いていると、女ひとりでは全然手が足りなくて。母が近所に住んでいるので、結局、母の手を借りるんですよ。その葛藤たるや…。
|
|
| 編た |
そうですよね。
私も母親は、自分にとっての不治の病みたいなもんですから。
だけど、それなしには、自分は形成されてないんですよね。
母が亡くなったときは、死んでしまいたいくらいの、罪悪感がありました。
|
|
| 辰巳 |
今のこの葛藤状態で母に死なれたら、後生が悪いわ。
離れてない限り、仲良くはなれないのよ。口をきかなければ仲良くいられる(笑)。
|
|
| 編た |
亡くなって初めて、母を客観的に見られたかな。ひとりの女性の一生として。
|
|
| 辰巳 |
そうかあ。私はなんともいえないなあ。子どもがいるから、離れられないというこのつらさ。
|
|
| 編た |
私一度、母親に聞いたことがあるんですよ。「なんで一生続けられる仕事を持とうと思わへんかったん?」って。
そしたら「そんなもん、おかあちゃんのときは結婚するのが当たり前と思っててん。それしか生きようがなかった」と。
何というか、「人並みの幸せ」というのが母親の目標だったように思います。
|
|
| 辰巳 |
そういう世代ですよね。
人並みってね、人並みであることが大変だった時代も確実にあって、そういう「人並みの幸せ」を追い求めるようになったのは、明治時代からじゃないかと思うんです。
幕府時代、あれだけ階級制で押さえつけてきたのに、明治政府になり「四民平等」と形だけはみな平等ということになった。でも表向きは「平等」といいながら、家制度の規範は武家ですから、みんな武家のように立派で恥ずかしくない暮らしをなさいと。
それまでの徳川時代は、百姓なら百姓、商人なら商人、
自分たちなりの暮らし方があったはずで、
貧富の差はひどくあったとしても
「そういうもんだ」「仕方がない」と
あるがままに開き直れた。
でも明治の封建制度によって、「武家の規範」が基準になり、武家らしく、日本の臣民らしく、今ある自分より高い規範で生きなくてはならなくなった。当時の、今以上に真面目で従順な日本人はそれはもう必死に背伸びして頑張ったんじゃないかしら。
|
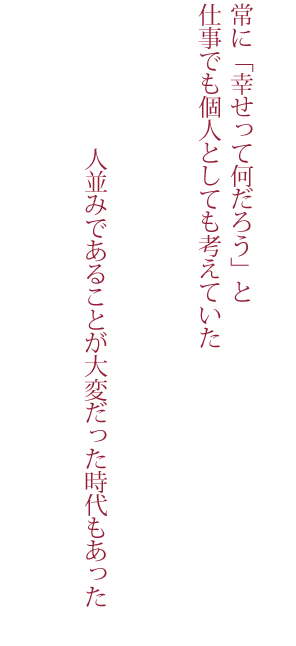

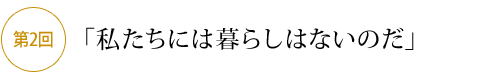





















コメントはまだありません
まだコメントはありません。よろしければひとことどうぞ!
現在、コメントフォームは閉鎖中です。