|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集部多川(以下・編た) |
『移行期的混乱』の中で、平川さんは、経済成長しなくてもやっていける戦略がないことが問題だと論じられています。その視点はどういうところから? |
|---|---|
| 平川 |
「人口減少」について色んなデータを調べていくと、それは日本という国がかつて一度も経験したことがない、有史以来の「転換期」にあることに気づかされる。だけど考えてみたら、鎌倉時代とかの人口は700万とか800万人ぐらいしかいなかった。それからどんどん増えて、人口爆発のような様相を呈して飽和状態になって、2006年をピークにして減り始めている。減り方は大幅で、かつ長期的。そのときに、経済成長3%をめざすとか、子どもを増やさないといけないとか政府は言うわけだ。でも、それは客観情勢を考えたら、単なる願望以上のものではないといわざるを得ない。ぼくは、人口グラフをじっと見て、今自分たちはどういう状態になっているのか、どこにいるんだって考え続けた。それがこの『移行期的混乱』という本になった。たぶん、今まで誰も言わなかった、書かなかったことだと思う。考えなかったのかもしれないけど。 |
| 編た |
自分がこれまで読んだ経済ビジネス書の多くは、今までのような成長は見込めないまでも、だからこそ戦略やビジョンが必要だと、その方向性は違っても何らかの変革や改革を唱えるものでしたし、自分もそれがないと成長はないと思っていた方です。変わらなければ変わらない、みたいな。 |
| 平川 |
僕は経済成長しないだけで、もう終わりだとも、先がないとも言っていない(笑)。経済成長というのは、消費・投資・貿易収支の総数を足したものだから、それらのメインファクターである人口が減れば、成長は難しいですよと、当然だということを言っているだけ。 |
| 編集部魚見(以下編う) |
たぶん世の中の多くの人の心配は「景気」で、それが良くなれば安心できるんじゃないかと。 |
| 平川 |
景気は、景気循環といって10年ごとに変動するような需給のアンバランスがもたらすものでしょ。でも、そんなことは本質的には、どうでもいい。どうでもいいってのは、いくらでも対処の仕方がある。。だけど景気循環とは別に、もっと大きな波があって、こっちは原因も対処も見つけ出すのが容易じゃない。そこをちゃんとつかまえていないと、今やっていることがまったくトンチンカンになってしまうという話をしたいわけです。 |
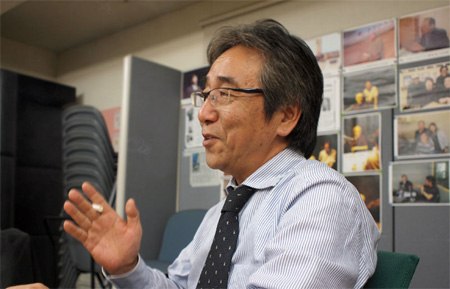 |
|
| 編う |
大きな転換期をどう生き延びるかが、個人的には大問題です。 |
| 平川 |
生活もさ、たとえば20万円ないと暮らせませんとか、30万円ないと暮らせませんとかいう話は、みんなそれはアパートの家賃がいくらで、食費がいくらで、と考えているからそうなるわけでしょ。僕は現在、父親の介護に入ったんだけど、介護をしていると、介護保険というのが出る。で、男二人食べていこうと思ったら、それで十分まかなえる。服買ったり靴買ったり、化粧品買ったりしなければ、全然金って使わないんだよね。お金って、使わないと思うと驚くほど使わなくてもやっていける。 |
| 編た |
でも国内市場で消費が拡大しないとなると、大企業はどんどん海外に出て行ってしまうのでは・・・。 |
| 平川 |
個人の生活にとって、私欲で動いている企業なんかどうでもいいんだよ(笑)。コントロールのしようがないしね。グローバル化してる大企業は、日本なんて関係ないからさ。安い労働力、人件費で物をつくって利益を最大化できればそれでいいわけよ。大企業に勤めている人間は、それでやっていけるからまあいいでしょうと。 |
| 編う |
はい、それはそれで(苦笑)。 |
| 平川 |
問題は、そういう大企業から仕事を受注している一次産業や中小企業だよね。そういう人たちは、生きながらえる策を考えないといけない。さっき話した消費の縮小と同じで、会社もダウンサイジングしたらラクになるんだよ。 |
| 編た |
消費が減るということは、受注生産の請負産業や会社自体、今までと同じ数は必要ないってことですよね。すると、その産業そのものもある程度淘汰されていくのは必然ってことですよね。 |
| 平川 |
それはもう仕様がないよね。そのなかで、中小零細の経営者たちはどこまでダウンサイジングしていけるか。そこが大きな課題なんだよね。課題だけど、やったことがないから、やり方がわからない。とても難しいと思う。だから、できる人からやっていくしかない。僕も一時は大きな会社をやっていたりしたけど、今は全然そういう会社に興味がないんだよ。つまんねえなあと思って。会社をやってて楽しいのは、10人まで。とりあえず屋根のある家に住んで、飯が食えれば、それでいいだろう。それ以上は望むなと、メンバーのそれぞれが覚悟して思いながら気脈を通じ合えるのが10人まで(笑)。 |
| 編う |
わたしも去年まで小さいながらも会社を経営して人を雇っていましたが、今は完全にフリー。まさにダウンサイジングの途中です。 |
| 編た |
人口減少による転換期を迎えている国は、日本だけなんですか? |
| 平川 |
超高齢化も、このような長期的かつ大幅な人口減少も日本が一番最初のモデルだと思う。急激に人口が増えて高度成長したから、その反動も大きいわけだね。そして日本がまさに、長期的人口減少のモデル国になろうとしている。そういう意味では面白い。アメリカは移民をどんどん受け入れたから、そういう風にはならなかった。日本もこれから移民を受け入れるかどうかは大問題なんだけどさ。 |
 |
|
| 編た |
それはどうなんでしょう? |
| 平川 |
僕は、受け入れる・受け入れないに関わらず、移民は入ってくると思う。これはコントロールしようがないんだよね。ただ、入ってはくるけど、移民を受け入れるのがまた一番苦手な人々だからね、日本人は。だから、それも移行期的混乱に拍車をかけることになるだろうと思う。 |
| 編う |
そうかもしれません。 |
| 平川 |
つまり国内分業が起きる。これは日本人のやる仕事。これは移民の仕事というように。アメリカなんかははっきりしてるけど、飲食店の中で、カウンターの内側で働いている中に白人はほとんど見かけない。スパニッシュと黒人です。使う人と使われる人が別なんだよ。おそらく日本もそういう風になっていくだろうと思う。いや、すでに、そのようなことがすすんでいる。 |
# 平川克美さんインタビュー第4回は2010年12月31日更新予定です。
| 004 株式会社リナックスカフェ 代表取締役 平川克美さん Interview | |
|---|---|
| 第1回 あると思っている「自分」なんて、ない。 | 2010年12月12日 更新 |
| 第2回 「自分で考える」とは、自分を壊すこと | 2010年12月17日 更新 |
| 第3回 移行期的混乱を生き抜くために。 | 2010年12月24日 更新 |
| 第4回 人間のつながりは、贈与なくして生まれない。 | 2010年12月31日 更新 |
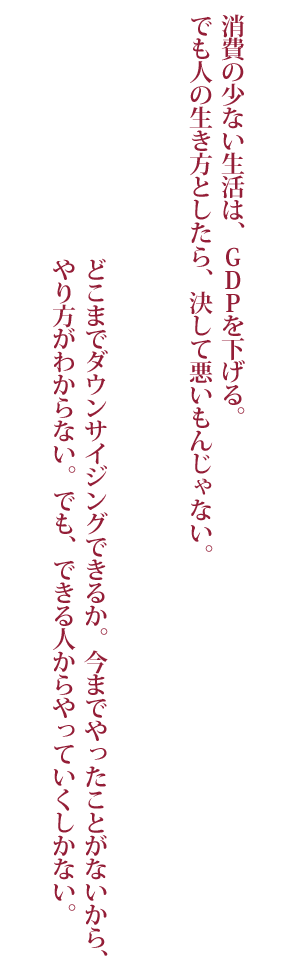
1950年東京生まれ。1975年早稲田大学理工学部機械工学科卒業。渋谷道玄坂に翻訳を主業務とする株式会社アーバン・トランスレーションを設立、代表取締役となる。1999年シリコンバレーのインキュベーションカンパニーであるBusiness Cafe, Inc. 設立に参加。現在、株式会社リナックスカフェ代表取締役。著書に『反戦略的ビジネスのすすめ』(洋泉社)、『株式会社という病』(NTT出版)、『移行期的混乱』(筑摩書房)、『経済成長という病』(講談社現代新書)、『会社は株主のものではない』共著(洋泉社)、『九条どうでしょう』共著(毎日新聞社)、『東京ファイティングキッズ』共著(柏書房)、『東京ファイティングキッズ・リターン』共著(バジリコ出版)などがある。
![]()

- 020
五味太郎さん×
イシコさん - 2016020

- 019
作家
平野啓一郎さん - 2015019

- 018
疫学者・作家
三砂ちづるさん - 2014018

- 017
写真家
鬼海弘雄さん - 2014017

- 016
劇作家
平田オリザさん - 2013016

- 015
フリーライター
井上理津子さん - 2013015

- 014
政治活動家
鈴木邦男さん - 2013014

- 013
歌手
八代亜紀さん - 2012013

- 012
社会学博士
大澤真幸さん - 2012012

- 011
カルーセル麻紀さん - 2012011

- 010
政治学者
原武史さん - 2011010

- 009
社会学者
宮台真司さん - 2011009

- 008
ノンフィクション作家
佐野眞一さん - 2011008

- 007
精神科医
春日武彦さん - 2011007

- 006
AV監督
村西とおるさん - 2011006

- 005
芸人/漫才協会名誉会長
内海桂子さん - 2011005

- 004
株式会社リナックスカフェ 代表取締役
平川克美さん - 2010004

- 003
映画監督
塩屋俊さん - 2010003

- 002
セラピューティック・トレーナー
白石宏さん - 2010002

- 001
生活哲学家
辰巳渚さん - 2010001
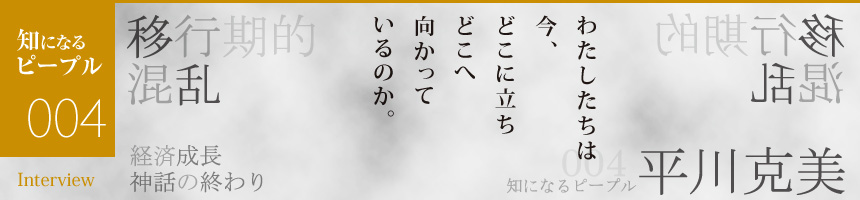
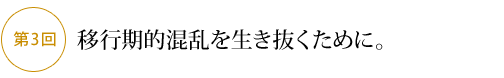
コメントはまだありません
まだコメントはありません。よろしければひとことどうぞ!
コメントする ※すべて必須項目です。投稿されたコメントは運営者の承認後に公開されます。