|
| 魚見幸代(以下魚見)
|
先ほどお話しいただいた毎日新聞の連載中の『マチネの終わりに』では、40代の苦悩についてもテーマにされています。そこで、「ヴェニスに死す症候群」という言葉が出てきて、とても興味をひかれました。
|
|
| 平野啓一郎さん(以下、平野)
|
映画『ヴェニスに死す』の原作で、主人公は自分の中に美に対して傾斜していくような危うい部分があるのですが、日々自分を抑制し、なんとか日常のバランスをとってきた作家なんです。自分の作品が教科書に載って社会的には立派な作家になっていくんだけど、一方で順調であることに、倦んでいる。年齢を重ねていく中でつらい状況にあるというつらさもあるけど、一見順調そうにいっても、このままでいいのかな?という思いもある。
|
|
| 魚見
|
作品では、“中年になって、突然現実社会への対応に嫌気がさして、本来の自分へと立ち返るべく、破滅的な行動に出ること”を指しています。
私はこの「salitote」を始めたのがちょうど40歳のときで、それまでは「こういうふうに生きたい」という目標みたいなのがあって頑張れたけど、その頃は漠然と不安があって、内側に向かっていった感があります。それは今も続いていて…。
|
|
| 平野
|
自分自身の歩みの中でも、20代30代は自分も未熟でやりたいことややらないといけないことが湧いてきて、それに向かってやっていくことが人生の前進になると見えていました。それが40歳にさしかかって、やりたかったことも結構やって、自分の技術を上げるためにやらないといけないこともやって、この先さらに一歩前進するためには、なにかしないといけないことはわかっているんだけど、ちょっと漠然としてしまうんですよね。
|
|
| 魚見
|
平野さんでも…。
|
|
| 平野
|
日本の近代文学の歴史をみても、20年以上創作活動をした人が、最近までほとんどいなかったんです。夏目漱石、森鴎外、芥川龍之介は死んでしまっているし、谷崎潤一郎は例外的に長く活動をしましたけど、、三島由紀夫、中上健次…みんな20年間ぐらいなんです。事情は色々だし、カウントの仕方も幅がありますが、要するに長く続けるための手本を誰に求めるかということですね。
|
|
|
|
|
| 魚見
|
平野さんは23歳でデビューされているので、もうすぐ20年を迎えるのですね。
|
|
| 平野
|
複合的な要因だとは思うんです。今の20代との感覚がズレてきているという世代のギャップもありますし、肉体的な変化も感じます。例えば、会社を辞めるとか、ポジティブな意味でドラスティックな方向の行動はいいと思いますが、それを破壊的な方法で乗り越えようとすると、危ないんじゃないかなという気がしているんです。つい大胆なことをしがちですけど、結局はコツコツやっていくしかないような。これからの時代は昔よりも、40歳以降の先が長いと思うんですよね。それをこの小説で考えたいと思いまして。
|
|
| 魚見
|
女性に限ることだと思いますが…40代の不妊治療は、かなり個人的な感想ですが、ポジティブでありながらもある意味破壊的な部分があるように思います。
|
|
| 平野
|
『決壊』でも、幸福と健康という観念が人を苦しめていると書いたのですが、子どもを産むことは、それが幸せでそうしないといけないとなってくると、それ自体がプレッシャーになりますね。そうしたいけど、できないこともある。
僕は森鴎外が好きなんですけど、鴎外の小説はだいたい、運命やその時代の封建社会のしくみ、無意識、義理など…不可能なことに巻き込まれて、しょうがないなって感じの主人公なんです。ヒロイックにそれらに打ち勝っていく主人公はいないんじゃないか。それがいわゆるエンターテインメントの小説とは真逆だから、人気がない理由のひとつなんでしょうけど(苦笑)。僕はそこに慰めを感じます。
|
|
|
|
|
| 魚見
|
私自身はヒロイックなものに憧れることが多かったですが、しょうがないっていうの、いいですね。
|
|
| 平野
|
女性の場合は子どもを産むかどうかはものすごく大きなことですけど、それに限らず、人間っていろんなことのなかで、あれができなかった、これができなかったってある。社会は努力して頑張れば、なんでも達成できるみたいなストーリーにしていますけどね。
|
|
| 魚見
|
成功する秘訣はあきらめないこと、みたいな。
|
|
| 平野
|
それは嫌だなと思いますね。できたらラッキーだけど、できない人生もあるというか。だから自分が書いている小説でも、そういうことを大事にしています。もちろん、どこかの段階で努力することは尊いことですけど、そのうえで最終的には、なにかが上手くいき、なにかがうまくいかないっていうのが、人生かなと思います。
|
|
| 魚見
|
平野さんが小説家を自分の道として選んだきっかけはあるのですか?
|
|
| 平野
|
最初は小説を読むのが好きで、一読者でしたけど、だんだん自分の言いたいことがたまってきて、書くことも好きでした。あとは向いていたんだと思います。僕は音楽もやっていたんですが、それは挫折しました。
|
|
| 魚見
|
そうだったんですか。パートは?
|
|
| 平野
|
ギターです。育ったところが田舎でしたからギターの練習ばかりしていて、近所ではかかり上手かったんですよ(笑)。それで中学生の頃は、やっぱりプロになろうとか思ったりして。今になって思うと、ミュージシャンはミュージシャンになるべくして生まれたような種族なんですよね。楽器が上手いとか下手というのはその先の話で、独特のノリがある。僕はどれだけ楽器が上手くなっても永遠にミュージシャンにはなれなかったと思います。たとえミュージシャンになっていたとしても売れなくて、でも作家になったおかげで、一生会うことができなかったような世界的なミュージシャンと会えたりすることがあるんです。そういう面白さがありますよね、人生は。
|
|
|
|
|
| 魚見
|
ところで平野さんは積極的にツイッターやフェイスブックを利用されています。ネットのスピード感や効率のよさなど、便利で欠かせないものだと思いますが、一方で、小説が読まれる機会が少なくなっていることについては、どう思われますか?
|
|
| 平野
|
ネットの世界はものすごい勢いで情報が渦巻いているので、それを右から左へ受け渡していっても、「リツイート」するだけの存在になってしまうと思うんですね。情報についていくことは不可避ですけど、一方で、自分なりにゆっくり考えて本当にそうかな?と疑うことも大事だと思います。
|
|
| 魚見
|
私はネットのスピード感に触れていると、ゆっくり考えることがなかなかできないです。小説を読むと、自分の中にたまっていた違和感と共感できることがあったりして、気づきになったりします。
|
|
| 平野
|
小説は情報として処理していくというよりも、身体感覚とか自分の過去の記憶とかを混ぜながら情報を整理していくんです。だから自分の血肉になっていく。
もうひとつは、社会学や哲学は人間一般の話から始まるんですね。「人間とは…」「現代人は…」とか。
|
|
| 魚見
|
そうしてグルーピング化されるのは、すごく反発してしまいます。
|
|
| 平野
|
僕もへそ曲がりで、「みんなはそうかもしれないけど、僕は違う」って思うんですよね。例えば調査では87%の人は当てはまるとか書かれてあっても、僕はだいたい残りの13%のほうにいた人間だから。
小説はあるところに変な人がいて…というふうに、13%のほうから話を始められるんです。ただその変な人の人生をみていくと、単に変な人で終わるのではなくて、今の社会の大きな問題が現れてきて共感できたり、一般性も開かれていくのが小説だと思うんです。僕にとっては、例外のこういう人間がいるんだっていうところから始められるっていうのが、文学の良さだと思いますね。
|
|
|
|
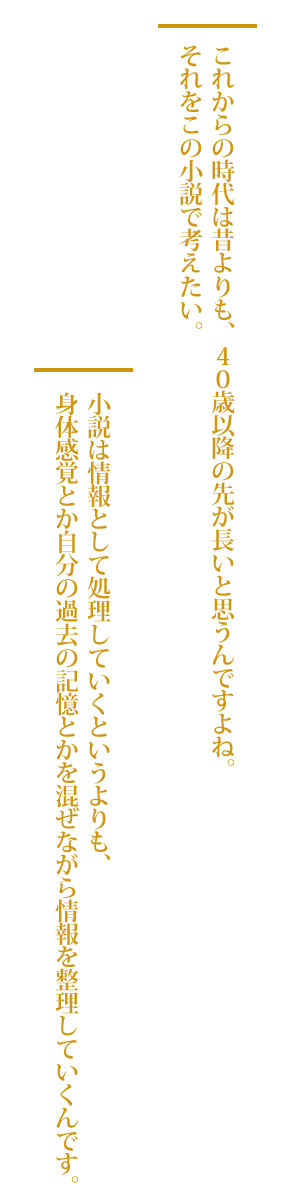
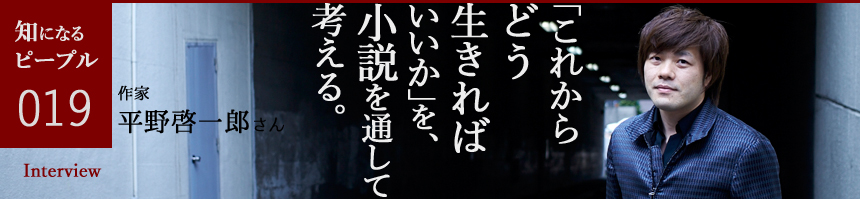
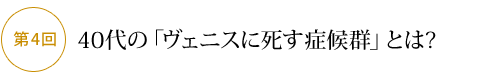



























コメントはまだありません
まだコメントはありません。よろしければひとことどうぞ!
コメントする ※すべて必須項目です。投稿されたコメントは運営者の承認後に公開されます。