|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集部魚見(以下魚見) | 実際に演劇ワークショップに参加していく中で、コミュニケーション能力がついてくるんでしょうか? |
|---|---|
| 平田オリザさん(以下平田) |
効果は、はっきり証明はできないんです。でも、モチベーションについては、比較的早くに効果が出ます。アンケート調査をすると、もちろん直後だったら楽しかったとか書くだろうけど、それだけだったら説得力がないから、最近は、家に帰ってから、お父さんお母さんに、今日の内容を子どもたちは話しましたか?という調査をしています。すると、演劇に授業は明らかに普通の教科学習に比べて楽しいから、親に話すんですね。 あと、どのくらい長くそのことについて話していたか、という調査もしています。アンケートのような社会学的な調査と、認知心理のような科学的な調査と両面からみています。すると、実際に体を使う学習のほうが、長期的記憶に結びつくということが証明されつつある。そういうことが証明されていくと、もう少し説得力が増すかなということはありますね。 |
| 魚見 | 証明するのは難しそうですが、やはり教育に取り入れていくには必要なことなんでしょうね。 |
| 平田 |
たとえば、去年の3月にベトナムで演劇を使った日本語教育の仕事をして、僕の作品をハノイ大学日本語学科の30人ぐらいが、リーディング上演をしたんですね。その上演も素晴らしかったんですけど、先々週またベトナムに行ったとき、この1年半でその学年だけが、突出して日本への留学率が高いということを聞きました。それは成績が優秀というよりも、積極性が出て、日本への関心がものすごく高まったと。1ヶ月弱のプロジェクトでしたが、演劇をつくるという授業を体験したために、非常に日本への実質的な関心が高まって、多くの人が日本留学を希望し、実際に実現するところまで至ったということですね。こういうことは、目に見えやすい成果もあるんですが、そうはいっても、本当の成果はわからないです。 成果はわからないのになぜ演劇教育が広がってきたかというと、現場にいるのはみんな教育者だから、なにが子どもの将来のために役に立つかは見ればわかるんです。 |
| 魚見 | それらは中高生や大学生といった学生の話ですが、大人にとっても演劇ワークショップでコミュニケーション能力をつけることはできるんでしょうか? |
| 平田 | 会社とかは上の人が変わらないと、こういうものは変わって行かないですね。各地で社会人向けのワークショップもやっていますけど、香川県の瀬戸内海放送の社長さんが以前、丸の内でやっていたワークショップを毎週末飛行機に乗って受けにきていて、これはいいと思ったらしく、今全社員に演劇のワークショップを導入しています。その社長さんは明らかに社員の能力が変わったと話していますね。ほんとにそんなにうまくいくかな?とも思うんですけど(笑)。 |
 |
|
| 魚見 | ワークショップに参加する以外に、個人的に試せることはありますか? |
| 平田 | 社会人の方からは、「上司がまったく理解がないので、どうすればいいですか?」といった会社内のコミュニケーションのことはよく質問に受けます。その場合には、例えばプロジェクトチームとか、新しい部署が立ち上がったときに、その企画とは全く別のものを最初にちょっとやってみたらどうですか?という話をします。アメリカだと一番一般的なのは、バーベキューパーティー。バーベキューパーティーだと、それまでのキャリアは全く関係なく、買い物の上手い奴とか、切るのが上手い奴、焼くのが上手い奴とか、やたら食う奴、皿洗いはちゃんとやる奴とか、いろんな役割分担ができて、仕事の上だけでは見えてこないものが見えてくるわけですよね。一旦フラットな関係にしてみることが大事で、たとえ、どんなに威張っている中高年の男性でも、バーベキューになったらまったく使えなかったりするわけじゃないですか。そういう状態をつくる。できれば、そういう状態を、いま権力を握っている中高年の男性が自分からそっちに身を置くというのが、ほんとは理想型なんですけどね。 |
| 魚見 | そういうのも、以前は会社でもあったのではないですか? クラブ活動や運動会とか? |
| 平田 | そうですね。企業が余裕がなくなると、そういう時間は減りますよね。逆に余裕のある企業や先端的な企業ほど、そういうことは、今のやり方でやっているということですね。昔の社員運動会とかそういうのではなく、もうちょっと新しいやり方でやっているということですよね。 |
| 魚見 | では、例えば私は母親だから、先生だからとか、カメラマンだから、社長だからとその役割でふるまうことと本当の自分は、どう捉えればいいんでしょう? |
| 平田 |
僕は基本的に本当の自分はないと思っています。いろいろな社会的な役割、それをふるまいといってもいいと思うんですけど、その社会的な役割を演じ分けることが大事で、ひとつのことだけを演じようとすると、さっきいったように重くなってしまう。私たちは同時にいろんな役を演じ分けている。それをできれば楽しむぐらいの状態がほんとはいいんですよね。 でも日本では、それをなんか裏があるみたいに言われる。裏も表もないよって思うんですけど。 |
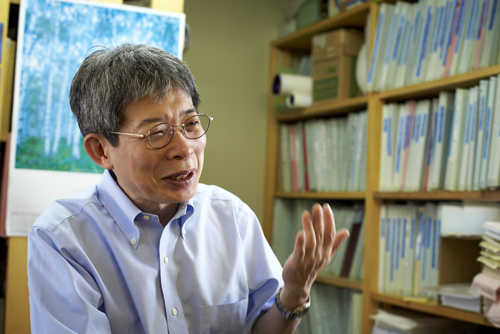 |
|
| 魚見 | 以前、平川克美さんに出ていただいたときも、本当の自分なんてないってお話があって、びっくりしたんです。では、例えばドラマの設定のようですが(笑)「○○ちゃんのママとだけいわれるのが嫌。ママ友たちの間では自分をわかってもらえない」というような状況の対処法は? |
| 平田 | 確かに○○ちゃんのママとしか言われない、それにしかアイデンティティがなくなってしまうと、それはつらいですよね。だからそうでない自分も必要です。だけど、○○ちゃんのママであることも事実ですよね。だからそういう仮面もかぶっておいたほうがいいんですよ。そうじゃないとお互いに困るし、それがなしになると、それは動物ですからね。 |
| 魚見 | うまく世の中を渡って行くためには演じることも大事なんだと思うのですが、それでも自分の意見や考えていることがあって、自分の考えていることと違う意見に遭遇したとき、ぐっと押し黙るだけで、うまく対応ができない気がします。 |
| 平田 | それは、いくつかの側面があるんです。今の子たちの話でいうと、今は少子化でみんな子どもの気持ちをわかってあげるし察してあげるので、ケーキといえばすぐケーキが出てくるし、優しいお母さんだとケーキという前にケーキが出てきたりもしますね。それは家庭だけの問題ではなくて、学校でも先生は優しいし、友だちも優しいんですね。いじめは嫌なので、できるだけ衝突を回避するように動きますから、これは自然のことなんですけど。昔だったら、子どもの数、兄弟の数が多くて、そうもいってられなかったのが、温室のようなコミュニケーションの中で育てられて、急に高校とか大学とか、僕が今いるような大学院とかでいきなりコミュニケーション能力とか言われるんです。このギャップが大きいわけです。 |
| 魚見 | つまり、私たちの世代よりももっと対応ができないということですか? |
| 平田 | 実際にこれは大学の教員間では笑い話で言われることなんですけど、学生がレポートを出して、それをちょっと厳しめに添削して返すと、「先生は僕のこと嫌いなんですか?」っていうんです。こっちは好きも嫌いもねえよ、仕事でやってるんだよって思うんですけど(笑)。要するに、その学生は、僕がわかってくれないのは、嫌いだからだと考えるんです。わかってくれない=嫌いなんです。関係ないでしょ。「いやいや、君のお母さんや友だちはこれでわかってくれたかもしれないけど、僕は君のお母さんじゃないので、これだとわからないから」と話をするんです。 |
| 魚見 | 今の若い人たちに限らず……、そう思いがちかもしれません。 |
| 平田 | 演劇の世界でもありますよ。よく若い劇作家や演出家に「君を好きな人はこの作品はいいというかもしれないけど、プロになりたいんだったら、君を好きじゃない人でもうならせないと。極端にいったら、この作品は嫌いだけど、この作家はすごいなと思わせるぐらいじゃないとダメなんだよ」という話をするんです。それがプロになるということですね。あるいは大人になるということです。それが好き嫌いだけの世界で生きてしまっているんですよね。それでもたいていの人はどっかでわかる。ただ、今はわかるチャンスが一度も得られなくても、社会人になれるので、そこが難しいところですね。 |
 |
|
撮影/岡崎健志
近頃の若者に「コミュニケーション能力がない」というのは、本当なのか。
演劇という切り口から、日本語コミュニケーションを考えた平田オリザ氏の考察書。
演劇という切り口から、日本語コミュニケーションを考えた平田オリザ氏の考察書。
青年団本公演として8年ぶりに上演。
202X年、架空の青年海外協力隊第四訓練所。この年、日本政府の財政は破綻寸前となり、全ての海外援助活動の停止が決定される。
202X年、架空の青年海外協力隊第四訓練所。この年、日本政府の財政は破綻寸前となり、全ての海外援助活動の停止が決定される。
最後の派遣隊員となる青年たちの訓練所生活の、その寂しく切ない悲喜劇を通して、人間が人間を助けることの可能性と本質を探る青春群像劇。
| 016 劇作家・演出家 平田オリザさん Interview | |
|---|---|
| 第1回 演劇とコミュニケーション教育。 | 2013年10月5日更新 |
| 第2回 演劇は漢方薬みたいなもの。 | 2013年10月25日更新 |
| 第3回 私たちはいろんな役を演じ分けている。 | 2013年11月5日更新 |
| 第4回 人生のさびしさに耐える力をつけるのが教育。 |
2013年11月25日更新 |
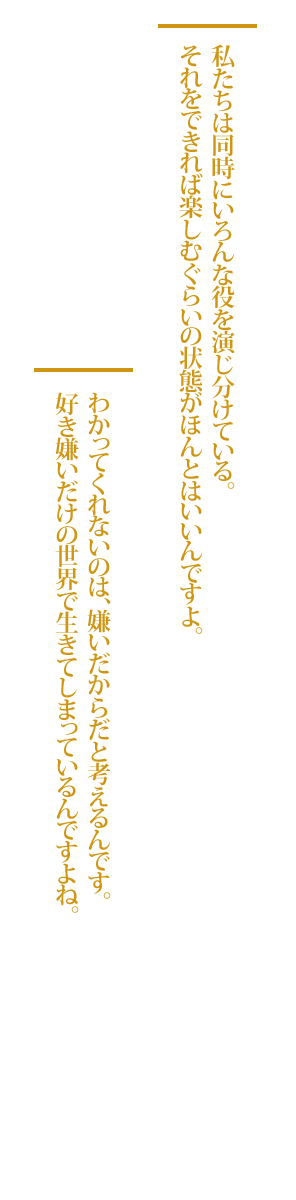
劇作家・演出家・青年団主宰。こまばアゴラ劇場支配人。 1962年東京生まれ。国際基督教大学在学中に劇団「青年団」結成。現在、大阪大学コミュニケーションデザイン・センター教授。2002年度から中学校の国語教科書に、2011年以降は小学校の国語教科書にも平田のワークショップの方法論が採用され、年間30万人以上の子どもたちが教室で演劇をつくるようになっている。その他自治体やNPOなどと連携した演劇教育プログラムの開発など、多角的な演劇教育活動を展開。戯曲の代表作に『東京ノート』(岸田國士戯曲賞受賞)、『その河をこえて、五月』(朝日舞台芸術賞グランプリ受賞)など多数。2008年から世界初の試みであるロボット演劇プロジェクトを始め、フランスなど世界各国にて上演。
![]()

- 020
五味太郎さん×
イシコさん - 2016020

- 019
作家
平野啓一郎さん - 2015019

- 018
疫学者・作家
三砂ちづるさん - 2014018

- 017
写真家
鬼海弘雄さん - 2014017

- 016
劇作家
平田オリザさん - 2013016

- 015
フリーライター
井上理津子さん - 2013015

- 014
政治活動家
鈴木邦男さん - 2013014

- 013
歌手
八代亜紀さん - 2012013

- 012
社会学博士
大澤真幸さん - 2012012

- 011
カルーセル麻紀さん - 2012011

- 010
政治学者
原武史さん - 2011010

- 009
社会学者
宮台真司さん - 2011009

- 008
ノンフィクション作家
佐野眞一さん - 2011008

- 007
精神科医
春日武彦さん - 2011007

- 006
AV監督
村西とおるさん - 2011006

- 005
芸人/漫才協会名誉会長
内海桂子さん - 2011005

- 004
株式会社リナックスカフェ 代表取締役
平川克美さん - 2010004

- 003
映画監督
塩屋俊さん - 2010003

- 002
セラピューティック・トレーナー
白石宏さん - 2010002

- 001
生活哲学家
辰巳渚さん - 2010001
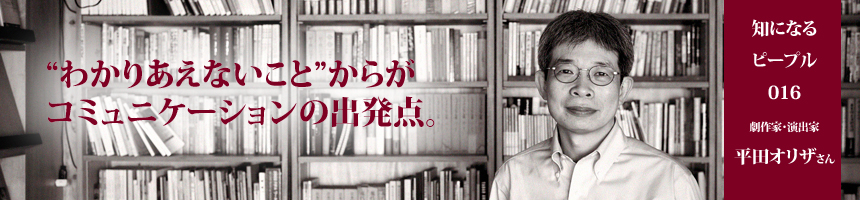
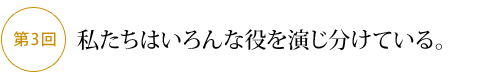
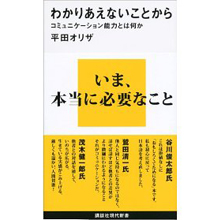
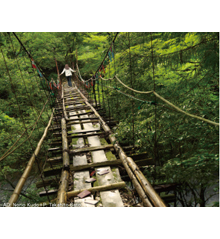

コメントはまだありません
まだコメントはありません。よろしければひとことどうぞ!
コメントする ※すべて必須項目です。投稿されたコメントは運営者の承認後に公開されます。