|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集部多川 | 先ほど、国や政府に依存しない共同体のあり方として、教会コミュニティのお話しがありました。今の日本でそういう共同体自治の回復は可能なのでしょうか? |
|---|---|
| 宮台 | 「自分の命、生活は自分で守るしかない」という自覚は、個人で持つしかない。自分が気づかないといけないので、気づいた人間たちが民主的な行動や新たな価値感や世論を生み出す活動を通じて、自分たちで政治を作り出すことが必要だと思います。 |
| 多川 | う〜ん、確かに、政府に求める国民の声の大半が「景気を良くしてくれ」というような現状では、そこまでの個人意識を持つのは難しいかも・・・。 |
| 宮台 | 日本は昔からそうだからね。幕藩体制の江戸時代には、地方自治があったように思われますが、実際に政治統治を行っていたのは武士で、農民は田畑を耕し米を作る労働集約的な共同作業に没頭するのみ。年貢が高くさえなければ、それでよかったわけでしょ。そういう意味では、およそ大半の日本人には「自治」の習慣がなかったといってもいいかもしれない。 今の日本もそうだよね。軍事と外交、国の根幹、舵取りは全部アメリカにおまかせで、自分たちでやっているのは利害配分の調整だけ。果たしてそれを政治と呼べるのかどうか。たとえばヨーロッパでは、民衆と呼ばれる中間集団というのは、統治権力、政府に対抗すべく、自分たちの手で自分たちの社会を作りあげようという考えがあるけど、日本の場合、地方自治体も、町内会も、学校もすべて統治権力のヒモ付き、下部組織なんだよね。 |
| 多川 | ということは、そういう自治のシステムを作るのは、政治や政府、お上の仕事ではないということですね。 |
| 宮台 | そう、政治が悪い、政府がお粗末というのは関係ない。自治というのは個人と個人のつながりの中で生まれるものだから。社会全体でどうにかできるものではない。だから気がついた人間たちがまさに知的なコミュニケーションを通じて、知的な厚みのあるネットワークをつくっていく。気づいたヤツから動いて、連携して、変えていくしかない。 |
 |
|
| 多川 | そういう個人の自覚・意識の持ち方を社会全体に浸透させようとすれば、やっぱり大事なのは教育だと思うのですが・・・。 |
| 宮台 | 教育を通じて全体を変えるのは一番いいんだけど。僕も以前はそういうビジョンを持っていたけど、やっぱり難しい。広範囲に社会を変えるのは教育だけど、教育をするのもまた人だから。 |
| 多川 | 今回の震災で、子どもたちの命を救ったのは世界最大級の防波堤システムでも何でもなく、常日頃からの教育でした。いわゆる防災マニュアルに従って全校生徒が一旦校庭に集まるのではなく、「津波が来たらてんでばらばらに逃げなさい」という先人の知恵を守った子どもたちは全員が助かりました。 |
| 宮台 | そう、あれは釜石市で8年間「津波てんでんこ」という先人の言い伝えを守る避難教育を続けてきた片田敏孝さん(群馬大学大学院教授、防災額の専門家として釜石市防災危機管理アドバイザー務める)というすごい人がいたから。彼がすごかったからです。事実、彼はひとりで、2つの小中学校の生徒578名の命を完璧に救いました。 |
| 多川 | ふつうは、「我先に逃げろ」ではなく「まわりのみんなを助け、協力して逃げろ」と教えますよね。 |
| 宮台 | まわりを見ながらでも「逃げる」のならまだいいけど、多くの人は警報サイレンが鳴ってもまず逃げない。なぜかというと、真っ先に逃げたヤツは臆病者の意気地なしだと、“へたれ”だと思われるのがイヤだから。 |
| 多川 | 非常時の危機感よりまず、まわりの空気をいの一番に察知してしまうんですね。 |
| 宮台 | そうです。率先して避難するというのは、「逃げるとかっこ悪いんじゃないか」というまわりの空気をぶち破ること。片田さんが小中学生に教えたのは、自分だけ助かれ、逃げろということではなく、「率先避難者たれ」ということ。自分の命を最優先に守りなさい。そうすることで、みんなも逃げる。自分が逃げることでみんなの命が助かるんだと、真っ先に逃げる理屈を子どもたちに与えた。 |
| 多川 | 真っ先に逃げたひとりの行動は「とにかく逃げろ!」というシグナルになってまわりの人間に伝わっていく。だから「とにかく逃げなきゃ!」と、全員が必死に逃げたから助かったんですね。 |
| 宮台 | 日本人が待ちわびているのは、「空気を破るヤツ」なんだよね。ほんとは逃げたいと思っていても逃げられない、ほんとは違うと思っていてもクチには出せないだけで、日本人っていうのは何も気づけないバカなんじゃない(苦笑)。ほんとのことは気づいて知ってるんですよ。いわば、原子力村の連中も原子力発電の不合理性には気がついている。でも、出世も家族も生活も棒に振ってまで真実のために闘うような大変なことはしたくないとか、色んなパラメータが働いちゃうわけ。いや、ほんとは覚悟も構えもあるのかもしれないけど、おそらくみんな、自分の意識をぶち破るきっかけがほしい。だから、そのきっかけを作るアイスブレーク(氷を溶かす)役の人間が必要で、それが津波てんでんこの場合は、率先避難者。価値を訴える人が必要なんですよ。 |
| 多川 | 日本人というのは、単に上に立つリーダーというだけでなく、自分が思っていてもできないことをさらっとやってのけてしまう人間にたとえようもなく惹かれる、付いていきたくなる性質なんですね(笑)。 |
| 宮台 | ある程度、普段からリスペクトされてるヤツの言動に共鳴して「やっぱり俺たちも本当はそう思ってた」みたいになりたいんだよね。みんなが知ってることをあらためてその通りだと、だからその通り振る舞う必要があるんだという気にさせる存在。日本においてはそういう役割がすごく大事なんですよ。 |
| 多川 | そのまどろっこしい繊細さが可愛いところでもあり、腹立つとこでもあり(笑)。 |
| 宮台 | 日本のリーダーというのは、年功序列だったり、派閥順送りだったり、既存のプラットフォームの上で能力を認められた人間が指導しているだけで、実のところ人間的な度量や器が優れているのかどうかはよくわからない。平時はそれでももいいんだけど、一番大事なのは大きな転換を迫られた時、既存の座席を争うだけではなく、座席の配置表全体を変える発想の転換を行えるのが、本当のリーダーシップなんですよ。そこが今の日本は致命的に欠けている。政治でいえば、政治主導どころか官僚支配そのものですから。 |
| 多川 | 以前、ラジオで「近代日本社会の最大の闘いは政治と官僚の構図にある」というお話しをされていましたが・・・。 |
| 宮台 | 政治家はつねにポピュリズムによって国民を陽動し、官僚は疑獄・汚職・政治スキャンダルによって政治家を失墜させる。で、日本の場合はいつも政治が負けるんですよ。なぜ負けるかというと、政治家がダメなこともあるけど、そういう闘いの本質を国民の多くが知らないからなんです。 |
| 多川 | 政治家がこれだけコロコロ変わっても国民の生活そのものは変わらない。それは、日本の官僚が優秀でしっかりしているからという見方もありますが、それは平時のプラットフォームが変わらないからなんですね。 |
| 宮台 | 90年代に入り、東西冷戦が終わり、グローバル化、資本貿易の自由化が進んだときに、日本は既存のプラットフォームを変えなくてはいけなかったのに変えなかった。先進国では日本だけが何も変えていないんですよね。変えなきゃいけないっていう意識が行政官僚にないのはどこの国も同じなんですけど、政治家にもなければ、国民にもないわけでしょ。官僚支配がいけないといっても、それの何がいけないのか、本質的な理由を理解していなければ、そりゃ勝てないですよ。 |
| 多川 | 自分も、そこまで理解してないです。 |
| 宮台 | 僕が知る限り、今の民主党の政治家でも、ちゃんと理解してないですよ。なぜ官僚支配がいけないのか完結に20秒以内に述べよと言って、明確に答えられる政治家がいったい何人いるのかと(苦笑)。 |
| 多川 | 自分が子どもの頃、昭和の政治家、田中角栄などの時代は政治主導に見えたんですけど。 |
| 宮台 | あの頃は政治主導でしたね、アメリカに潰されましたけど。小沢一郎は田中角栄の1/3ぐらいの力しかないと思うけれども、それでも検察に追われるわけだからね。ああいうのは必ず、アメリカのゴーサインがあるんですよ。検察って、アメリカ大使館とのコネクションが強くて、検察庁にはアメリカの特殊警察とパイプを持つ幹部がたくさんいたりするので。政治スキャンダルの影には官僚とアメリカのコネクションがあるというのは、前提条件ですから。 |
| 多川 | アメリカの国益を邪魔するような政治家は追い払われるということですか? |
| 宮台 | アメリカもどこの国も同じで、自分たちの国益増収をめざして外交を武器に闘うわけですよ。だから、こうなるすべての原因は日本にある。もちろんアメリカのコバンザメみたいな政治家や官僚もいるし、アメリカの狡猾な陰謀があるのも事実だとは思いますが、私たちは、普通の国だったらはねのけるようなアメリカの意向に応じて、自分の利益増大をはかるような人間がいるこの国のいびつな構造・システムに対して、本当の怒りを向けなければならないと思います。 |
撮影/編集部
| 009 社会学者 宮台真司さん Interview | |
|---|---|
| 第1回 なぜ日本は変われないのか | 2011年7月15日更新 |
| 第2回 日本人が待ちわびるリーダーとは? | 2011年7月29日更新 |
| 第3回 才能を育てられない、日本というシステム。 | 2011年8月12日更新 |
| 第4回 隙間に生きる人間力 | 2011年8月26日更新 |
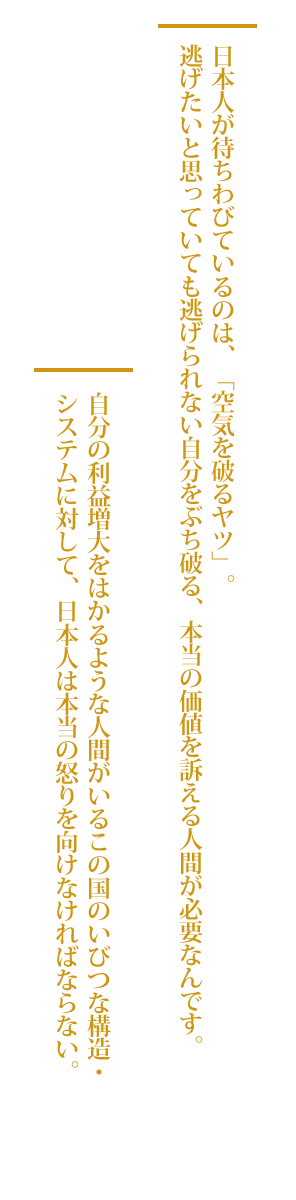
みやだい・しんじ
1959年、宮城県生まれ。社会学者、評論家。首都大学東京教授。公共政策プラットフォーム研究評議員。東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了(社会学博士)。権力論、国家論、宗教論、性愛論、犯罪論、教育論、外交論、文化論などの分野で単著20冊以上、共著を含めると100冊以上著書がある。
最近の著作には『14歳からの社会学』『日本の難点』『原発社会からの離脱——自然エネルギーと共同体自治にむけて』など。キーワードは、全体性、ソーシャルデザイン、アーキテクチャ、根源的未規定性、など。
![]()

- 020
五味太郎さん×
イシコさん - 2016020

- 019
作家
平野啓一郎さん - 2015019

- 018
疫学者・作家
三砂ちづるさん - 2014018

- 017
写真家
鬼海弘雄さん - 2014017

- 016
劇作家
平田オリザさん - 2013016

- 015
フリーライター
井上理津子さん - 2013015

- 014
政治活動家
鈴木邦男さん - 2013014

- 013
歌手
八代亜紀さん - 2012013

- 012
社会学博士
大澤真幸さん - 2012012

- 011
カルーセル麻紀さん - 2012011

- 010
政治学者
原武史さん - 2011010

- 009
社会学者
宮台真司さん - 2011009

- 008
ノンフィクション作家
佐野眞一さん - 2011008

- 007
精神科医
春日武彦さん - 2011007

- 006
AV監督
村西とおるさん - 2011006

- 005
芸人/漫才協会名誉会長
内海桂子さん - 2011005

- 004
株式会社リナックスカフェ 代表取締役
平川克美さん - 2010004

- 003
映画監督
塩屋俊さん - 2010003

- 002
セラピューティック・トレーナー
白石宏さん - 2010002

- 001
生活哲学家
辰巳渚さん - 2010001
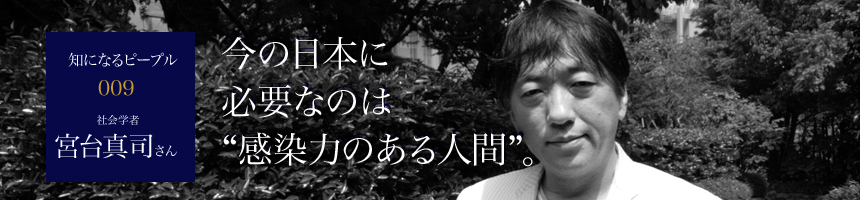
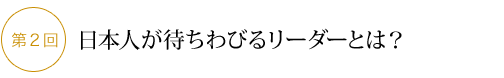
コメントはまだありません
まだコメントはありません。よろしければひとことどうぞ!
現在、コメントフォームは閉鎖中です。