デニスとは、今年3月に発売されたサンディーの最新アルバム『HULA DUB』のプロデューサー。UK初のレゲエ・バンド、マトゥンビのメンバーであり、パンクやニューウェイヴに大きな影響を与えた伝説の人物、デニス・ボヴェルのことだ。僕も大好きなアーティストなのだが、ここsalitoteは音楽専門サイトではないので、深入りはしない。

『HULA DUB』Live Tourの詳細はこちらから!
「よく誤解されるんだけど、私にはハワイの血は一滴も流れていないの(笑)。遠い親戚がハワイにいて、その方が私のことをとても可愛がってくれたので、10歳くらいのときからハワイで暮らすことになったわけ。でも、日本にも家族がいたから、さびしくなると帰ってきて、行ったり来たりという生活をしていました」
イメージというものはおそろしいもので、僕は勝手にサンディーのことをハワイ生まれの日系二世だと思い込んでいた。出身は僕と同じ東京の郊外の街だという。
幼少の頃、サンディーはどんな子供だったのだろう?
「私はとても気が小さい子で、怒鳴り声を聞くとジンマシンが出るほど繊細だったの。きっとバイオレンスに対して敏感だったんでしょうね。だから、両親がケンカを始めると、私は別の部屋に逃げこんで歌をうたっていた。するとね、不思議なことに、両親のケンカが終わるんです。そのとき、私は確信しました。私の歌にはまわりの空気をふわっとさせる力がある。歌をうたっていれば自分も平和になれるし、まわりの人もハッピーにできるんだって!」
■蝶々と遊ぶことは、みんながふつうにできることだって思っていた
サンディーの歌声に反応したのは人間だけじゃなかった。
「あれは8歳のときでした。テキトーな歌詞にテキトーなメロディをつけて歌っていたら、二匹の蝶々が飛んできたんです。私が高い声で歌ったら蝶々はひらひらと上昇し、低い音でため息をついてみたら下降。それが面白くって、私は毎日蝶々といっしょに遊んでいました。でもそのとき私は子供だったから、これが特別なことだとは思わなかった。蝶々と遊ぶことは、みんながふつうにできることだって思っていたんですよ(笑)」
子供のころは誰もが説明しがたい不思議な経験をするものだが、サンディーの場合は少し違っていた。大人になっても、魔法が解けなかったのである。
「インドネシアで録音しているとき、お腹を壊して、声に力がまったく入らなくなってしまったことがあったんです。でも、スタジオにわざわざヴォーカルの先生をお呼びしていたから、なんとか今日中に歌い終えなきゃならなかった。体調を回復させるためにしばらく休憩室で横になっていたら、子供の時に遊んでくれたあの二匹の蝶々が私の目の前に現れたんです。その瞬間、聞こえてきたのは、“声は力じゃないんだよ。おでこのあたりから声を出すような気持ちで歌ってごらん”という細野さんの声でした」
細野さんとは、はっぴいえんどやYMOのメンバーとして知られている細野晴臣のこと。日本とイギリスで発売されたサンディーの初ソロアルバム『イーティン・プレジャー』(1980年)のプロデュースとアレンジを手がけた人物である。
「そんな細野さんのアドバイスを守ってなんとか歌い終えたら、コントロールルームのスタッフが拍手してくれました。でも、ヴォーカルブースを出たら、みんな私の顔をじーっと見て、変な顔をしているんです。なんだろうと思って鏡を見たら、声を出すために意識していた、おでこのあたりがボコンって腫れあがっていた(笑)。蝶々は自然界のフェアリー(妖精)だというけれど、私のまわりにはこんな不思議な話がいっぱいあるんですよ」
このときに録音されたアルバム『アイルマタ』(1993年)は、マレーシアなど東南アジアの国々で大ヒットを記録。1995年には日本人アーティストでは初となる、マレーシアのグラミー賞といえるマレーシア音楽産業賞(AIM)特別賞(1995年)を獲得した。現地の民謡や歌謡曲をマレー語とインドネシア語で歌ったこの作品は、アジアンポップの傑作として今も高く評価されている。
ちなみに、“こぶし”を効かせたサンディー独特の歌唱も、プロデューサー細野晴臣のアドバイスによるものだとか。
「“英語がぺらぺらで民謡のこぶしが回る人が面白い。そうだ、きみはインド歌謡のこぶしを効かせて歌うといいよ”と、細野さんが言ってくれました。日本の“こぶし”はハッキリと回っているような感じだけど、インド歌謡やインドネシア民謡の“こぶし”は、角がとれて、ローラーコースターみたいに上下する感じ。そんな歌い方が面白くて、いろいろと試していたら、それがいつのまにか自分の歌い方になっていました」

■歌い終えたら、坂本九さんが私のところへやってきたんです
サンディーは日本でのデビューのきっかけについて、話し始める。
「ハワイで暮らしていた十代の頃、シンガーを募集していたあるバンドに、友達が私のデモテープを送ったんです。まさか受かるとは思わなかったんですけど、なぜかオーディションに合格。で、そのバンドが日本で演奏をするってことになったときに、私もいっしょに日本へ来ることになったんです。来日と言ってもたいしたステージじゃないんですよ。デパートの屋上とか、楽器屋とかで演奏しただけでしたから(笑)。でも、そのときにたまたま音楽関係者の目にとまり、日本に来て歌手をやらないかって誘われたんです」
偶然はもう一つ重なった。
「NHKの音楽番組にクックアイランドから来たポリネシアンダンサーが出演することになっていて、ポリネシア語がわかる人を探していたんです。それならちょうどハワイから来ている人がいるらしいよってことで、私に通訳の話がきたんですよ。当時の私はポリネシア語を今ほどは理解出来ていなかったんですけど、クックアイランドなら英語も通じるはずだし、まあなんとかなるかなって引き受けちゃったんです(笑)」
収録が無事に終わると、サンディーは誘われるがまま打ち上げに参加。坂本九、左とん平、三橋美智也など、そうそうたる顔ぶれの中で、歌声を披露することとなる。
「赤坂、銀座と飲み歩いて、三次会のピアノバーが“ミニ紅白歌合戦”みたいになったんです。みんなピアノの伴奏で歌っていたけど、私はお店にあったギターを手にとり、この曲を歌ったんです」
サンディーが僕の目の前で歌い始めたのは、ブレッドの「Make It With You」(1970年)。日本では「二人の架け橋」というタイトルで知られ、アレサ・フランクリンもカバーしている名曲だ。
「歌い終えたら、坂本九さんが私のところへやってきてこう言ったんです。“あなたは通訳じゃなかったの? ひょっとして歌い手になりたいの?”。私はただ“はい”とうなづくことしかできませんでしたが、翌日、私が滞在していたホテルに坂本九さんがリムジンで迎えに来たんです。行き先はNHK。昔は歌手としてNHKの番組に出演するには、オーディションに通過しなければならなかったんですよ。車の中で私はものすごく緊張して、おしりのあたりが汗でびっしょり濡れてしまったことをおぼえています(笑)」
オーディションに合格したサンディーは、NHKのラジオ番組「若いこだま」のパーソナリティに抜擢。ちなみに担当ディレクターの波多野紘一郎は、伝説の洋楽番組「ヤング・ミュージック・ショー」を手がけていた人物である。
同番組には頭脳警察、はっぴいえんど、夕焼け楽団、センチメンタル・シティ・ロマンスなども出演。数年後、サンディーがロックを本格的に歌うことになったのは、波多野氏の勧めがあったからだという。
■芸能界に入っても、歌手だというプライドは持ち続けていました
出演した番組は、NHKだけではなかった。声がかかれば、民放のバラエティ番組にも出たし、グラビアモデルの仕事をすることもあった。
「バニーガールの格好で“宛て先はこちら!”なんて言わされたり(笑)、いろいろな経験をしました。今でもよくおぼえているのは、民放のバラエティ番組で、歌手の役を演じたこと。西部劇のシーンで、私がピアノバーでジャズを歌い始めると、カウボーイが撃ち合いを止めるんです。“あれ? この状況って子供の頃、私が歌い始めると両親がケンカを止めたときに似てる”って思いましたね(笑)」
芸能界の仕事がどんなに忙しくなっても、サンディーは自分がシンガーだというプライドを忘れなかった。
「NHKには本当にお世話になったし、育ててもらったという恩を感じているけれども、民放のプロデューサーの中にはひどい人もいて、セクハラまがいの扱いを受けることもありました。私はそれが本当に嫌で、耐えられなくなっちゃったんです。でも、事務所との契約が残っているから、すぐに芸能界をやめることはできない。そのうち、私は体中にジンマシンが出て、精神的にまいってしまいました」
そのときにサンディーを支え、「契約書なんか破いちゃいなよ」と言ってくれたのが、夕焼け楽団の久保田麻琴。のちにサンディー&ザ・サンセッツで活動を共にする、運命の人である。
話を少し戻す。70年代後半に芸能事務所を抜けたサンディーは、その後、シンガーとしてのキャリアを着々と積んでいく。
「当時はまだ英語で歌えるシンガーが多くなかったから、コーラスやコマーシャルソングのお仕事をいただくことができました。私が重宝がられたのは、テイク1か2で決められること。コマーシャル制作会社の人にはよくスタジオ代が節約できて助かるなんて言われました(笑)。この頃になってようやく、歌手の仕事だけで生活ができるようになったんだけど、歌手だという意識はずっと持ち続けてきました。私はおぼえていないけど、ちっちゃい頃から“私は歌手でーす!”って周囲の大人に言いふらしていたらしいし(笑)、前世もその前も歌手だったという気がしてならないの……」
1976年、「グッドバイ・モーニング」で第7回世界歌謡祭のグランプリと最優秀歌唱賞を受賞。1978年、映画『ナイル殺人事件』の主題歌「ミステリーナイル」(名義はサンディー・オニール)」、1979年、TVアニメ『ルパン三世(セカンド・シリーズ)』のエンディングテーマ「ラヴ・スコール(名義はサンドラ・ホーン)」などのヒットを放つ。
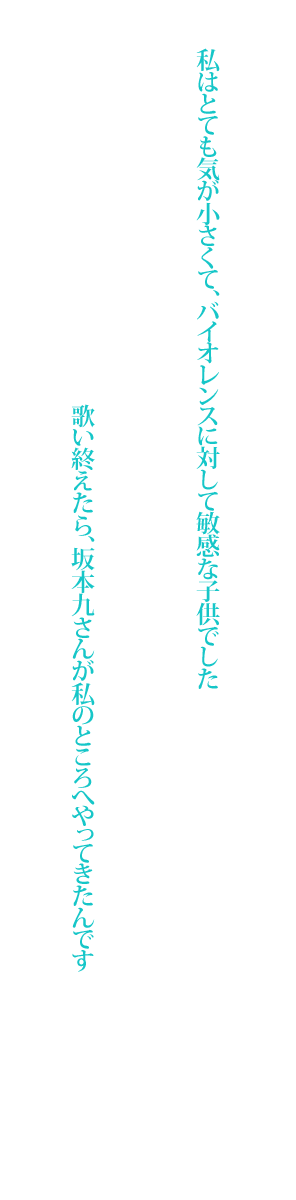




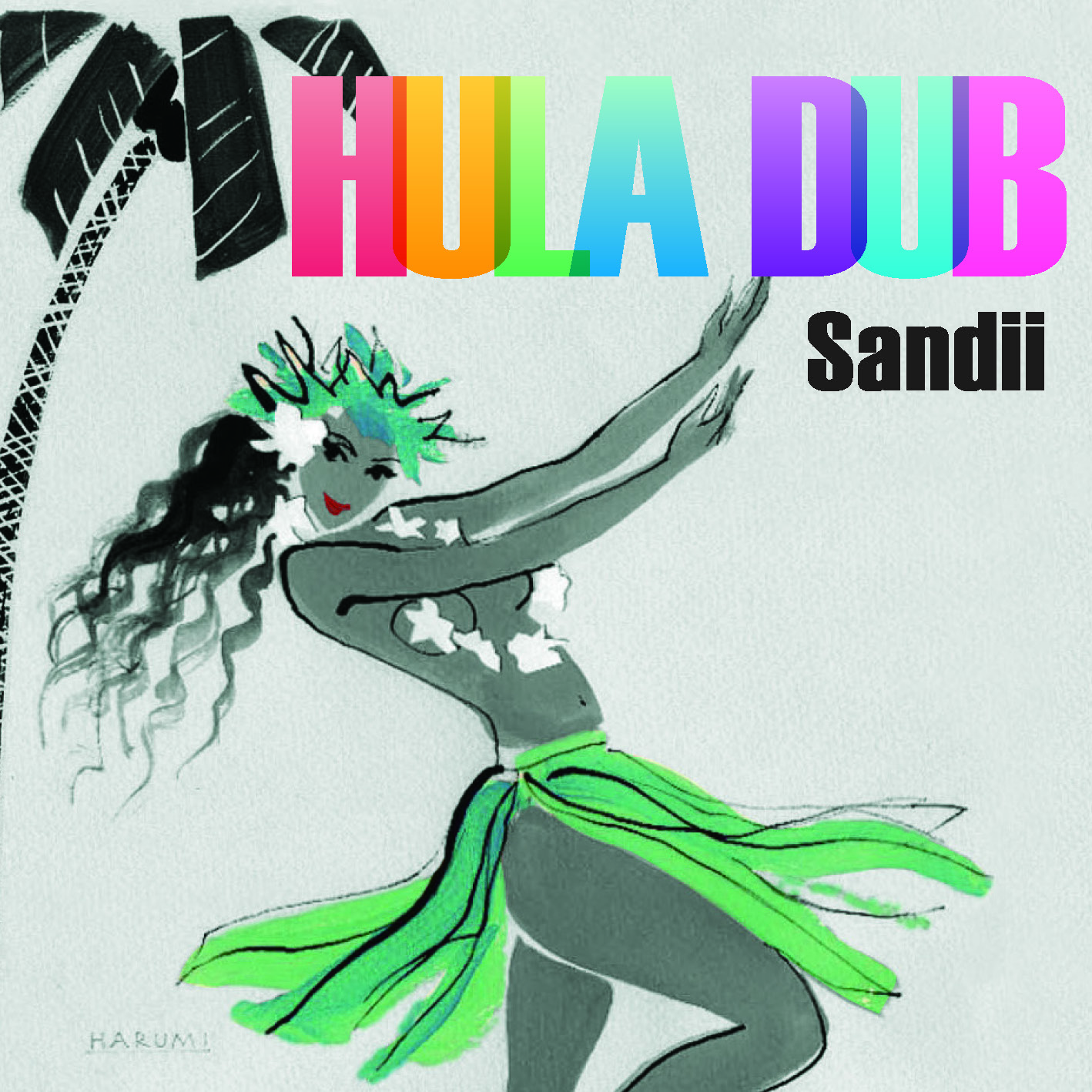





















1件のコメント
さむくなく、あつすぎもしない、心地のよい五月の風に吹かれた気になるサンディーさんであり、村瀬さんのインタビュー、文章です。そして、さりとてならではのひとつのパラダイスにしばしひたることができました。この風にいつまでも吹かれていたい。このシャングリラにもう少しとどまりたいと思いました。
コメントする ※すべて必須項目です。投稿されたコメントは運営者の承認後に公開されます。