|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集部多川(以下多川) |
さきほどのまゆ美ママもそうですが、たとえそれが「悪」であっても、それを必要とする人間がいる限り、自分たちの行為は「善」であるという、強靭な「必要悪の論理」がありますよね。 故・山口組三代目田岡組長も、自分たち山口組は社会の枠からはみ出た人間の受け皿なのだと語っておられます。「この社会の中に、在日や部落、義務教育も受けられていないような男がまともに生きて行ける場所があれば、山口組は必要ない。けれど、そんな場所はどこにあるのかと。だから、こいつら(組員)が、なんとか生きていける場所として山口組はあるんやと。 何か、飛田という社会もやくざ社会同様に、世の不条理の縮図のような存在で、そこには一般社会の論理など通用しない別の論理が働いて然りかもしれないなと、井上さんの本を読んで、あらためて考えさせられました。 |
|---|---|
| 井上理津子さん(以下井上) | ごめんなさい。私はやくざ社会にも疎くて…。一般社会の論理と別の論理、と言えば、そうなるのかな。飛田の彼女たちは、私たちが当たり前だと思っている社会福祉制度の外でずっと暮らしてきているのだと。 |
| 多川 | 飛田の経営者、まゆ美ママもそうですが、ある意味「社会事業」としての役割を担っているという、ひねりの利いた自負がありますよね。 |
| 井上 |
「女の子を採用するときは、裸にして体を確かめる」とか、それを聞いて「えっ!?」とたじろぐ私に、まゆ美ママはさらっとひとこと「それが何か?」と。 「注射の跡がないか、皮膚が腫れていないか、脱がして見ないとわからへんでしょ」とか、恐れ入るしかないですよね。 「何があかんねん!」って言われたら、前の前で泣き叫んでいる人がいない限り、抑えられないですよ。 飛田のしくみそのものがそうなんです。確かにお金は介在しているけれど「売春」ではないことになっている。一応、表向きは飲食業ですから。たまたま来たお客といい感じになって「じゃあ」という流れになることも「男と女やったら、そらあるでしょう」と。あくまでも「自由恋愛」なんですよ。 |
 |
|
| 多川 | そう言われたら、何も悪いことなどひとつもない気になりますね。その、今の時代、女性たちは自分の意思決定で「飛田を離れる」ことは可能なんでしょうか? 料亭に肩代わりしてもらった借金は、別の仕事で働いて返済するとか何かして…。 |
| 井上 | そこが、微妙なところ…としか、言えない。 |
| 多川 | そこなんですよね。彼らの「筋」に背いたときに世間一般の「道理」は通じない。タダじゃ済まない。そこが「ヤクザ」ではないですが、怖ろしいところだと思います。 |
| 井上 | 飛田の近くの喫茶店のおばちゃんいわく、「いまの女の子たちはもっとカジュアルに割り切った感覚で働いてるよ」。普通のOLがアルバイト感覚でやってたり、借金返すために学生が来てたとか。もし、それもリアルだとしたら、本人の自己決定による契約だったら、それはそれでいいのかもしれない。でも、そんなケースはおそらくひと握り。先にも言いましたが、私が取材した限り、「自ら好んで来ました」という女性はひとりもいなかった。みんな、仲介の人がいた。 |
| 多川 | 本人が決めてそこにいるとしても、お金なり何なり完全に「弱み」を握られた状態で「どうする?」と迫られたら、そうするしかないわけですよね。 |
| 井上 | 自主的なのか強制的なのか、ポイントはそこですね。 |
| 多川 | 口では本人も「問題ない」といってるけど、実際のその人がここに来た経緯や事情を推察すると、必ずしも自分の意思で選んで来たのではない事実を、井上さんは取材を通して実感されたわけですよね。 |
| 井上 |
この本を出した後に、売防法の前後の時代に飛田の女性のポートレートを撮っていた現在80歳のカメラマンの方と知り合ったんです。その方に撮り溜めたネガをたくさん見せてもらったんですよ。黒岩重吾の小説世界じゃないですが、当時の飛田の女性というと今なんかよりもっと暗く荒んだイメージを抱いていたのが、全然違っていてびっくりしました。そこに写っている女性たちは、貌立ちもきりっと引き締まっていて、優雅な着物やモダンなワンピースでおめかしして、芝居の見物やデパートに買い物にでも行く女性と変わらないという印象を受けました。 先述してきたことと矛盾するんですが、その頃は、壁の内と外の境界線が見えにくいというか、こっちとあっちが「地続き」だったんじゃないかと。 |
| 多川 | 昔のほうが、リアルには地続きやったんじゃないですか? たとえば、飛田の存在をあたりまえに知っている人はもっと多かっただろうし、「あそこは飛田ゆうて、きれいなお姉さんと男の人がええことする街なんや」とか、商店街の人たちも「あの人は飛田のお姉さんや」とか、ちゃんと「在るもの」として受け入れられ、根づいてたような気がします。たとえば、やくざにしても、私が子供の頃、昭和40〜50年頃はもう少し身近な存在だったような…(苦笑) |
| 井上 | うーん。私自身は、ヤクザの人たちとは大変遠い所にいたから。ピンとこないですね。 |
| 多川 | 今の時代の方がよっぽどクリーンで安全な社会ではあるけど、それは本当にそれらの「悪」がなくなったのかどうかは疑問でしょう。単に見えなくなった、見ようとしなくなった、見え方が変わっただけかもしれないし。たぶん、昔の方がダーティで危険な要素が街に溢れかえっていたけど、でもそういう「ないほうがいいもの」を許容する懐は深かったのかもしれないですね。 |
| 井上 | とても難しい問題です。おっしゃる「昔の悪」については、私はリアルな体験がなく、本や映画や、あるいはリアルな体験者からの聞き取りからイメージするまでなので、同意する・しないを言いかねます。私にとっては、町歩きや人権の取材を長くしてきて、その奥行きに飛田があった。その程度の、能天気な位置づけでしたから。 |
| 多川 | 逆にそのほうがよかったのかもしれませんね。下手に知りすぎていると、まさか飛田を取材しようなんて、そんな度胸は持てなかったかもしれないですよ。 |
| 井上 | やっぱり、怖いもの知らず、でしょうね。 |
| 多川 | そう、井上さんに聞きたかったことなんですけど、飛田の人たちは「遊廓がなくなる将来」を望んでいるのかどうかと。 |
| 井上 | ご年配者たちは、自分たちの代で「飛田は終わる」とおっしゃってますけど、若手には、ビジネスとして隆盛にしていかなければという意気込みの人たちも少なくないと思います。 |
 |
|
| 多川 | 年配の人は、ある種の役割は終わったと。 |
| 井上 |
社会に対しての「役割」と言うよりは、とりあえず「自分が食えた」ということだと思います。 たとえば、飛田という街が行政の手で切り刻まれて排除されたとしても、きっとまたどこかに「新飛田」ができるでしょうね。 |
| 多川 | まだ「新飛田」ならいいんですけど、一見しただけでは「飛田」とわからない形で、もっと下に潜る可能性もあるじゃないですか。 |
| 井上 | そうでしょうね。 |
| 多川 |
そうなると、もっと悪辣な商法で女性たちも搾取されるだけとか。下には下じゃないけど、今の飛田を「あの頃はよかった」と懐かしむような「最悪のその先へ」みたいなパターンに陥るような気がします。 経営、ビジネスとしてはどうなんでしょうか。お客さんの数は、それほど増えてはいない? |
| 井上 | 客数はこの何十年ずっと横ばい状態と聞いています。でも「横ばい」というのは、いまの世の中、いいということでしょ。「井上さんの本のおかげで、お客さん増えたわ。ありがとう」とか言われると、ちょっとは貢献できたような気がしたり。って、言ってることが矛盾だらけですね、私(笑)。 |
 |
|
| 多川 | 彼ら(飛田の経営者や女性たち)には彼らの哲学、考え方があって、わたしたち外の人間に対して、言いたいこと訴えたいことは腐るほどある。そんな彼らの言葉にならない声を言葉にしたのがこの本だと、わたしは強く思いました。 |
| 井上 | そう思ってもらえると、とても嬉しいです。 |
| 多川 | 取材・撮影お断りというのは、社会に対する拒否、拒絶かもしれないですね。言ったところでわからないだろうし、おまえたちに何がわかるか、と。 |
| 井上 |
それもあるだろうけど、諸事情もご賢察ください…。彼らの中には、言葉にならない、口にできない「もやもや感」はあると思います。本が出て3カ月ほど経って、取材に協力してくれた人が電話をくれたんです。 こんな分厚い本を読むなんて生まれて初めてだった、24色の色えんぴつで色分けしながら読んだと。 「何ページにこう書いてあるやろ?」と文章を読み上げながら、「ここ、おれもまさにそう思っててん」「井上さん、わかってくれてうれしいわ」とか、一生懸命伝えてくれるのがうれしくて、ありがたくて、泣きそうになりました。 |
| 多川 | 自分を語ったことも、語ろうと思ったこともない。こうして井上さんが飛び込んで、聞き取って、自分の中にある“もやもや”とした言葉が文字として表に出るというのは、そういう人たちにとってはすごいことなんだと、今日井上さんと話して改めて思いました。 |
 |
|
撮影/岡崎健志
取材期間12年に及ぶ、著者渾身のルポタージュ!
遊廓の名残りをとどめる、大阪・飛田。
社会のあらゆる矛盾をのみ込む貪欲で多面的なこの街に、
人はなぜ引き寄せられるのか!
取材拒否の街に挑んだ12年、衝撃のノンフィクション。
遊廓の名残りをとどめる、大阪・飛田。
社会のあらゆる矛盾をのみ込む貪欲で多面的なこの街に、
人はなぜ引き寄せられるのか!
取材拒否の街に挑んだ12年、衝撃のノンフィクション。
『さいごの色街 飛田』を記した著者の原点。
50年で、8000人もの赤ちゃんを取り上げた助産婦・前田たまゑ。彼女の産婆人生は、神戸の福原遊廓から始まった。堕胎が許されなかった戦前の遊廓、戦時下のお産、戦後すぐのベビーブーム、いつしか主流となった病院出産の時代……世話焼きおばさんの語り部から聞こえてくる助産の歴史は、昭和を背負った女性たちの肉声を伝え継ぐ。『さいごの色街 飛田』を記した著者の原点。
50年で、8000人もの赤ちゃんを取り上げた助産婦・前田たまゑ。彼女の産婆人生は、神戸の福原遊廓から始まった。堕胎が許されなかった戦前の遊廓、戦時下のお産、戦後すぐのベビーブーム、いつしか主流となった病院出産の時代……世話焼きおばさんの語り部から聞こえてくる助産の歴史は、昭和を背負った女性たちの肉声を伝え継ぐ。『さいごの色街 飛田』を記した著者の原点。
日刊ゲンダイの連載「本屋はワンダーランドだ! 」が一冊に!
都内60ヵ所に及ぶ、個性的な町の本屋さんとブックバーを紹介! 独自に本をセレクトし、棚作りに工夫を凝らす新刊書点。「昭和」「サブカルチャー」「辺境」「車」「エロ」など得意分野を打ち出した古書店。雑貨販売、ブックカフェ、ブックバーを兼ねた書店など、ちょっと変わった町の本屋さんがずらり。実際にお店を訪ね取材したからこそ知り得た、店主の人柄や、お店の雰囲気、オススメ本などの情報も満載。
都内60ヵ所に及ぶ、個性的な町の本屋さんとブックバーを紹介! 独自に本をセレクトし、棚作りに工夫を凝らす新刊書点。「昭和」「サブカルチャー」「辺境」「車」「エロ」など得意分野を打ち出した古書店。雑貨販売、ブックカフェ、ブックバーを兼ねた書店など、ちょっと変わった町の本屋さんがずらり。実際にお店を訪ね取材したからこそ知り得た、店主の人柄や、お店の雰囲気、オススメ本などの情報も満載。
| 015 フリーライター 井上理津子さん Interview | |
|---|---|
| 第1回 是々非々、最後の遊郭・飛田。 | 2013年3月21日更新 |
| 第2回 語られない飛田のリアル。 | 2013年4月10日更新 |
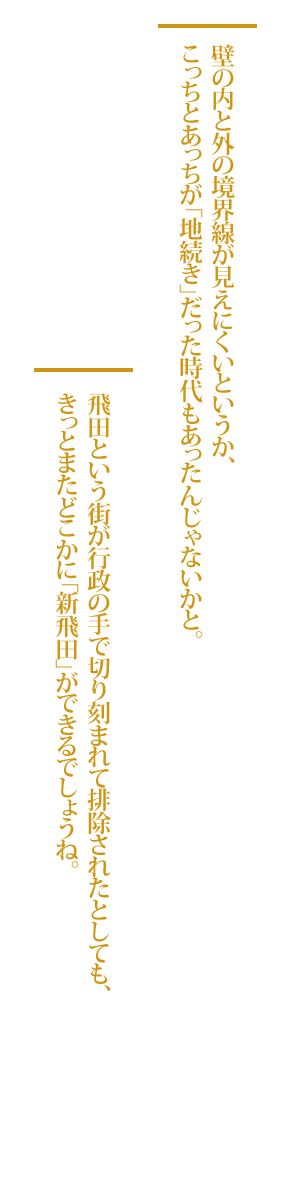
1955年奈良生まれ。人物インタビューやルポを中心に活動を続けており、特に生活者視点を踏まえた文章が多い。『さいごの色街 飛田』は足掛け12年間に及ぶ取材をもとに上梓。長く大阪を拠点としていたが、現在は東京在住。最近は葬送をテーマにした取材に取り組んでいる。
![]()

- 020
五味太郎さん×
イシコさん - 2016020

- 019
作家
平野啓一郎さん - 2015019

- 018
疫学者・作家
三砂ちづるさん - 2014018

- 017
写真家
鬼海弘雄さん - 2014017

- 016
劇作家
平田オリザさん - 2013016

- 015
フリーライター
井上理津子さん - 2013015

- 014
政治活動家
鈴木邦男さん - 2013014

- 013
歌手
八代亜紀さん - 2012013

- 012
社会学博士
大澤真幸さん - 2012012

- 011
カルーセル麻紀さん - 2012011

- 010
政治学者
原武史さん - 2011010

- 009
社会学者
宮台真司さん - 2011009

- 008
ノンフィクション作家
佐野眞一さん - 2011008

- 007
精神科医
春日武彦さん - 2011007

- 006
AV監督
村西とおるさん - 2011006

- 005
芸人/漫才協会名誉会長
内海桂子さん - 2011005

- 004
株式会社リナックスカフェ 代表取締役
平川克美さん - 2010004

- 003
映画監督
塩屋俊さん - 2010003

- 002
セラピューティック・トレーナー
白石宏さん - 2010002

- 001
生活哲学家
辰巳渚さん - 2010001
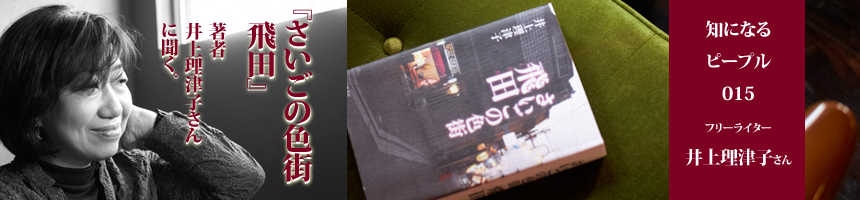
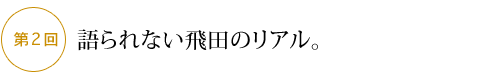
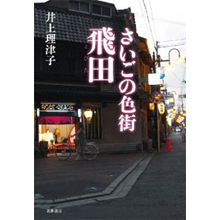
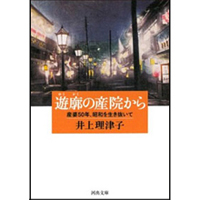
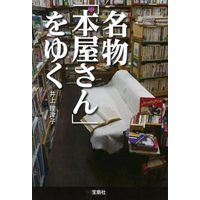
1件のコメント
著者や編集者は飛田新地を現代の”健全な日本社会を逸脱した異界”として捉えているが、同様の売買春場所として全国に展開するソープランドについて著者らはどう考えているのか不明だ。
インタビューを通じて垣間見るこの本では、今も昔もソープランドは存在しないかのようで、全く視野の外に置かれている。しかし現実には東京・吉原や川崎・堀之内など首都圏でもソープの聖地として知られる場所があり、これなどは飛田と同じ異界ではないのか。両者の比較考察がなされていないことに拍子抜けしたしまう。
社会事象を正確に、かつ多角的な視点で考察する作業をせずに先入観や思い込み、浅薄な正義感でルポしたとしたら、著書の価値は大幅に減ずるだろう。
現在、コメントフォームは閉鎖中です。