2015-06-5
生まれたて子羊のジャケット
- オーガニック (有機でより自然に近い食べ物や商品 ※私の個人的な解釈)
- フェアトレード (生産者や労働者との公平な取引)
- エシカル (倫理的で環境や社会を配慮したもの)
こういったことにちなんだ製品を、可能な限り選びたいと思うようになったのはいつからだったろう?
記憶をさかのぼると、そのような言葉をはっきりと意識するようになったのは、イギリスへ移住した6年前からだ。中でも、はじめて「フェアトレード」という言葉に直面したときのことは、今でもよく覚えている。
イギリスの生活に少しずつ慣れ始めた頃、いつものように近所の大型スーパーマーケットで買い物をしていると、あることに気が付いた。
青と緑のエキゾチックなロゴマークの下に、’FAIRTRADE’ と書かれたロゴが記載されている商品と、何も記載されていない商品が横並びになっているのだ。
その後店内を注意深く見回してみると、そのロゴはフルーツ、コーヒー、チョコレート、スパイスなど、数多くの商品に記載されているではないか。そして、その’FAIRTRADE’という商品は、そうでない商品よりも、少し値段が高い。
なんなんだこの謎のロゴは?と気になって、帰宅してから調べてみると、
「このフェアトレード製品は、ケニアやコロンビアなどの発展途上国の生産者と公正な価格で取引をしています。また、あなたがこの製品を購入することは、現地のコミュニティーへの貢献にもつながっています。」
というようなことが、ウェブサイトにずらっと書かれていた。
ふむふむ。’FAIRTRADE’製品を選ぶことによって、生産者や労働者の権利を守ることができるなんて、すごく素晴らしいじゃないか!
その時はそう単純に解釈をし、その日から選択肢がある場合は’FAIRTRADE’と書かれた商品をなるべく選ぶようにした。
初めのうちは、フェアトレード製品を購入することで自分がちょっと社会に貢献しているような、また遠く離れた発展途上国の誰かを支えているような、心地よい満足感を得ていた。
しかしながら時間が経つにつれ、「実際、その生産地や労働者について何一つ知らないにもかかわらず、いいことをしてるような気になるのはあまりに身勝手じゃないか?」「そもそも、特定のコーヒーを買うことで、誰かの暮らしをよくすることなど出来るのだろうか?」と考えるようになった。
だからといって、フェアトレードマークを無視して安い方のロゴなし商品を買うかというと、それはさらに良くない気がする。
そんな答えの出ないジレンマに陥っていたとき、本屋である一冊の本に目が止まった。
タイトルは、’フェアトレードのおかしな真実 / UNFAIR TRADE’。
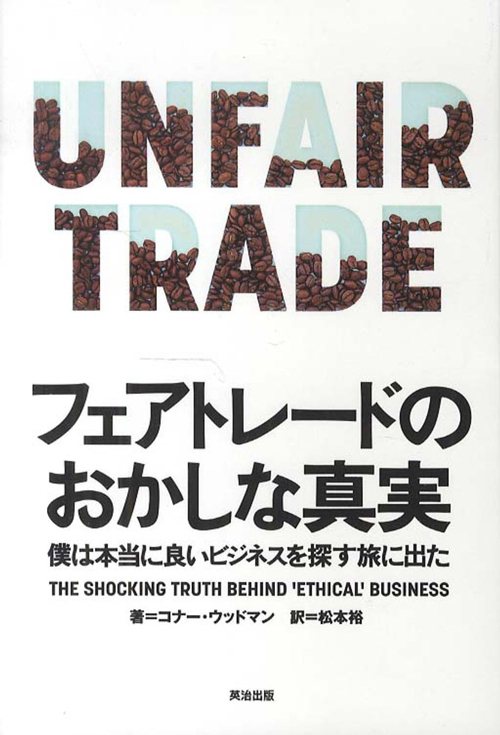
その内容は、テレビキャスターでジャーナリストでもあるイギリス人男性が、本当に良いビジネスを見つけるために、iphoneなどを組み立てる中国の大規模工場や、死と隣り合わせのコンゴの鉱山(その鉱山は私たちのPCやスマートフォンに使われている)などの世界各地を実際に訪れ、真実を探る旅にでるというものだった。
身の危険さえも伴うこの旅へと彼を導いたものは、私が感じていた違和感と同じものだった。
この本には、フェアトレード認証マークが、今では売り上げ上昇のためのブランディング効果になっているという事実や、フェアトレードを謳っている企業の生産地でのグレーゾーンなど、彼の経験に基づいた興味深い内容が、詳しく書かれていた。
この本を読み終え、私が再確認したことは、「自分の目で実際に見たものを一番に信じて、その時感じたことを大切にしたい。」ということだった。
何が本当で何が嘘か判断のつかない情報に踊らされ、ひとり悶々とするよりも、自分の目の前で起こる事柄や経験を基準として、そこに思いを巡らせたい。
それは簡単なようで、意外と難しい。
しかしこの想いが、私の中の「まだ見ぬ世界をこの目で見たい」というひそかな情熱を、まだまだ駆り立て続けているのは事実だった。

私と夫は、約1年間住んだ南アフリカのケープタウンを、4月初旬に自転車で出発し、今ナミビア共和国にいる。
国土の大部分が砂漠地帯で、人口密度が1㎢に2人という、人が極端に少ない国だ。そのため、村と村との間隔が50~100kmほどあり、その間お店も住居も何もないような、乾燥した土地が延々と続く。
南部ナミビアはほとんどの川がからからに干からびているほどなので、いくら土地があっても作物が育たたない。しかしそんな気候下でも、羊や牛を放牧している農家を見かけることはあった。
私たちは、小さなガソリンスタンドと売店が一件ずつだけある「街」で、ある家族と出会った。見るからに優しそうな夫婦と、4人の子供たち。彼らは白人系ナミビア人(元のルーツはドイツ)で、その街から60km離れた場所に家畜を飼って生活をしているという。そしてありがたいことに、通りがかる時はぜひ寄っていくように、と声をかけてくれた。
彼らの家は、メインの道路(といっても車が1時間に1台しか通らないガタガタの未舗装道路)から5km離れた僻地にあった。正直いうと、自転車で60kmを漕いだ後の、ほとんど漕ぐこともままならない未舗装の5kmの道のりは、疲れた体にかなり堪えた。
だけど、疲労が顔に滲んだ私たちを、家族そろってあたたかい笑顔で迎えてくれた彼らを見て、ここまで来た甲斐があったとすぐに思い直した。

その夜、私たちは家族のリビングにお邪魔し、色々な話をした。
4人の子供たちは、下から4歳、9歳、15歳、17歳で、全員学校へは通っていない。彼らは母親のホームスクールで育ち、毎日家の手伝いをしている。そして現代社会でぬくぬくと育つとそうはならないだろうというほどの、気の効きようと純粋さを持ち合わせていた。
ビールを一杯ごちそうになったあと、お父さんのトーマスは私たちを物置き小屋へ案内し、どんな家畜農場を経営しているのか説明してくれた。
彼らの主な家畜は、他の農場と同様に羊だが、その羊たちは肉を売るためではなく、毛皮を売るために飼っていると聞いて驚いた。そして羊は生まれたてが最も皮が柔らかいため、生後48時間後に皮を剥ぎ取るというのだ。
その後、ちょうど今朝張ったばかりだという、キャンパスのようなパネルに張られた毛皮の1つを、トーマスは気さくに見せてくれた。すでに野原をかけ回る動物の姿とはかけ離れていたが、まだ少し暖かかく、とても柔らかかった。

この毛皮は、地元ナミビアのハイエンドファッション産業に売られ、高いもので1着100万円もするジャケットに生まれ変わる。
主なクライアントは、中国とロシアのお金持ちで、そのジャケットは丈夫ではあるものの、ファーコートのように保温性に優れているというわけではないと、トーマスは教えてくれた。ということは、このジャケットはあくまで「ファッション」の用途だけのものだ。
これだけ聞くと、ほんの一部のお金持ちのファッションのために、子羊がわずか48時間の命のために生き、そして屠殺されるのはとても残酷で、不必要に思える。また、いくらそのジャケットが魅力的で私の手の出る価格だったとしても、私はそれを欲しいとは決して思わないだろう。
しかし、その後のトーマスの話は、今まで私が想像もしなかった内容だった。
この子羊の毛皮を生活の収入源とするのは、作物が育たないこの地域ならでは昔からの伝統で、数十年前は1年につき、ナミビア全土で約500万体もの毛皮を生産していたという。
だが、15年ほど前から、毛皮生産に対する法律が厳しくなると同時に、リアルファー反対の動きが世界で活発になり、今では12万体にまでその生産数は減少しているようだ。
こんなナミビアの僻地にある小さな農家にまで、途上国での毛皮反対の活動が大きく影響を与えていることは、正直驚きべき事実だった。そしてこの大きな数字の変動は、毛皮反対の活動家にとっては「とてもいい風潮」なのだろう。
トーマスは、子羊を毛皮のために殺す残酷さも、ハイエンドのファッションに対する矛盾についても、よく理解をしている。しかし、彼の家族がこの土地で生きていくために家畜は不可欠で、ならば毛皮用ではなく、食用としての羊を育てたらいいかというと、そうでもない。
毛皮用の羊は単価が高いため、食用の羊よりもかなり少ない数の羊を飼うことで生計をまかなうことができる。また、生まれてからすぐに屠殺するため、羊を守るためにヒョウやジャッカルなどの捕食動物を殺さずに済む。
(食用家畜農家は、ヒョウやジャッカルの被害を防ぐため、夜中に捕食動物の狩りをする。一度夜中にテントのそばで銃声が鳴り響き、身が縮む思いをした。)
この話しを聞いて、私は分からなくなった。
命の数か。生きる時間か。
自分のためか。誰のためか。
その晩は、様々な考えが私の頭の中に浮かんでは消え、ぐるぐるとループした。

この家族に出会うまで、趣向としてのファッションに動物を殺す必要性は、何もないと私は考えていた。
しかしこの家族も、動物と同様、共に生きている。
ひとことに「毛皮はいらない」と断言してしまうのはあまりにも容易で、現実は私が想像するよりいつも幾分か複雑だった。
現地を訪れないと知る由もない真実が、どこにだって存在している。だが、今の私たちが生きる社会では、その真実が自分の目で見えないことが残念ながらほとんどだ。
しかしそれでも、’オーガニック’ ’フェアトレード’ ’エシカル’ などの表面的な言葉に捉われる前に、まずは普段自分の身につけているもの、口にしているものにそっと思いを寄せてみたい。
それが世界を変える第一歩なんじゃないかと、本気で思うのだ。



コメントはまだありません
まだコメントはありません。よろしければひとことどうぞ!
コメントする ※すべて必須項目です。投稿されたコメントは運営者の承認後に公開されます。