『読後の一服ノート』text: Ritsuko Tagawa
日々ことあるごとに集まって、下ネタ全開の恋愛話をぶちまけあい、泣きたいときには一緒に泣き、男と別れたとなれば「あんな男!」と一斉に袋だたきに過去を蹴散らし、誰かがつらいとなれば手に手を取ってアブダビまで傷心セレブ旅行。『SEX AND THE CITY』の爽快な面白さは「やっぱ女友だちって最高!」と女に生まれた幸せを実感できるところにあると思う。 けれどまた、日々、近しく語り合える友だちでなくても、遠く離れてたまにしか会えずとも、会った瞬間、同じ時を過ごしてきたかのように通じ合える友もいる。相手の中に自分がいて、自分の中に相手がいる。同じ時代に生きられて良かったと、ただありがたく思える存在。一生のうちに、そういう友情が持てたなら、それはもうこれ以上ないくらい生まれてきて良かったと、生きてきて良かったと感じられるものではないか。わたしにとっての友情とは、それはもう生き甲斐としか呼べないものだったりする。 昔、自分の祖母が、次々と友に先立たれていく晩年にぽつりこぼした言葉が、今も忘れられない。 もうひとり、友情の哀切を思い知らされた人物といえば、森繁久弥(享年96歳)である。日本のテレビ・映画界が最も輝いていた時代を共に駆け抜けた俳優仲間、腹心の友が次々とこの世を去り、その葬儀のたび悲しみに打ちひしがれた姿で杖をつき参列していた森繁翁。その映像を見るたび、はかりしれない寂寥感に胸が締めつけられた。「本来ならば、わたしが・・・」友に語りかける言葉の中で、こんなにも悲しくつらい言葉はあるだろうか。 そんな森繁翁の無念が滲む後ろ姿に、友情の何たるかを痛切に感じ取ったわたしは、いつも親友との別れ際、「ほな、また!」と手を振りながら心の中で縁起でもないことを祈ってしまうのである。 文・多川麗津子
4/4
|
|
|
|

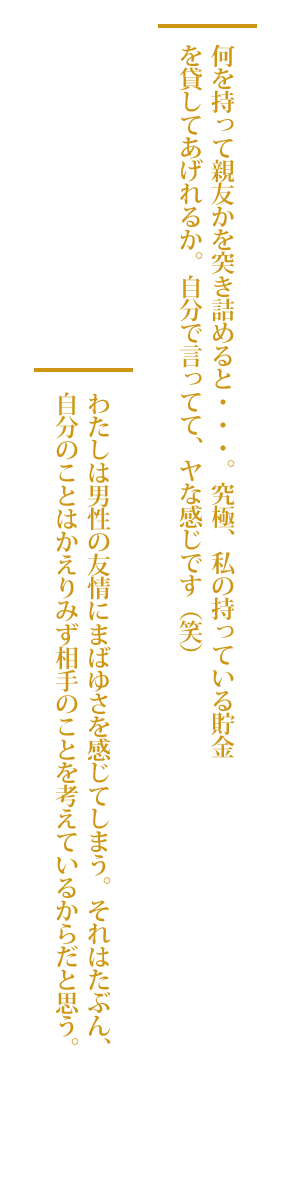
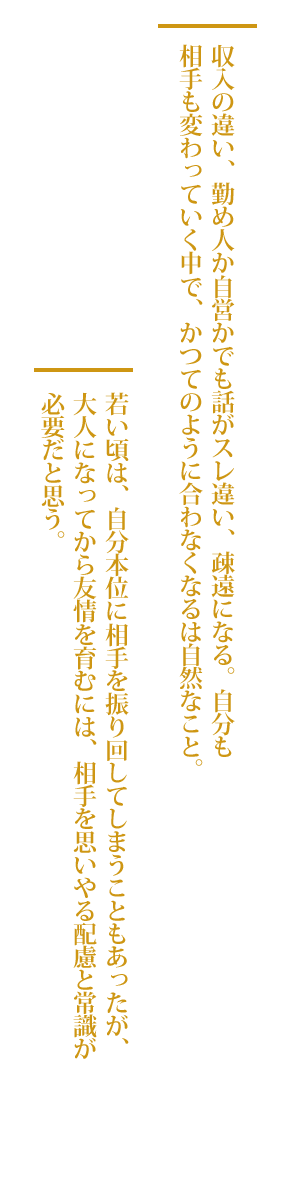
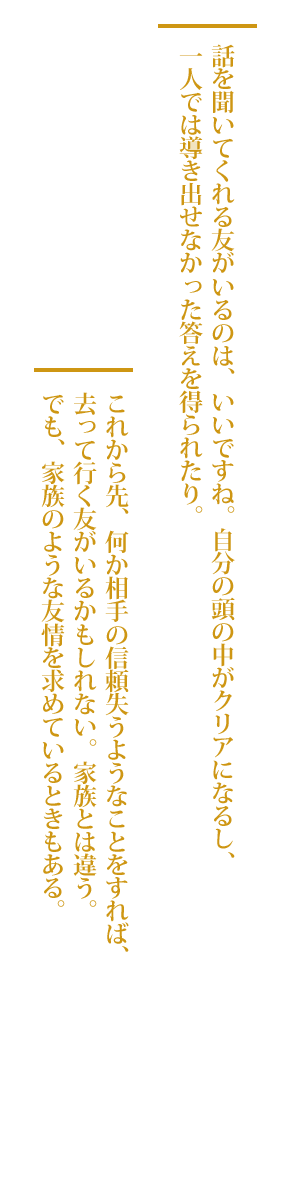







コメントはまだありません
まだコメントはありません。よろしければひとことどうぞ!
現在、コメントフォームは閉鎖中です。