2011-06-14
ブラックスワンに観た
“恐がり女”の怖ろしさ。
自分の器量・力量・才能を超えた大役を与えられたことで、思いもよらない潜在能力がスパークする場合もあれば、そのプレッシャーに押しつぶされ自滅する場合もある。いわば前者が天才、後者が凡才といおうか。しかも運命の残酷さは、平凡な性格の人間に有り余るほどの地位や名誉、栄光の輝きに満ちたチャンスを与えるところに遺憾なく発揮される。そこまで大層な世界にさえ入らなければ、普通に近所で有名な「かわいい奥さん」になって、子どもの入学式や参観日など表に出れば「昔モデルか女優さんやってはったみたいよ〜」ともてはやされ、「大したことないですよ〜」と笑って生きられたのにと悔やまれる悲劇のアイドル・女優・芸能人は結構いる。先日、若くして自ら命を絶ったアイドル・上原美優さんも、もしかしたら、身にそぐわぬ非凡な運命の犠牲になった平凡な女の子のひとりだったのかもしれない。
不幸な運命が必ずしも不幸な人生につながるわけではないように、幸運な運命が即ち幸福な人生に至るとは限らない。どちらかと言えば、人から見れば幸せに恵まれて映る幸運ゆえの生き難さの方が恐ろしくキツイのかもしれない。と、昨日「ブラック・スワン」を観て、人間の精神をじわじわと破壊していく幸運な悲劇を痛く思わされた。と同時に、そんな心配だけはまったくいらないけど一応、念のため、何にも「選ばれたくない」と心に刻んだわたしである。何せ、神や運命や時代に見込まれた人間は、よほどの才と器がない限り、ロクなことにならん。人は人に見込まれてなんぼの生き物という自分の持論を再認識させられた映画であった。
映画のストーリーは、華麗なるバレエの世界でプリマを夢見る可憐な少女が、追い詰められた奈落の底で見つけた「もうひとりのわたし」という、少女漫画風の心理ホラーサスペンス。
浜村淳風に「観なくてもいい」くらい微に入り細に渡り解説させてもらうと、主人公はバレエダンサーのニナ(ナタリー・ポートマン)。儚いほど可憐でキレイで上品で、バレエの才能も確かにあるものの、窮屈すぎるほどクソまじめな頑張り屋さんゆえに「抜け」も「遊び」も何にもなく、よくは知らないが、吉永小百合を彷彿とさせる面白味のない美しさである。そこにもってきて母親の過保護な溺愛によって下手なお姫さま気分が抜けず、女には無用の「固さ」「臆病さ」「自己愛のきつさ」が致命的な女の子である。ある日、ニナが所属するバレエ団のプリマであるベス(ウィノナ・ライダー)がスターの座を追われるように引退。(このベスも、プリマ凋落の憂き目に感情を炸裂させ、後に自壊)。そこに新たな振り付け師・トマスが登場。「わたしも知らない私の魅力」を発掘&開発させたら当代一流とおぼしき振り付け師・トマスが、新たなプリマのお披露目公演となる「白鳥の湖」のプリマ役をオーディションで選ぶという。ひたすらプリマの座をめざし不惜身命の構えで稽古に明け暮れてきた貴乃花親方、じゃなくニナである。何としてもこのチャンスをものにしたい。しかし、いかんせん生真面目で臆病な性格ゆえ、オーディションでは極度の緊張で失態を演じ、せっかくのチャンスを逃してしまう。もはやプリマの夢はついえたと絶望しあきらめかけたそのとき、運命の白羽の矢に射止められたニナ。意外や意外、トマスが抜擢した白鳥プリマはニナであった。信じられない興奮と喜びに胸躍らせ、持ち前のひたむきな律儀さと責任感を発揮して一心不乱に稽古に励むニナであったが、可憐で無垢で純真な白鳥パートは完璧でも、奔放で妖艶で官能的な魔性の黒鳥パートになると、悲しいくらいカチンコチンの冷凍マグロ。「おまえのその踊りで、誰が欲情するか」と屈辱的な言葉でトマスになじられたニナは、自分を解き放つべく自己開発の底なし沼に堕ちてゆく。そこに同じダンサーで解放感たっぷりのセクシー小悪魔女子・リリーが、「月曜日のユカ」の加賀まりこ的な魅惑の黒鳥オーラを振りまいてくるから、たまったもんじゃない。邪悪な欲望すら魅惑の媚薬に変えてしまう生まれながらの黒鳥・リリーにプリマの座を奪われはしまいかと戦々恐々、焦るわ、足掻くわ、もがくわ、落ちるわ、日に日にかぼそい神経を磨り減らし、発狂寸前まで病んでいくニナ。自分にない「セクシー」を徹底的に要求され、見せつけられ、自分を解き放とう解き放とうと頑張れば頑張るほど自縄自縛の生き地獄に陥ったニナは、現実と幻覚の狭間をさまよう亡霊と化すまで完全崩壊。しかし、壊れた魂と引き替えに手にした狂気の羽によって、恐ろしいほど華麗な変身を遂げたニナの残酷なまでに美しい悲劇の結末とは・・・と、ざっとそんなような話である。
「純白の野心は、やがて漆黒の狂気に変わる」というキャッチフレーズにあるように、純真無垢なバレリーナがプリマのプレッシャーに耐えきれず心を病み、狂い、ひょう変していく王道的な心理サスペンスなのだが、それを「バレエ物」で魅せるところがこの映画の憎いところ。女の邪で浅はかな好奇心は、人間心理のおどろおどろしさとバレエのロマンティックさという相反するものの組み合わせに小躍りして異様に波立つ癖がある。だから女性週刊誌はつねに邪悪な俗欲と優雅な洗練の清濁混合リミックスなのである。
わたしがこの映画を観て、「やはり…」と導き出した結論。それは、女のくせにやたら恐がる、おびえる女は、どんなにキレイで可愛くてもマズイ、いただけないということである。何しろナタリー・ポートマン演じるニナときたら、映画の出だしから最後まで終始おびえっぱなし。つねに眉間に縦ジワを寄せた頼りなげなハの字眉で「どうしよう・・・」「恐い…」とビクビク怖じ気づいてるのが顔に出まくっていて「そんなお前が一番怖いわ!」とイラッときた。
たぶん健全なる男性諸氏からすれば、おびえればおびえるほど、困れば困るほど、もがけばもがくほど愛らしさ倍増のナタリー・ポートマンの表情に無性にそそられるものがあるのかもしれないが、万引きGメンのおばちゃんばりに鋭い同性の眼からすれば、何を今さら、あんたが隠し持ってる本性などお見通しなのである。
何しろバレエ団の花形スターであるプリマへの強烈な憧れからとはいえ、ベスの楽屋に忍び込んでは化粧道具やバレエ道具を盗んでいたニナである。結果は無残に玉砕とはいえ、オーディションに選ばれるためトマスの元に誘いの勝負メイクを決め込んで色仕掛けの作戦に出る勇気も小狡い根性もきっちりある。それの何が純真無垢な白鳥かと自分で突っ込んで自分で笑える神経の持ち主であれば、ここまで追い詰められることはないのだろうが、そういうやつは端っから手つかずの未開の土地にしか興味のない名うての女ディベロッパー・トマスの眼に止まらないから、身に余る運命に選ばれる心配は一切無用なのである。
しかしながら、 真面目な女性にありがちな自分の中に眠っている私を呼び覚ましたい覚醒願望とはいったい何なのか。大体からして、死に物狂いで行き着いた「もうひとりのわたし」なんて大抵ロクなもんじゃないというのが一般的な女の相場勘だったりする。現代女性はとくに「自分を解き放つ」という言葉に弱かったりするが、普通に今まで生きてきて解き放てないということは、解き放つ必要がないか、もしくは解き放つモノがないかのどちらかだと、そこは冷静に少なめに見積もってみた方がいいような気がする。
おそらく、ニナの母親はわたしと同じ同性の厳しい眼で、臆病なくせに自尊心だけは高い娘の「厄介さ」を見抜いていたのだろう。念願のプリマに選ばれた喜びを伝えたとき、電話の向こうで一瞬、言葉を飲み込んだ母親に、「どうして、喜んでくれないの?」とニナがいぶかしがるシーンがあった。同じバレリーナとして群舞ながらもその世界の過酷さを知り尽くしていた母親はきっと、娘を思うがゆえに言ってやりたかった。でも、言えなかったのだろう。「あなたみたいな、ぬいぐるみを抱いて寝るようなお嬢ちゃんには無理」だと。この映画、ストーリー展開も心理描写も至ってシンプルでわかりやすいのに、母と娘の愛憎関係だけは実に精緻な複雑さをもって描かれているところがやけにリアルで気に入ってしまった。
汚れなく美しい白鳥とはいえ、ひとたび白い羽をむしり取れば、黒い生身が顔を出す。それならいっそ、見るからに黒いカラスの方が美しいとも言えるし、悪女遊女の深情けというがごとく、白鳥よりカラスの方が情け深い純情乙女だったりするわけである。引いては、黒鳥の中にも酒を飲んだら思い出す「わたしが白鳥だったあの頃」があり、普段は明るいママが酔った弾みでホロリとこぼす昔話に、店の若い女の子たちが黙って「お疲れさま」と看板を下ろして帰って行くみたいな、しどけない場末のブラックスワンにこそ、実は正真正銘、汚れても汚れきれない女のしたたかな純真が宿っているような気がしないでもない。
とはいえ、何度もしつこく繰り返すが、そういうブラックな純真さは、悲しいかな、得てして選ばれないのが人生の皮肉なところである。
映画終了後、「泣ける映画」でも何でもないのに、泣いてる女の子がいた。「なんかぁ、むっちゃ怖くなって…」と、物欲しそうに彼氏を見つめる上目遣いに、ほんまもんの邪悪なブラックスワンを見た思いがしてゾッとした。少女の頃はとうに過ぎても「恐い・・・」とか平気で言ってのけられる女ほど怖ろしいものはない。絶対に。

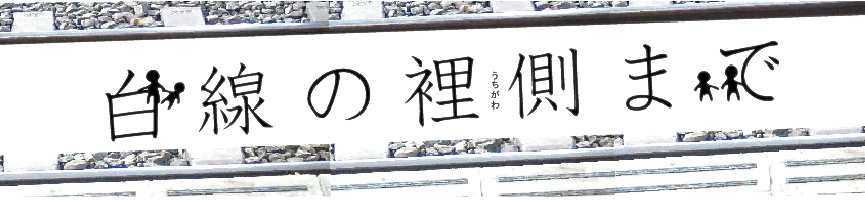

コメントはまだありません
まだコメントはありません。よろしければひとことどうぞ!
コメントする ※すべて必須項目です。投稿されたコメントは運営者の承認後に公開されます。