2011-04-26
フォーエバー・キャンディーズ
21日、元キャンディーズ、女優・田中好子さんが乳ガンでこの世を去った。映画「黒い雨」でアカデミーやブルーリボンなど栄えある女優賞を総なめに、女優としての大きく飛躍しようという矢先に乳ガンを発病。以来20年間、誰にも病を明かさず抗ガン治療を続け、再発の不安と闘い、めげそうな心を強く強く奮い立たせながらひたすら女優業に打ち込んできたスーちゃん。女優としても一人の人間としても、まさにこれからという55歳でこの世を去らなければならなかったその無念と悔しさはいかばかりかと残念でたまらない。
1974年、キャンディーズのデビュー当時4歳だったわたしにとって、その思い出の始まりは大ヒット曲「年下の男の子」からである。わたしはとりわけランちゃんが大好きだった。1歳下の弟と2歳下の近所の男の子を強制的にスーちゃん、ミキちゃん役に任命し、2人を泣かすまでスパルタ指導。母親や近所のおばちゃんが集まれば、衣装代わりに母親のスカーフや着物の絞り帯を身体に巻き付け、センターのランちゃんになりきって気分良く歌い踊っていた。
なぜ、そんなにもキャンディーズが好きだったのか。それは、当時のちびっこたちに絶大な人気を誇っていたお笑い番組「見ごろ食べごろ笑いごろ」や「8時だよ!全員集合」のコントで見せるキャンディーズの体当たりの演技に、アイドルだから、可愛いから、女の子だからという生半可なちゃちな「甘え」が一切なかったからである。子どもながらに、そこが「偉い」と思った。7、8歳の少女といえども、同性として見るべき所はちゃんと見ているのだ。だから女の子は手強いのである。
「団塊世代のアイドル」として語られることが多いキャンディーズだが、確かに葬儀に参列したファンの多くが企業サラリーマンや喫茶バーのマスター風のラフなおじさん、いつの時代も変わらない一途な瞳をした中高年オタクといった50〜60代男性がほとんどだった。そんないくつになってもキャンディーズを忘れないファンのために献花台や焼香の場を設け、自分を応援してくれたファンのみんなに見送られての葬儀を望んだスーちゃんに、何よりファンを大切に重んじる昭和の芸能人の流儀を見る思いがした。結婚、離婚、出産などプライベートな報告はFAX、ブログで済ませられる平成の芸能人とは、その背に負っている不自由な責任感が違うのである。もちろん、人間である以上、いくらファンとはいえ迷惑な人もいる。はっきり言ってキモい人も、正直ウザい人もいるだろう。でも、そういうファンあっての自分である自己認識の重みがキャンディーズの頃と今とでは横綱と幕下ほど差があるような気がする。どっちがいい悪いではなく、伝わってくる気迫、格が違うとしかいいようがない。
今から33年前の1978年、春。「普通の女の子に戻りたい」と、キャンディーズは解散した。後楽園球場(現・東京ドーム)で行われた「解散コンサート」が放映された日は、わたしが初めて「テレビを見て泣いた日」でもある。人間、どうでもいいことほど、やたら憶えているものである。「わたしたちは幸せでした!」と肩を抱き合い、泣きながら歌う3人の姿を見て自分が何を思って泣いたのか、いまだにはっきり記憶している。生まれつき物事をやたら悲観的にとらえる性質らしく、「どんなに仲良くても、どんなに楽しくても、いつか離れるときがくる。大きくなんかなりたくない」と、やたら暗く寂しい気持ちになった。「別れがあるから出会いがある」「卒業と旅立ち」「ハロー・グッバイ」などという言葉やロジックなど8歳の自分の頭にあるはずもない。いつの日か自分にも、大好きな人と離ればなれに「ひとり」になるときが来る。わたしもキャンディーズみたいに泣かなあかんときが来ると、解散云々よりもそうなるのがイヤで、結局は自分の将来を思って泣いていたような気がする。
それは、わたしにとってキャンディーズはアイドルというより「となりのお姉さん」的な存在だったからかもしれない。いつも明るい笑顔で楽しませてくれた大好きなラン姉ちゃん、スー姉ちゃん、ミキ姉ちゃんが泣いている。今まで見た中で一番華やかで、きれいで、まばゆく輝く衣装を身につけ、「幸せでした!」と泣いている。わたしはキャンディーズの解散に「娘時代の終わり」のような漠然とした恐怖を感じてしまったのかもしれない。「金襴緞子の帯締めながら、花嫁御陵はなぜ泣くのでしょ〜」の歌のように、嫁いでいく近所のお姉さんの涙の理由を、首を傾げてじっと見つめる小さい女の子のような面持ちで。
可愛い可愛いで済まされる花の季節はあっという間。しかも、元からそないに可愛くなければ、最初からそんな季節はない。蝶よ花よの娘時代を自分で終わらせるか、人に終わらされるか。戦中戦後生まれの母親世代までは、親や親戚や世の中に終わらされた。でもキャンディーズは、自分たちの意志で「ひとり立ちして旅立つ時」を決めた。女の子も20歳を過ぎたら、自分の足で立って歩いて行ける一人前の人間にならなければならない。だから、自分の人生、どうやって生きていくか見つめ直すために運命共同体であるキャンディーズを解散し、ひとりになる。それが「普通の女の子に戻りたい」という言葉の真意だったと、解散後の復帰会見でランちゃんは語っている。
「普通の女の子では飽き足らなくなったのですか?」と嫌味ったらしい質問をぶつける芸能記者たちに、「ひとりの人間として自立するためには、キャンディーズを離れなくてはならないと。そういう深い意味を込めた言葉でしたが伝わらなかったのが残念です」と毅然と言い放ち一蹴したランちゃん。若干22歳とは思えないそのクールで落ち着いた知的な振る舞いにも驚かされるが、それより何より、こうしたキャンディーズの自己実現に向けた決意と行動は、’60〜70年代生まれのわたしたちの「普通の価値感」になっていることに、今さらながらキャンディーズの存在の大きさを思い知らされる。わたしたちは、ランちゃん・スーちゃん・ミキちゃん3人のお姉ちゃんの後を、無意識にも追いかけていたのだと思うと、なおさら懐かしくありがたく涙がこぼれてくる。
25日の今日、青山葬儀場でいとなまれた告別式で、肩を寄せ合い手を握り合いスーちゃん・田中好子さんを失った哀しみに涙するランちゃん、ミキちゃん2人の姿に、キャンディーズの友情の深さを知らされた。女優として主婦として、それぞれ別々の道を歩みながらも、互いの家に集まって深夜までお菓子をポリポリつまみながらしゃべり明かしたという3人のエピソードを聞くと、長く苦しい闘病の中にあっても、それでもスーちゃんは幸せだったのだと少し救われる。そんな3人のおしゃべりな様子をそばで見ながら「誰も入り込めない3人の世界」を感じたという田中好子さんの夫・喪主の小達さん。SATCで言えば、キャリーたち4人の物語に花を添えるそれぞれのパートナー、ビッグ、ハリー、スティーブの役回りである。「毎度会うたび、よくそんなにしゃべることがあるなぁ」と旦那が呆れ返るような女同士の時間、つながりを持ち続けることがどれほど幸せなことか。そして、どれほど難しいことか。最期を看取ってほしいと思えるような一生の友を持てることは、それこそ女の勲章に等しいくらい誇らしく喜ばしいことではないだろうか。
さらに、わたしが感銘を受けたのは、ミキちゃんが弔辞の中で述べていた「わたしたち3人プラス豊さん」。ここ最近は、ランさんの家に集まり、3人プラス豊さんの4人で楽しく語り合うことが多かったのだとか。「豊さん」とは紛れもなく伊藤蘭の夫であり俳優の水谷豊のことだが、誰にも入れない女のおしゃべりな世界に自然に溶け込み、しかも女性陣に「プラス・ワン」とその存在を認められるとは…。ゲイに匹敵する鋭い感性の持ち主か、かわいげのある「イジラレ役」か。たぶん、きっと後者だろうと思う。
キャンディーズは、普通の女の子として「自立することの大切さ」とともに、夫・パートナー・家庭がプラスされても変わらない女の友情があることを教えてくれた。だからわたしにとってキャンディーズは、男なら「兄貴」と呼びたいほど、永遠にかなわない「お姉ちゃん」なのである。多感な少女期、キャンディーズに出会えたわたしたちも、わたしたちで幸せでした!

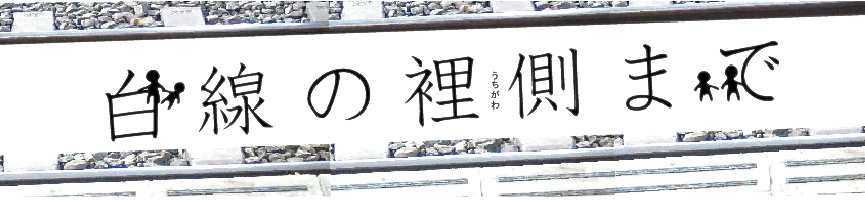

1件のコメント
女性の立場からキャンディーズを長期にわたり、愛し続ける解釈に感謝いたします。
1676日で270曲以上を残したキャンディーズの、努力の結果身につけた奇跡といえるハーモニーの素晴らしさに惚れた私としては、あの日、青山に行かなければ一生後悔すると前日から手に付かない仕事を放り出して、盛大に送ってほしいとのスーちゃんの希望どおりにするため、スーツの上に着るランちゃんカラーの赤い法被を持参しました(残念ながら青が無いので)。日本の儀式の中でも極めて作法が限定されている葬儀の場です。誰も赤だ、黄色だ青だと原色の法被を着る不心得者はいません。見渡せば2000人以上の黒スーツの参列者の中にやっと青いスーちゃんカラーの法被姿が1名だけです。こちらは赤、極めて不謹慎です。心の中で葛藤しました。葬儀に合わせるか、故人の遺志か。私は心の中で1977年に解散宣言をしたのち、彼女たちの意思を尊重するのがファンだろうと解散を支持した当時のことを。赤い法被を黒いスーツの上から着ると、報道陣の目が一斉に向きます。その姿で祭壇に向かうと、ご親戚からの刺さるような視線を感じました。ファン仲間とすれ違った際、「なんで着ないの」とたずねると、黒スーツ姿で「大人ですから」との返事。誰のための葬儀だよ。いつの間に変な大人になったんだ。心の中で怒りましたが、スーチャンが喜んでくれれば良い。黒一色の会場でただ二人の反逆児でした。しかし、ドラマはここからでした。出棺が近づくと、やはりスーちゃんの意思を最優先しようと決断したようで、持参してきた法被を10数人が一斉に着始め、場合によっては止めようとしていた約300本の青い紙テープを参列者に配布し始めます。その行動は長年キャンディーズを応援してきた熟練ファンのなせる業です。通路に立ち、スーちゃんに当たって怪我をさせてはいけないので、テープの芯を抜いてくださいと、即席の心抜き取り講座開始です。投げる方向は天国に向けて頭上へなげるように。掛け声により開始します。すべての伝達が瞬時に実施されました。この光景を見ていた多数の報道陣から、「キャンデイーズってすごいファンがいるんだね」と聞こえます。スーちゃんの病床でのテープが会場に流れ、このような方のファンであったことを誇りに思い涙し、あなたに夢中の音楽が流れた瞬間、スーちゃんを盛大に送る青いテープの絨毯となって通路を彩りました。葬儀場でテープ投げは不謹慎だとか、法被姿は何事かとの批判もなく、スーちゃんの希望どおりに送れたことをファンの一人として心から誇りに思っています。もちろん投げたテープは、「撤収」の掛け声とともに数分ですべて回収するいつもの光景でした。
最後に33年も変わらずキャンディーズを聞き続けられるのは、シングルで発売された17曲(つばさを除く)以外の、アルバムに収録された200曲以上が、素晴らしいクォリティで、現在の音楽をも越えているからです。
コメントする ※すべて必須項目です。投稿されたコメントは運営者の承認後に公開されます。